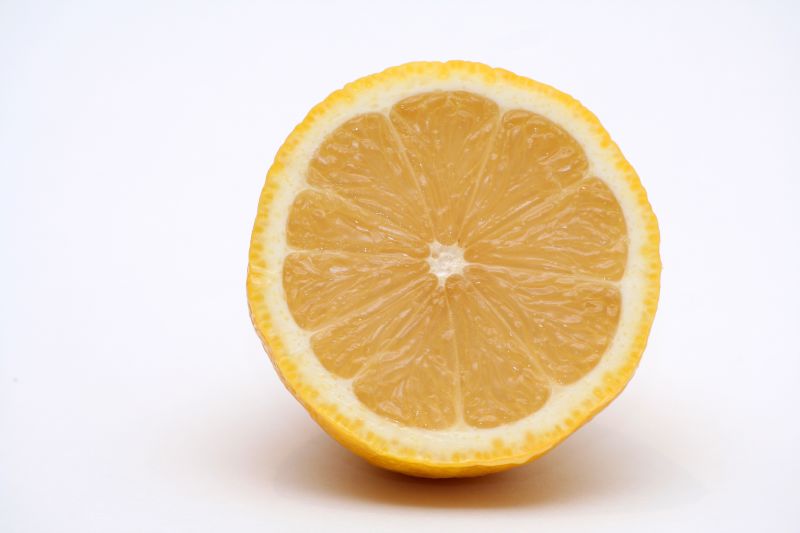> 健康・美容チェック > 脂肪肝 > 女性が注意したい脂肪肝の原因とは|肝臓を守る方法は「おさかなすきやね」|あさイチ(NHK)
2012年9月10日放送のNHKあさイチで「女性が危ない!脂肪肝」が取り上げられ、「脂肪肝」への検索数が急増しています。
→ 脂肪肝とは|脂肪肝の症状・原因・治し方 についてはこちら
【目次】
■女性こそ肝臓を大事に!

by David Simmonds(画像:Creative Commons)
40代以降の女性に肝臓の病気は要注意です。
女性がなぜ肝臓に注意が必要かというのは2つあります。
一つは、女性は男性よりも体も肝臓も小さいことから、血中アルコール濃度は男性よりも女性のほうが高くなりやすいということです。
もう一つは、女性ホルモンにはアルコールの分解を抑える作用があるのですが、40歳以上は女性ホルモンが減少する傾向にあるため、それまで大丈夫だった人も肝臓に負担がかかりやすくなっていることです。
【関連記事】
■脂肪肝に注意!
成人の3人に1人、約3000万人はいるのが脂肪肝であり、決して珍しい病気とはいえず、いつ自分がなってもおかしくない病気です。
脂肪肝と言うとは、まだまだお酒を好きな人の病気というイメージを持っている人も多いと思いますが、実は、お酒を飲まない人も脂肪肝になることがあり、そのまま放っておくと、肝硬変や肝臓がんになる恐れがあり、また、糖尿病の発症リスクが高くなったり、動脈硬化の促進といったリスクもあります。
■女性が注意したい脂肪肝の原因とは?
脂肪肝とは、肝臓に中性脂肪が蓄積された状態のことをいいますが、その原因の中には、「甘いものの食べ過ぎ」があります。
お菓子や果物には「糖質」が多く含まれており、糖質が肝臓で中性脂肪になり、それがたまることで脂肪肝になってしまうのです。
■脂肪肝危険度チェックリスト
・朝食を食べない
・夜食
・間食
・果物
・一品もの
・食べ残さない
・早食い
・睡眠6時間以下
・体型が変わった
・エスカレーター
※肝臓専門医の栗原毅さんによれば、5つ以上当てはまる場合は脂肪肝の可能性が高いそうです。
糖化・AGEsを知ってアンチエイジング・病気予防という記事で紹介した糖化チェックの内容と近いものがありますね。
■糖化チェック
□甘いものの間食が多い
□丼物が多い
□アメやお菓子が周りにある
□ペットボトルの清涼飲料水をよく飲む
□甘辛い料理が多い
□ごはんや麺類などの主食をしっかり食べたい
□野菜や豆類が嫌い
□夜食を食べることが多い
□早食いをする
□運動不足
脂肪肝危険度チェックリストのポイントを考えてみました。
■体内時計の乱れ
●朝食を食べない
体内時計 ダイエット|たけしの家庭の医学 5月25日
内臓:朝食がリセット方法
※内臓の時計遺伝子をリセットするには、たんぱく質が必要。
朝食にタンパク質を取ることで、その刺激が小腸に到達し、小腸の時計遺伝子を動かす。
すると、その信号が胃や肝臓にも伝わり、エネルギー代謝がはじまる。
そのため、タンパク質の少ない朝食の場合は、時計遺伝子はリセットされず、内臓の機能も低下したままになります。
すると、すでに活性化している脳が、栄養分が入っていないことを感知し、体が飢餓状態にあると判断します。
そのような状態で昼食をとると、飢餓状態に対応するため、体内に脂肪をため込む機能がスタート。
脂肪がエネルギーとして消費されず、コレステロール量が増加してしまう。
●夜食
夜食を取ると、肝臓の「時計遺伝子」が乱れ、代謝異常になり、太りやすくなる?
夜食など不規則な時間に食事を摂ると、インスリンの作用で肝臓の時計遺伝子のリズムが乱れてしまい、肝臓の代謝機能に異常を引き起こすことがわかったそうです。
●睡眠6時間以下
夜更かしは肥満を招く
睡眠不足になると、食欲のバランスをとるグレリンとレプチンのバランスに影響を与えてしまい、食欲が増え、満腹を感じにくくなるそうです。
【関連記事】
■糖質の摂り過ぎ
●間食
間食は食べ物の選び方次第では問題ないと思いますが、比較的おやつには糖質が多いですよね。
●果物
また、果物にも糖質が多いです。
栗原院長によれば、果物は砂糖よりも吸収が良く、果物の糖が中性脂肪に合成されて肝臓にたまるそうです。
●一品もの
そして一品物(例えばどんぶりもの)の場合、炭水化物、つまり糖質を多くとりがちです。
■食べ過ぎる食習慣
●食べ残さない
●早食い
早食いは食べ過ぎの原因ともなりかねません。
ゆっくり食べることで、満腹中枢が働き、食べ過ぎを防いでくれるはずです。
また、食事への満足感も高まりそうです。
【関連記事】
■運動不足
●体型が変わった
●エスカレーター
糖尿病は「過食」「運動不足」が原因で加速する!
食事をすると血糖が上がります。
血糖はインスリンだけでコントロールされるのではなく、筋肉に取り込んで消費したり、脂肪細胞へ取り込み蓄積したり、肝臓で糖の取り込み・放出をするなど身体の中で微調整されているそうです。
人間の体のメカニズムというのはよくできているというのがわかります。
しかし、食べ過ぎや運動不足になるとこの体の中の血糖コントロールするメカニズムが崩れてしまうようです。
■脂肪肝をチェックする重要な数値
ALT(GPT)が20以上 の場合は脂肪肝である可能性が高い。
中性脂肪が150を超えている 場合は、脂肪肝にいつなってもおかしくない予備軍。
ALT(GPT)が20以上 の場合は脂肪肝である可能性が高く(30以上は脂肪肝)、中性脂肪の値が150を超えている 場合は、いつ脂肪肝になってもおかしくない状態なので注意が必要です。
→ 肝臓の数値・検査値|ALT(GPT)・AST(GOT)・γ-GTP についてはこちら
■脂肪肝は万病の元!
・脂肪肝→非アルコール性脂肪肝炎→肝硬変・肝臓がん
・脂肪肝→糖尿病→失明・透析・下肢切断
・脂肪肝→動脈硬化→脳こうそく・狭心症・心筋こうそく
脂肪肝は、肝臓の病気であるNASHや肝硬変、肝臓がんになるおそれがあるだけでなく、糖尿病や動脈硬化といった病気の発症リスクが高くなるおそれがあるので、注意が必要です。
■ダイエットしても脂肪肝になる!?
極端なダイエットをすると、脂肪肝になることがあります。特に糖質を多く含むお米やパンなど炭水化物を極力とらないダイエットをすると「低栄養性脂肪肝」になります。
肝臓には一定量の脂肪が必要であり、糖質を極端に制限すると、肝臓は機能障害を防ごうとあわてて体中から脂肪をかき集めてしまい、脂肪肝になるのです。つまり、糖質のとりすぎで脂肪肝になりますが、とらなさすぎでも脂肪肝になってしまうのです。
ダイエットをしても脂肪肝になることがあると聞いて驚く方もいるかと思います。
糖質のとりすぎでも脂肪肝になるおそれがありますが、反対にとらなさすぎでも脂肪肝になってしまうので、何事も適量が大事なんですね。
■脂肪肝を防ぐ食事
1.糖質をとりすぎない
糖質は肝臓で体のエネルギー源である中性脂肪に合成されるので、適量の摂取は必要ですが、食べすぎは脂肪肝になってしまいます。
お菓子などの甘いものはもちろん、お米やパンなど炭水化物の食べすぎも注意が必要です。
糖質を取り過ぎないようにするために、間食では甘いモノをできるだけとらないようにすることや炭水化物が多い一品ものだけを食べるということを避けたほうが良いようです。
2.野菜やキノコは1日350グラム以上
野菜やキノコは糖質の吸収を遅らせるなどの効果があります。その際、一食にすべて食べるのでなく、朝昼晩、各食ごとに分けて食べましょう。
血糖値を上げ過ぎない食事と同様に、おかずと汁物を先に食べ、ひと息ついてからご飯やパンに手を伸ばすようにするとよさそうです。
3.体を温める食材をとる
ショウガ、にんにく、とうがらしなどは新陳代謝を促進させ、ついてしまった脂肪の燃焼を助けます。
体内時計 ダイエット|たけしの家庭の医学 5月25日という記事でも紹介しましたが、内臓の時計遺伝子をリセットするには朝食(たんぱく質)をとることが重要なのだそうです。
体を温めるためにも、たんぱく質を摂ることが大事なので、内臓の時計遺伝子をリセッツするためにも、そして体を温めるためにも、タンパク質をとることを忘れずに!
ちなみに、体を温める食品で冬太りを防ごう!によれば、冷たい食べ物や飲み物、体を冷やす性質を持つ食材を摂り続けると、体が冷やされてしまい、新陳代謝が落ちて、太りやすい体になったり、肩こり・頭痛などの不調が起きたり、病気になりやすくなるそうです。
⇒ 低体温 について詳しくはコチラ
【関連記事】
春には、たんぱく質・旬の食材を取り入れて、肝臓をいたわろう!
そんな弱ってしまった肝機能の回復に欠かせないのがたんぱく質です。
たんぱく質は筋肉を作りあげるのにも重要な役割をしますが、肝臓にたまった脂肪(中性脂肪)を血液中に送り込んで出してくれる役割もしています。
たんぱく質が極端に不足してしますうと脂肪肝になる恐れもあるのです。
この場合、動物性たんぱく質ばかり摂取すると脂肪分も取りすぎてしまい余計に肝臓が疲れてしまうことも。
おすすめは高たんぱくで低脂肪のお豆腐や大豆製品を中心に、動物性と植物性をバランスよく摂取することです。
■肝臓にやさしい食生活のための8品目
おさかなすきやね(オサカナスキヤネ)で覚えましょう!
オ:オリーブオイル
サ:魚類
カ:海藻類
ナ:納豆
ス:酢
キ:キノコ
ヤ:野菜類
ネ:ネギ類

【スーパーセール】オイスターFゴールド|タウリン・亜鉛・アミノ酸サプリ
通常価格7,560円(税込)をスーパーセール価格6,615円(税込)で販売いたします!
【関連記事】
 肝臓関連ワード
肝臓関連ワード
続きを読む 【あさイチ】女性が注意したい脂肪肝の原因(甘いものの食べ過ぎ)|オリーブオイルと脂肪肝|肝臓を守る方法は「おさかなすきやね」 →
 糖尿病関連ワード
糖尿病関連ワード


 肝臓関連ワード
肝臓関連ワード