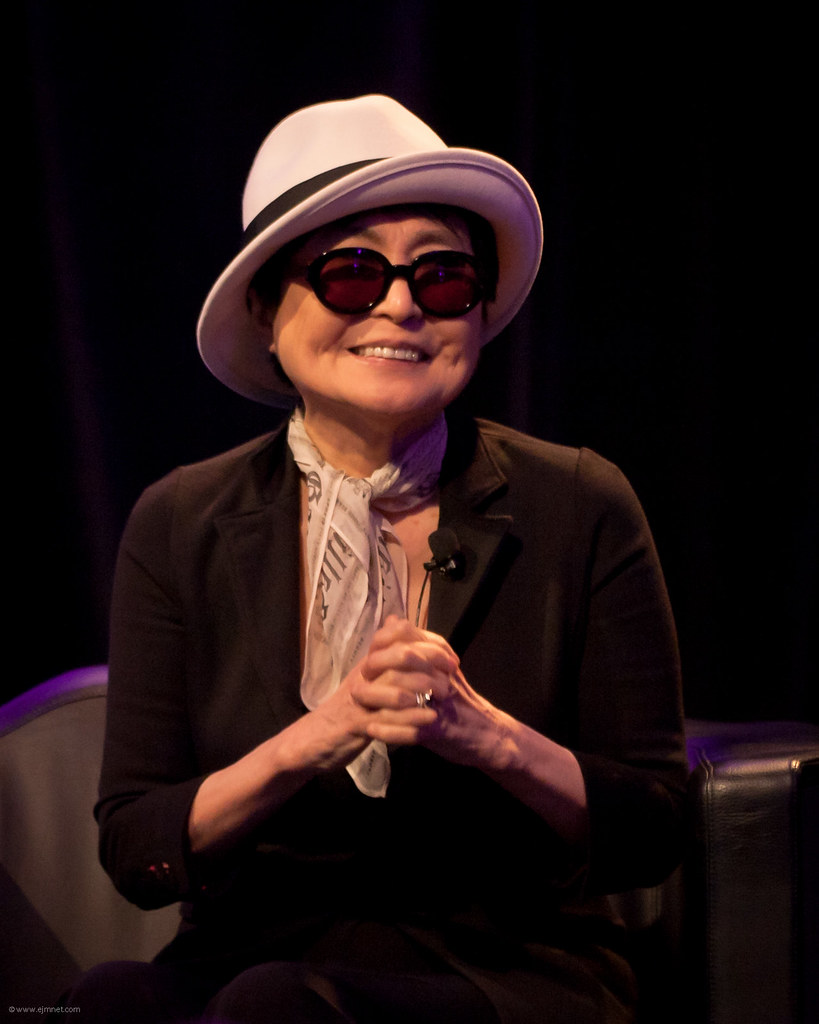by LASZLO ILYES(画像:Creative Commons)
> 健康・美容チェック > 目の病気 > 「目薬後に目をパチパチ」は間違い!?目薬の点眼方法、不適切が9割超|正しい目薬のさし方とは
「正しい目薬の差し方」が話題 漫画家・蛇蔵氏がわかりやすい絵入りで紹介
(2016/3/1、livedoor)
絵では、目薬を差した後に目頭から流れないよう、目をつぶり、目頭を人差し指で1分~5分、そっと押さえると説明している。
漫画家・蛇蔵さんがTwitter上で、「正しい目薬の差し方」を投稿し、話題なのだそうです。
「目薬後に目をパチパチ」は間違い!?目薬の点眼方法、不適切が9割超|正しい目薬のさし方とはによれば、目薬をした後に「目をぱちぱちさせている」など間違った点眼方法をしている人が9割を超えているそうです。
正しい目薬の差し方は、薬が鼻やのどに流れ出てしまわないように「しばらくの間、目頭を押さえながら目を閉じている」で、この行動をとっているのは、わずか5.8%だったそうです。
目をぱちぱちさせたりするなど誤った使い方すると、目の外に薬が流れてしまったり、鼻やのどに流れてしまって「効果が十分に得られない」そうです。
■正しい目薬のさし方(点眼方法)
正しい点眼方法についてのポイントは2つ。
●目薬は一度に一滴でよい
目薬は1度に2滴以上さした方が効果的だと考えている人が多いようです。
しかし、1滴の量は目の中にためることができる量にあわせているため、それ以上さしても目の外にあふれてしまうので、効果が高くなることはないそうです。
●しばらくの間、目頭を押さえながら目を閉じる
薬が鼻やのどに流れ出てしまわないように、目頭を押さえながら目を閉じましょう。
正しい点眼方法で、きちんと目の病気を治しましょう。
【関連記事】