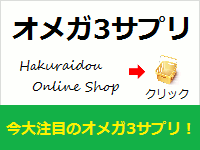> 健康・美容チェック > 肺の病気(呼吸器の病気) > 肺がん > 肺がんを予防するにはどうしたらよいか?|肺がんは喫煙者だけにおこる病気ではない
肺がんを予防するにはどうしたらよいか。
by Yale Rosen(画像:Creative Commons)
筑紫さんの命奪った…がん死亡数でトップ「肺がん」
(2008/11/15、夕刊フジ)
7日、肺がんで死去したジャーナリストでニュースキャスターの筑紫哲也さん(享年73)。昨年5月のがん告白から1年半の闘病の末に力尽きる格好となったが、筑紫さんは昔からの喫煙派のたばこ好きだった。
筑紫さんは昔から喫煙派のたばこ好きだったそうです。
やはりタバコが肺がんのリスク要因の一つであり、禁煙が肺がん予防の大事な予防法ではあるようですが、記事によると、肺がんは喫煙者だけにおこる病気ではないと忠告しています。
「肺がんには大きく分けて小細胞がんと非小細胞がんの2種類があり、最も多いのは非小細胞がんに分類される腺がん。
これは喫煙の有無とは関係なく発症する危険性が高く、たばこを吸わないからといって安心はできません」と長医師は注意を促している。
たばこが肺がんのリスク要因ではありますが、たばこを吸わないからといって安心はできないようです。
では、肺がんはどのようにすれば予防できるのでしょうか。
肺がんは、現在日本人のがんによる死亡者数でトップ。その理由はいくつか考えられるが、最も懸念すべき点は「早期発見の難しさ」にある。大阪府済生会吹田病院呼吸器病センター長の長澄人医師が解説する。
「肺がんの症状には血痰や息苦しさ、長く続く咳などがあるが、いずれも症状が出た頃には病気が進んでいることが多い。症状が出る前に発見できるか否かが分かれ道になってきます」
肺がんの症状が出る前に、早期発見することが肺がんを早期治療する方法といえそうです。
そうなると、定期的に検診を受ければよいということになりますが、記事によると、そうとも言えないそうです。
「50歳あたりから発症頻度が高まり始め、70歳前後でピークになる。
会社や自治体の健康診断では単純レントゲン撮影しかメニューにないことが多く、これだと小さながんは見落とす危険性がある。
手術が可能な早期の段階で見つけるためには、年に1度は胸部CTを撮るのが理想的。
そのためには人間ドックを受けて、メニューに胸部CTがない場合はオプションで加えるくらいの積極的な姿勢が必要になってきます」(長医師)。
単に検診を受ければよいということではなく、手術が可能な早期の段階で見つけるためには、人間ドックで胸部CTを撮るなど、肺がん予防に対して自らが積極的な行動が必要になるようです。
肺がんを予防するためにも、定期的に人間ドックで自分の体の状態をしっかり把握していくことが肺がんの早期発見において一番重要なようです。
→ 肺がんの症状・原因・予防するための検査 について詳しくはこちら