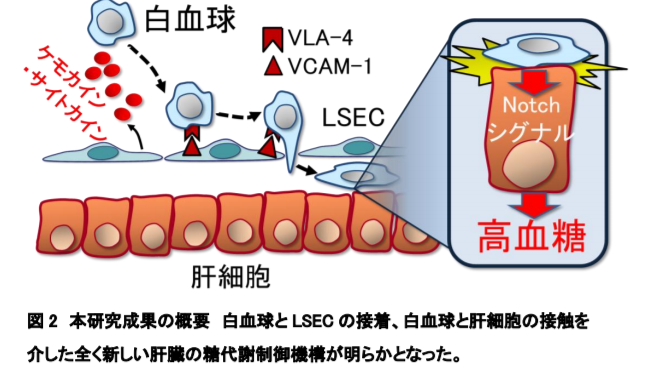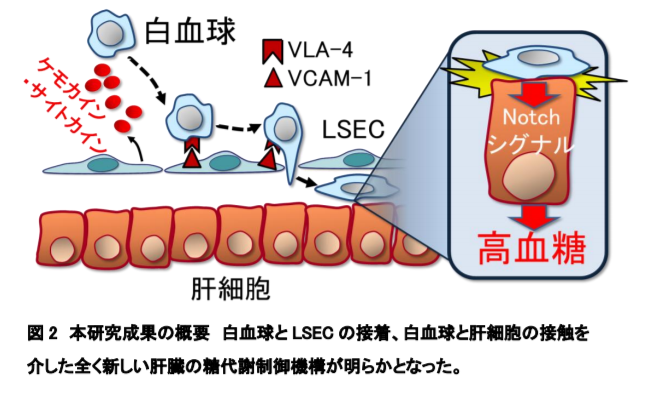> 健康・美容チェック > 肝臓 > 【さんま御殿】鷲見玲奈アナはテレ東時代に週7、8回飲み会に連れ出され肝臓を壊したことを告白
【目次】
■【さんま御殿】鷲見玲奈アナはテレ東時代に週7、8回飲み会に連れ出され肝臓を壊したことを告白
by Timothy Krause(画像:Creative Commons)
2020年8月4日放送の「踊る!さんま御殿」に出演した鷲見玲奈さんは上司からの誘いは断ってはいけないものと思って、テレビ東京に勤めていたときの飲み会にはすべて参加していたため、大変な時には週7、8回ほど、最長2週間連続ということもあり、肝臓を壊してしまったそうです。
鷲見玲奈「肝臓、コレステロールの数値引っかかった」過去 テレ東時代の20代半ば その原因は
(2022/9/19、スポニチアネックス)
「20代半ばで『C3』とか出たことあって。Aが一番良いんですけど、再検査になって。肝臓とコレステロール値とかいくつかありました」と振り返った。
女性は飲酒量(アルコール)が男性と同じでも、肝臓は先に悪化する!によれば、アルコールを摂取すると、その大半が肝臓で代謝され、有害なアセトアルデヒドとなった後に酢酸に分解されますが、女性は男性よりも体も肝臓も小さいことから、血中アルコール濃度は男性よりも女性のほうが高くなり、また、女性ホルモンにはアルコールの分解を抑える作用があるともいわれているため、女性は男性よりもアルコールの適量は少なくしたほうが良いようです。
9割の女性が疲れている!?肝臓が疲れているのかもしれません!肝臓を守り中性脂肪を減らす方法!によれば、肝臓には代謝や解毒といった身体にとって大事な機能があるのですが、体の疲れの原因である「睡眠不足」や「ストレス」といったものが、肝臓に負担をかけることにより、肝臓の機能が低下し、ますます疲れてしまうということが考えられるようです。
約8割の女性が肝臓ケアを意識していない!?|ブロッコリースプラウトなどに含まれるスルフォラファンを積極的に摂取しよう!によれば、カゴメが20代から50代の男女1000人に「食生活と健康診断に関する意識調査」を行なったところ、約8割の女性が自身の肝臓については気をつけていないことがわかったそうです。
最近の話題で言えば、外出自粛期間中のオンライン飲み会(zoom飲み会)では家飲みであるため、ついつい安心して飲み過ぎてしまうケースがあるということでした。
肝臓を壊さないようにしっかりとケアをしていきましょう!
→ 肝臓とは|肝臓の機能・働き・位置(場所) について詳しくはこちら
→ コレステロールとは|コレステロール値を下げる食品・食事 について詳しくはこちら
→ 休肝日の取り方(過ごし方)・ペースの目安・休肝日は必要か? について詳しくはこちら について詳しくはこちら
■肝臓を守り、中性脂肪を減らす方法
肝臓に負担をかけないようにするには、低カロリー低脂肪の食事、腹八分目の食事の量にする、アルコールを控えめにする、運動する機会を作る、などです。
●まごわやさしい
肝臓を助ける食事としては、肝機能を助けるタウリンを含む食事や「まごわやさしい」をキーワードにした食事をすること。
さまざまな食材の組み合わせのキーワードは「まごわやさしい」。
- 「ま」は、豆類
- 「ご」は、ゴマ類
- 「わ」は、わかめなど海藻類
- 「や」は、野菜類
- 「さ」は、魚(魚介類)
- 「し」は、しいたけなどきのこ類
- 「い」は、いも類
●肝機能の数値をチェック
できれば、定期的な血液検査で肝機能の数値をチェックしていきましょう。
●タウリン
肝臓(脂肪肝)に良い食事・食品は、タウリンを含む食品です。
肝臓から分泌される胆汁酸には、コレステロールを排泄させる働きがありますが、タウリンを含む食品を摂取するによって胆汁酸の分泌が増え、血液中のコレステロール値も下がります。
●タウリンには、酵素の働きを助ける働きがあるので、アルコールの分解を早め、肝臓への負担を軽くしてくれます。
また、タウリンには、腎臓や肝臓の有害ミネラルである毒素を濾過する機能をUPさせてくれます。
●カキに含まれるタウリンは、肝臓に溜まった中性脂肪を肝臓の外に出してくれ、そして肝臓(脂肪肝)を良くする働きがあるのです。
つまり、タウリンが肝臓に入ると、まず肝臓内の中性脂肪を取り除きます。さらに肝臓から脂肪を外に排出する働きをしてくれます。
食事療法としては、タウリンを含むカキなどを食事に取り入れましょう。
→ タウリンとは|タウリンの効果・効能|タウリンの多い食品・食べ物 について詳しくはこちら。
●不飽和脂肪酸やオメガ3脂肪酸の油
不飽和脂肪酸は、HDLコレステロールを増やし、LDLコレステロールを減らす働きがあると言われています。
また、オメガ3脂肪酸は、中性脂肪を減らす効果が期待されています。
→ オメガ3脂肪酸|オメガ3の効能・効果・食べ物・オメガ3ダイエット について詳しくはこちら