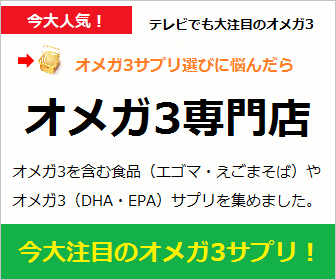■認知症の人への薬の提供方法の問題について考える|認知機能が低下すると、たくさんの薬が出ると、飲まない、飲めないことが起こる
by Brandon Giesbrecht(画像:Creative Commons)
【日薬担当者会議】検体測定室手引き、来月以降に‐認知症対策の充実求める
(2015/3/18、薬事日報)
老健局認知症ケアモデル推進官の真子美和氏は認知症施策推進総合戦略について概説すると共に、特に薬局薬剤師に向け「認知機能が低下すると、例えば、たくさんの薬が出ると、飲まない、飲めないことも起こる。そこで一包化することで対応できるのではないか」などとし、薬物療法の面での認知症対策への支援を求めた。
認知症の高齢者は2025年には730万人と推計|認知症に役立つ食べ物と生活習慣というニュース以降、「認知症」への関心の高まりを感じます。
【認知症について取り上げたテレビ番組 関連記事】
- オメガ3で健康に!認知症が予防できるエゴマ油|主治医が見つかる診療所 12月15日
- ココナッツオイルを使ったケトン体質ダイエット・肥満と認知症を改善する食品|世界ふしぎ発見 1月24日
- えごま油で認知症対策|林修の今でしょ!講座 2月24日
- 認知症予防(ココナッツオイル)|主治医が見つかる診療所 3月16日
今回のニュースで気になったのは、この部分。
認知機能が低下すると、例えば、たくさんの薬が出ると、飲まない、飲めないことも起こる。
飲む必要がある薬も認知機能の低下によって、飲まない・飲めないということが起こりうるということですね。
薬を飲むタイミングを通知するボトルを開発するADHERETECHという記事では、薬を飲むタイミング・量を通知するというのはいいサービスかとも思いましたが、今回の視点から言えば、認知機能が低下していると、通知に反応しないということが考えられるため、難しいですね。
※サポートする人がつくのでそこまで考える必要がないと思いましたが、サポートする人ができるだけ楽にサポートできるような仕組みづくりが重要です。
ですから、今回の記事では「一包化」することで対応することが提案されていましたが、一方に様々な薬を入れるのではなく、将来的には「これを飲めば大丈夫」というような患者に合わせたひとつの薬の形へと変わっていくのではないでしょうか。
認知症の人が増える時代を迎えることは間違いないと思いますので、こうした取り組みを行う企業・個人に注目が集まるでしょう。
→ 認知症対策|認知症に良い食べ物・栄養 について詳しくはこちら
【追記(2025年1月28日)】
笑福亭鶴瓶さん、体調不良で歩き方がおかしくなり救急病院へ 原因は「薬の飲み合わせ」/加藤茶さんと石破茂首相のケースと一緒に考えるによれば、笑福亭鶴瓶さんは空港で車いすに乗せられるほどの状態で歩き方がおかしくなり、夫人に歩き方がおかしいと指摘されて、救急病院に行ったそうです。
原因ははっきりとはわかっていないのですが、鶴瓶さんは薬の飲み合わせが関係しているのではないかと考えているようです。
鶴瓶さんは過去にNHK『鶴瓶の家族に乾杯』(2014年6月9日放送)で加藤茶さんと共演した時に加藤さんが返答が遅くて体調不良が心配されていた時(実際は風邪だったそうです)と同じ状態と自身の状態を重ね合わせていました。
先日ニュースにもなった首相指名選挙で居眠りする石破さんは実際は風邪気味で薬を服用したために起きたことだったそうです。
認知症ではなくても、薬の飲み合わせによっては体調不良を起こすことがあるのであれば、理想としては、薬をバラバラにもらったり、管理するのではなく、「一包化」する方法がないかを考えていく必要がありますね。
【アドヒアランス関連記事】
続きを読む 認知症の人への薬の提供方法の問題について考える|認知機能が低下すると、たくさんの薬が出ると、飲まない、飲めないことが起こる