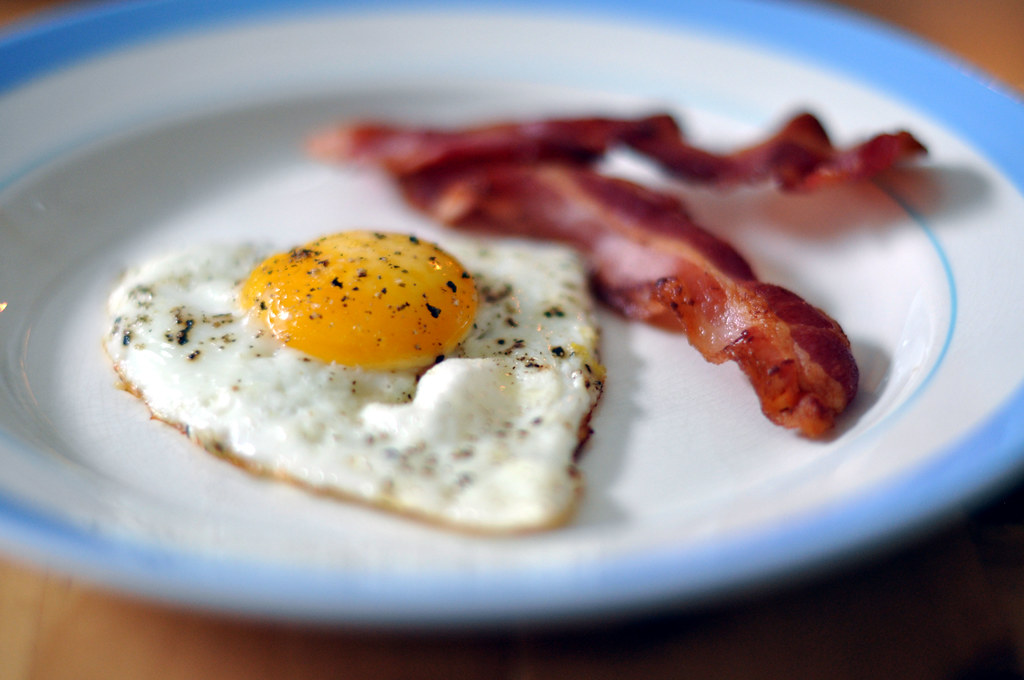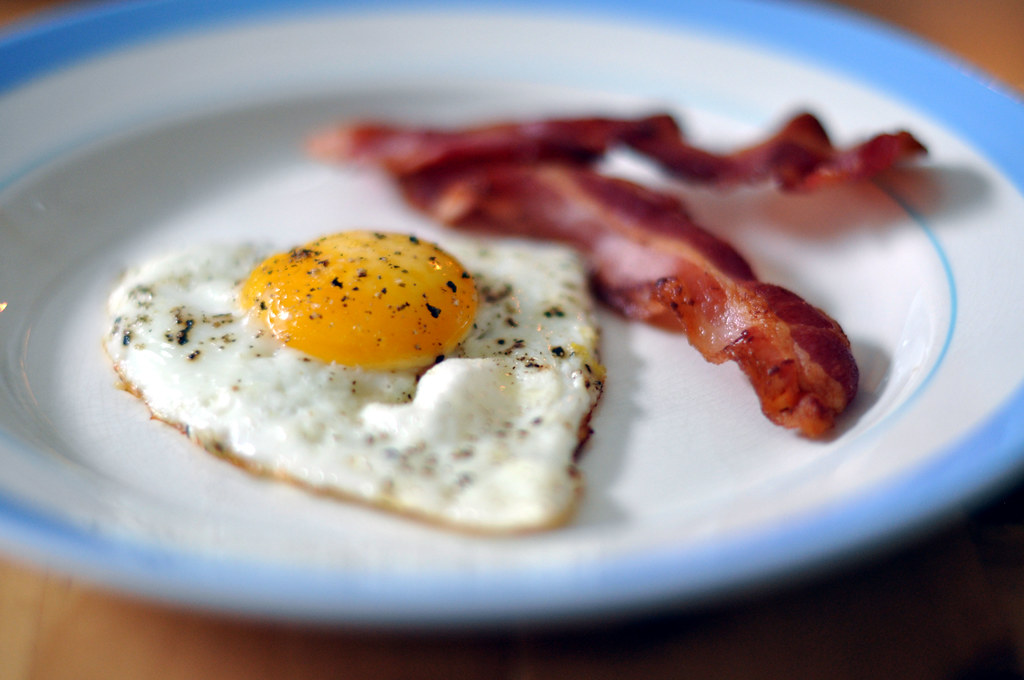
by cyclonebill(画像:Creative Commons)
> 健康・美容チェック > コレステロール > <管理栄養士に聞く>間違いだらけのコレステロール5つの罠
コレステロールに関しては、間違った知識を持っているひとが多いのではないでしょうか。
是非この記事を参考にしてみてください。
【目次】
1.コレステロールは人間にとって必須の物質
間違いだらけのコレステロール 5つの罠 – 管理栄養士に聞く
(2010/1/22、マイコミジャーナル)
生活習慣病の元凶と思われているコレステロール。
実は、人間のからだを維持するために必要不可欠であるという。
生命現象の根幹をなす細胞膜は、コレステロールが原料。
女性ホルモンや骨粗しょう症との関連で話題のビタミンDの前駆物質(前の段階の物質)の材料もコレステロールだ。
コレステロールは必要ないと考えている人も多いのではないでしょうか。
しかし、実際は、コレステロールは人間の体を維持するために、欠かすことのできない物質なのです。
まずは、コレステロールは必要であるという認識を持つようにしましょう。
【関連記事】
2.卵や魚卵を控えることは無意味
からだの中のコレステロールは、80%前後が主に肝臓でつくられている。
生命維持に必須のコレステロールは肝臓で必要に応じて生産量が調整されており、卵を1、2個食べても食べなくても関係ないとも言える。
たこやいか、いくらやたらこなどの魚卵、煮干しなどは、コレステロールを多く含むため敬遠されがちだ。
しかし、たこやいかはコレステロールが原因となる胆石症を予防するほか、糖尿病を予防・改善するはたらきのあるタウリンというアミノ酸の一種をたくさん含んでいるし、魚卵や煮干しには細胞の新陳代謝を活発にして老化を防ぐ核酸が豊富。
食材から摂ってもからだに影響の少ないコレステロールを控えるということは、多くの大切な栄養素を控えることになってしまう。
家族性高コレステロール血症以外では、むやみな食事制限はたんぱく質不足を引き起こしかねないので注意したい。
身体の中のコレステロールは主に肝臓で作られているため、食事でそれほど注意する必要はないようです。
コレステロールのとりすぎのために高コレステロール血症になっていると思っていましたので、卵や魚卵を控える必要があると思っていた人も多いのではないでしょうか。
しかし、卵や魚卵、たこ・いかを控えることはその他の大切な栄養素(例えば:タウリン)を控えることにもなりかねないですよね。
むやみな食事制限には注意したいところです。
【関連記事】
3.LDLコレステロールは悪玉ではない
一般的に、LDLコレステロールは悪玉、HDLコレステロールは善玉、といわれるためか、悪玉は悪く善玉はよいコレステロールといった誤解が少なくないが、生命現象の根幹をなすコレステロールにはそもそも悪も善もなく、どちらも不可欠なものである。
LDLコレステロールには、体内でつくられたコレステロールを組織に運ぶ重要なはたらきがあり、HDLコレステロールには、体内であまったコレステロールを回収して肝臓に運び、再利用する重要なはたらきがある。
これもよくある間違いですよね。
HDLコレステロールは善玉コレステロール、LDLコレステロールは悪玉コレステロールなので、そのネーミングからか、LDLコレステロールは必要がないものと思って敬遠されています。
しかし、両方共欠かすことのできないものです。
問題なのは、酸化LDLコレステロールなのだそうです。
酸化LDLコレステロールは血管壁に付着し、動脈硬化を引き起こすことがわかってきた。
本当の悪玉は、酸化LDLコレステロールなので、覚えておきたいですね。
→ 酸化悪玉コレステロールとは・原因・数値(基準値)・測定(検査)・対策 について詳しくはこちら
4.LDLコレステロールを真の悪玉にしないコツ
HDLコレステロールが低く、中性脂肪が高いと真の悪玉である酸化LDLコレステロールが増えてくるといわれている。
中性脂肪とは脂っこい料理だけではなく、ご飯やパン、麺などの糖質を摂ることでも増加するので、主食を抜いたり、少なくしたりして調整したい。
一方、卵や魚介類、肉類には、たんぱく質やビタミン、ミネラルが豊富なので、刺身、焼きもの、少量の油でのソテーなど、油を控えるように工夫して取り入れよう。
食パンや菓子パン、焼き菓子などに使われることの多いマーガリンやショートニング、ファストフードや出来合いの総菜などの揚げ油もできるだけ控えたいもの。
食事の総エネルギーを減らし、ウォーキングなどの軽い運動を継続的に行っていくと効果的だ。
LDLコレステロールを酸化LDLコレステロールにしないためにも、食事の仕方には改善が必要なようです。
ポイントは油の選び方、使い方にありそうですね。
また、食事の量を減らし、運動を継続することも大事なようです。
5.低コレステロール血症の方が危険!?
高いとよくないと考えられてきたコレステロールだが、最近では、むしろ低コレステロールの方がリスクが高いという研究結果が発表されるようになってきた。
そのひとつが「日本人はLDLコレステロールと中性脂肪の高い方が長生きする」というもの(※1)。
「コレステロールの値が低い人は、うつの症状を発現するケースが実に多い」。
「高コレステロール血症と診断された人のなかで、投薬によるコレステロール低下治療を受けた人と受けなかった人を比較したデータでは、投薬治療を受けていた人において自殺や事故死が多いという報告も少なくない」(※2)という指摘もある。
低コレステロール血症では死亡率がやや高くなるともいわれている。
動物性食品をあまり摂らない人、たんぱく質の摂取が少ない人は、コレステロールの不足に注意してほしい。
※1『 Cholesterol-lowering medicine testing: enigmatic and confusing』 Michel de Lorgeril
(コレステロール低下薬の検証:謎と混乱) 大櫛陽一 東海大学医学部教授
※2『「うつ」は食べ物が原因だった』溝口徹(青春出版社)
低コレステロールの方がリスクがあるという研究結果が発表されているそうです。
まだまだコレステロールに関しては今後の研究結果に注目しておく必要がありそうですね。
■コレステロール関連ワード
■コレステロールとは|コレステロール値を下げる食品・食事
■HDLコレステロールを増やす方法と善玉コレステロール吸う力をアップする方法
■総コレステロール値・基準値|総コレステロールが高い原因
■悪玉コレステロールを減らす方法|LDLコレステロールを下げる食品・食事
■悪玉コレステロールの数値(基準値)
■悪玉コレステロールが高い原因
■高脂血症とは|高コレステロール血症の症状・原因・食事
■動脈硬化とは|動脈硬化の症状・原因・改善方法
■中性脂肪とは・数値(正常値)・高い原因・下げる(減らす)