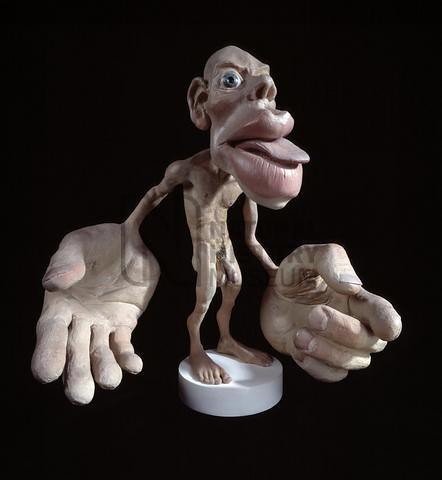【目次】
■ロコモティブシンドロームとは?

by Jaka Ostrovršnik(画像:Creative Commons)
『要介護』招く運動器症候群 ロコモティブシンドローム
(2009/8/14、東京新聞)
「ロコモティブシンドローム(運動器症候群)」という言葉を聞いたことがあるだろうか。
骨や筋肉、関節など運動器の働きが衰え、生活の自立度が低くなり、要介護の状態や要介護となる危険の高い状態のことをいう。
ロコモティブシンドローム(運動器症候群)とは、運動器の障害のために要介護となる危険の高い状態のことを言うようです。
■ロコモティブシンドロームの原因
ロコモティブシンドロームの原因は何なのでしょうか。
原因は、加齢による筋力やバランス能力の低下が考えられる。
加齢による筋力やバランス能力の低下によって、ロコモティブシンドロームになっているそうです。
老化のスピードが速い大腿筋を鍛える方法|大腿筋の老化のスピードは最も速いで紹介した石井直方さん(東京大学大学院筋生理学・トレーニング科学専門)によれば、筋肉量は30歳をピークに減少し始めるそうです。
なかでも大腿筋の老化は深刻で、30~70才までの40年間で、前側(大腿四頭筋)は2分の1、後ろ側(ハムストリングス)は3分の2にまで落ちることが実証されているそうです。
筋肉(とくに前側の筋肉)が衰えると、
- 椅子から立ち上がれない
- 転びそうになっても体を支えられない
- 骨は、筋肉を使えば使うほど刺激を受けて強化され、基本的に、太ももの筋量が多い人ほど骨の強度も高いそうなのですが、筋肉が衰え、活発に動けなくなると骨への刺激も減るため、転倒や歩行困難、最悪の場合は寝たきりになるおそれもある
になることが考えられます。
■ロコモティブシンドロームに当てはまる運動器の障害とは?
どういった運動器の障害がロコモティブシンドロームに当てはまるのでしょうか。
介護が必要となる運動器の障害には、関節の軟骨がすり減って痛む「変形性ひざ関節症や腰椎(ようつい)症」、骨量の減少で骨が弱くなり骨折しやすくなる「骨粗鬆(そしょう)症」、背骨の内部の神経が圧迫されて足腰のしびれや痛みが出る「脊柱(せきちゅう)管狭窄(きょうさく)症」などがある。
変形性膝関節症や骨粗鬆症、脊柱管狭窄症などが代表例といえそうです。
●変形性膝関節症
関節痛は、高齢になると、ほとんどの方が持っているといわれています。
その関節痛の多くが、関節軟骨の磨耗が原因の、「変形性膝関節症(へんけいせいしつかんせつしょう)」です。
通常、軟骨は、柔軟性と弾力性、なめらかさを持っており、関節のスムーズな動きを支えています。
しかし、老化や過激な運動などで、軟骨の消耗が進むと、骨同士が直接こすれあい、強い痛みを感じます。
つまり、変形性膝関節症とは、膝関節のクッションである軟骨のすり減りなどが原因となって、関節が変形したり、膝関節に炎症が起きたりすることで痛みが生じる病気です。
変形性膝関節症(関節痛や膝痛)に当てはまる方は、正座のしにくい方や階段の上り下りがつらい方、立ち仕事の多い方に多いです。
●脊柱管狭窄症
脊柱管狭窄症とは、神経の通り道である脊柱管(せきちゅうかん)が狭くなり、神経の通りが悪くなることで、背骨の内部の神経が圧迫されて足腰のしびれや痛みが出る病気です。
●骨粗しょう症
骨粗しょう症の原因は、カルシウム不足です。
血中のカルシウム濃度は一定ですので、カルシウムが不足し始めると、骨のカルシウムから補填をするようになります。
つまり、血中のカルシウムが不足すればするほど、骨のカルシウムも減っていくことで、骨がもろくなり、骨粗しょう症につながっていきます。
また、日光にあたることもなく運動もあまりしない生活を続けていると、骨の形成に大切なビタミンDが活性化されず骨粗鬆症になってしまいます。
■ロコモティブシンドロームの予防
ロコモティブシンドロームを予防するには、どうしたらよいのでしょうか。
ロコモティブシンドロームの考え方は、痛みに対する治療だけでは不十分で、筋力強化なども併せて運動の状態を向上させ、QOL(生活の質)を保つことを目指す。
それが、介護予防にもつながる。
痛みに対する治療だけでなく、日頃から筋力を強化することで運動の状態を維持していくことが、大事なようです。
毎日運動している人としていない人との間には体力に大きな差がある!?|2014年度体力・運動能力調査で紹介したスポーツ庁の2014年度体力・運動能力調査によれば、高齢者(65~79歳)で、ほとんど毎日運動している人と運動をしない人では、体力に大きな差があることがわかりました。
記事の中には、ロコモティブシンドロームの予防に取り組む目安の五項目が紹介されています。
日本整形外科学会は、予防に取り組む目安として五項目を紹介している。
片脚立ちで靴下がはけない
▽階段を上るのに手すりが必要
▽横断歩道を青信号で渡りきれない
▽十五分くらい続けて歩けない
▽家の中でつまずいたり滑ったりする-。
この5項目のうち、一つでも当てはまる人は、ロコモティブシンドロームを予防するロコモーショントレーニングを薦めているそうです。
効率よく筋力強化ができるのが目を開けての「片脚立ち」。
松井医長によると、片脚立ちは両脚立ちに比べ二・七五倍の負荷がかかり、一日三回、左右一分間の片脚立ちは、約五十三分間の歩行に相当するという。
支えが必要なら、机に手をついて行ってもよい。
「スクワット」はお尻を低く下ろせばより筋力が鍛えられるが、継続するには浅い角度の方が安全だ。
脚はかかとから三〇度くらい外側に開き、体重が脚の裏の中央にかかるように意識する。
現在の筋肉を維持しようという人がウォーキングだけをしても、筋肉は衰えていってしまいます。
筋肉を衰えさせないためにも、筋トレが必要。
ロコモティブシンドロームを予防するトレーニングとして紹介されているのは、「片脚立ち」と「スクワット」です。
片手だけまたは手を使わずに床に座ったり立ったりできる人は長生きできる?によれば、中高年で床に座ったり立ったりが片手だけで、または手を使わずにできる人は筋骨格がしっかりしており、それができない人に比べて長い寿命が期待できるそうです。
また、おすすめなのが「スロトレ」。
スロトレは、軽い負荷でありながらも、、すべての動作を“ゆっくり、止めずに、連続して行う”ことで筋肉が力を発揮している時間を引き延ばし休ませないため、筋肉量が増えるのに効果的なトレーニング方法です。
また、軽い負荷であるため、次のような方にもおすすめができます。
【ロコモ 関連記事】
続きを読む ロコモティブシンドロームになると要介護のリスクが高くなる?ロコモの原因・予防のためのトレーニング方法 →