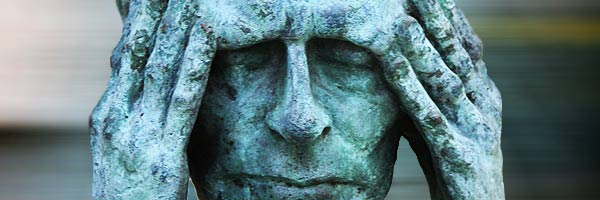by James Theophane(画像:Creative Commons)
> 健康・美容チェック > 冷え性 > 冷え性解消方法 > 「寒くなってきた」と思ったあなたに♥️2015年最新冷え対策特集
10月に入り、朝晩が冷え込んできて、「寒くなってきた」とつぶやく人も増えてきました。
季節の変わり目で、衣替えをしたり、防寒対策をする人も増えてくるのではないでしょうか。
そこで、今回は2015年の冷え対策を特集したいと思います。
【目次】
■国民総「冷え」時代になっている?|冷え性・低体温が健康にもたらす影響とは?
現代は多くの人が「冷え」を感じています。
人によっては、一年中「冷え」を感じているそうです。(冷えを1年中感じている人は25.9%!)
「冷え」といえば女性をイメージする方も多いと思いますが、今は男性も子供も「冷え」で悩んでいます。
【関連記事】
【男性と冷え関連記事】
【子供と冷え関連記事】
そして、先日若い人ほど冷え性?20代では3人に2人が冷えを感じているによれば、若い人ほど冷えを感じており、20代では3人に2人が冷えを感じているというアンケート調査が出ていました。
国民総「冷え」時代・国民総「低体温」時代といえるくらいです。
⇒ 冷え性の症状・冷え症の原因・手足の冷え についてはこちら。
⇒ 低体温|低体温の改善・原因・症状 についてはこちら。
⇒ 体温を上げる方法 についてはこちら。
⇒ 冷え性改善方法(食べ物・食事・運動・サプリ・ツボ)についてはこちら。
■冷えが招く症状とは?
冷え性といっても、人それぞれで冷えの感じ方は違っており、内臓型冷え性によれば、冷え性には、大きく分けると、5つのタイプがあります。
- 四肢末端型冷え性
手足の先が特に冷えてしまう - 下半身型冷え性
- 内臓型冷え性
気温が低くなっても、交感神経の働きが弱いために、手足の血管が収縮されず、血液を体の中心である内臓に集まることがないことで、体の中心である内臓が冷えてしまう - 全身型冷え性
- 局所型冷え性
「私は冷え性じゃない」と思っていても、実は「冷え」のサインが出ているということもあります。
「目のクマ」や「ニキビ」が冷え性のSOS?によれば、例えば、
・目の下にクマができる
・おなかが冷たい
・二の腕が冷たい
・鼻水が出やすい
・肩がこる
・のぼせやすい
・鼻の周りが赤い
・口周りにニキビができる
が冷え性のサインです。
また、内臓型冷え症の症状は以下のとおり。
・おなかが冷える
・厚着をしても体が冷える
・風邪を何度も引いてしまう
・倦怠感
・冷えがひどく、動けなくなる
こうした症状が複数重なる場合には、自分が気づかなくても冷えている恐れがありますので、ぜひ生活習慣を見直してみてください。
【関連記事】
- 「目のくま」と「低体温・冷え性」と「乾燥」には関連がある!?
- 体の不調の原因は低体温? 平熱が下がる原因と影響は?
- 手荒れと冷えには関係がある?
- 手足の荒れ、「冷え」が犯人 マッサージで血行改善
- 胸が大きくならない原因は「バストの冷え」?
- 冷え性・低体温は妊娠に影響する?
- 女性に急増中の「冷え太り(低体温)」
- 長時間のパソコン使用で冷え・肩こり・眼精疲労の症状を併発
- 冷え性・低体温による肌の不調を改善するには?
■ストレス過多、ケータイ・スマホ・パソコンの使い過ぎが「冷え」の原因?
このリラックスしたくてもできない“過緊張”の症状を訴えた女性は、「重度の冷え症である」と感じてい る割合(過緊張 30.2%>非過緊張 14.3%)が高くなりました。スマホの過度な利用が過緊張の症状を引き起こし、“冷 え症”を悪化させる、といった因果関係があるのかもしれません。
若い人ほど冷え性?20代では3人に2人が冷えを感じているによれば、ストレス過多の方やケータイ・スマホ・パソコンの使い過ぎと感じる方に冷えを感じやすいという結果が出たそうです。
どれくらい使いすぎているかと言えば、例えば、「女子高生の4割、スマホ1日6時間超」がもたらす影響とは?によれば、女子高生の4割がスマホを1日6時間以上触っているそうです。
【関連記事】
長時間のパソコン使用で冷え・肩こり・眼精疲労の症状を併発によれば、パソコンの画面を長時間同じ姿勢で見続ければ、目、肩だけではなく、足先などの末梢の血液循環が低下し、眼精疲労や肩こりが起こりやすく、体の冷えにもつながるようです。
ケータイ・スマホも同様に、同じ姿勢を続けることが冷えの原因となっている可能性があります。
また、低体温・冷え性は万病のもと 生活環境・ストレス影響によれば、ストレスで交感神経が緊張し心臓の動きが速くなり、血圧が上がり体温も高くなるのですが、過度になると血管が収縮したまま戻りにくくなり、血の巡りが悪くなり冷えにつながるそうです。
■2015年版最新冷え対策
以上のことをふまえて、2015年版最新冷え対策を考えてみました。
【目次】
この対策に当てはまる人は、スマホにするまではそれほど冷えを感じていなかったという人です。
ポイントはスマホ自体が悪いのではなくて、スマホを使う姿勢が長時間同じであることと常につながっているというストレスです。
同じ姿勢を続けることによって、血行が悪くなる可能性があり、また、常につながっていることがストレスになっている可能性があるので、定期的にでよいので、意識的にスマホから離れてみてはいかがでしょうか.
【関連記事】
- 時にはスマホから離れて読書をしよう!
- 「つながりすぎ」の弊害|バカンス中もスマホでメールチェックをしてしまっている!?
- つながっていても孤独?|つながりすぎることで失ったものとは何か?
- たまには「スマホ」から離れてみよう!|英・国立公園のゲートに「電子機器預かり所」がつくられた理由
- 「子供は夜9時からスマホ禁止ルール−愛知・刈谷市」から考えること
- PCやスマホから離れて4日間自然の中で過ごすだけで想像力がアップする?
- スマホやパソコンが原因の「夕方老眼」の人が増加している!?
- スマホ症候群チェック
また、スマホの長時間使用をすると、血流が悪くなり、目への血流が減ると、酸素や栄養分が届かなくなることで、目の周囲の皮膚にシワや目の下のくまができやすくなる、いわゆる老け顔になりやすいので、美容のためにも、スマホから離れるといいと思います。
【関連記事】
基本は「頭寒足熱」靴下、ひざ掛けなどで下半身を温め、上半身は厚着を避けます。こうすることで効率よく全身を冷えから守ることができます。
単に厚着をしてしまうと、内臓型冷え性タイプの人は、汗をかいてしまい、体内の熱が逃げてしまい身体の内部が冷えてしまいます。
体の表面の熱を逃がしやすいように通気性のよいものを着て、厚手のタイツや靴下をはき、熱を逃がさないようにしたほうがよいようです。
【関連記事】
身体を冷やす食べ物とは、夏の暑い時期に食べる機会が多い食べ物を想像してください。
また、甘い食べ物や暑い地域でとれるフルーツなども身体を冷やします。
ポイントは、今の旬の食べ物を意識すること。
そうすることで、身体を冷やさない食べ物を選ぶことが自然と出来ます。
そして、たんぱく質は熱に変わりやすいので、たんぱく質を積極的に摂取し、熱に変えるときに欠かせないミネラル・ビタミンを摂るようにしてください。
【関連記事】
お湯に浸かると、身体が温まり、血液の循環がよくなり、疲れもとれ、健康にもダイエットにも効果的。
また、ストレスがかかりやすい現代人の生活の中ではリラックスする方法としてもお風呂の時間を大事にしたいものです。
さらには、冷え性・低体温になると、血流が悪くなり、肌に栄養がいきわたらず、老廃物の代謝が低下してしまうため、肌の不調が出てくるので、美容のためにも、お風呂にゆっくりつかるのはよいのではないでしょうか。
【関連記事】
- 小雪さんの美の秘訣はお風呂?冷えている女性は幸せをつかめない?
- 冷え性・低体温による肌の不調を改善するには?
- ヒートショックプロテイン・HSP入浴法で低体温改善|世界一受けたい授業 2月5日
- 熱ショックたんぱく質|ためしてガッテン 5月11日
- 冷え症・ストレッチ入浴法|みんなの家庭の医学 12月7日
- 薬湯で代謝をアップしてダイエット|「mina」11月号
- 寝る前にお風呂に入ると、ヤセ体質になれる?
第2の心臓とも呼ばれるふくらはぎが動き、そのポンプ作用で血流が良くなります。
また筋肉を使うことで体温が上がります。
冷え性でない人は運動(ウォーキング・ラジオ体操・筋力アップ)で冷え性対策をしているによれば、長年冷え性の人は、厚着をしたり、電気毛布や湯たんぽ、暖房器具を利用する人が多いのに対して、冷え症でない人は、からだを動かすことを大事にしているようです。
- ウォーキングやラジオ体操など体を動かすことを意識している
- 筋力を上げてから冷えが気にならなくなった
- 体を温める食べ物を多くとるように心がけている
冷え性を根本的に対策するには運動する機会を増やすほうがいいかもしれませんね。
6.筋肉を増やす
筋肉をつけるためには、運動することだけではなく、筋肉を作る材料となるたんぱく質を摂取することが大事です。
<中略>
低体温の人が増えている理由の一つには、デスクワークが増えたり、運動する機会が減るなどして、筋肉量が減少していることが挙げられます。
たんぱく質を摂取し、運動する機会を増やして、熱のもととなる筋肉を付けたいですね。
【関連記事】
冬場になると、気になるのが、冷えと乾燥による肌荒れ。
冷えと肌荒れに共通するのが、血行不良。
冷えは血行不良が原因の一つであり、血行が悪いと新陳代謝が落ちるため、肌荒れが起きやすくなるそうです。
また、ユースキン製薬が男女約800人に調査したところ、かかと荒れがある人のうち約8割が「冷えの自覚がある」と答えています。
冷えと肌荒れ防止のために、マッサージクリームを使ってマッサージをすると、冷え対策・肌荒れ対策になり一石二鳥ですよね。
特に、ふくらはぎのマッサージを入念にやるとよいそうです。
ふくらはぎは血液を送るポンプの役割を果たしていて、ふくらはぎをマッサージをするとその機能を補うことが出来ます。
【関連記事】
- 手足の荒れ、「冷え」が犯人 マッサージで血行改善
- 時間がない朝に「目の下のクマ」を解消する方法
- 「目のくま」と「低体温・冷え性」と「乾燥」には関連がある!?
- 手荒れと冷えには関係がある?
- 冬は目の下のクマがある女性が急増するらしい
ツボを押して冷えを解消しましょう。
【関連記事】
- 足の冷え解消のツボ:築賓(ちくひん)|たけしの本当は怖い家庭の医学
- 下半身の血流改善のツボ:臀中(でんちゅう)|たけしの家庭の医学 8月11日
- 足の冷え改善のツボ:八風(はちふう)|たけしの家庭の医学 8月11日
- 足の冷えと腰痛解消のツボ:胞肓(ほうこう)|たけしの本当は怖い家庭の医学
- 下腹の冷え解消・更年期障害・月経不順のツボ:三陰交(さんいんこう)|たけしの本当は怖い家庭の医学
【低体温・冷え性関連記事】
- 低体温から抜け出す5つの方法+1
- 日本人の体温が下がった理由とは
- 低体温・冷え性は万病のもと 生活環境・ストレス影響
- 低体温体質 筋肉量増、食生活、睡眠で改善
- なぜ、ミネラル・ビタミンが不足すると、低体温になってしまうのか?
- 冷えのぼせの症状・原因・改善・対処法・やってはいけないこと
⇒ 低体温|低体温の改善・原因・症状 についてはこちら。
⇒ 体温を上げる方法 についてはこちら。
⇒ 冷え性改善方法(食べ物・食事・運動・サプリ・ツボ)についてはこちら。