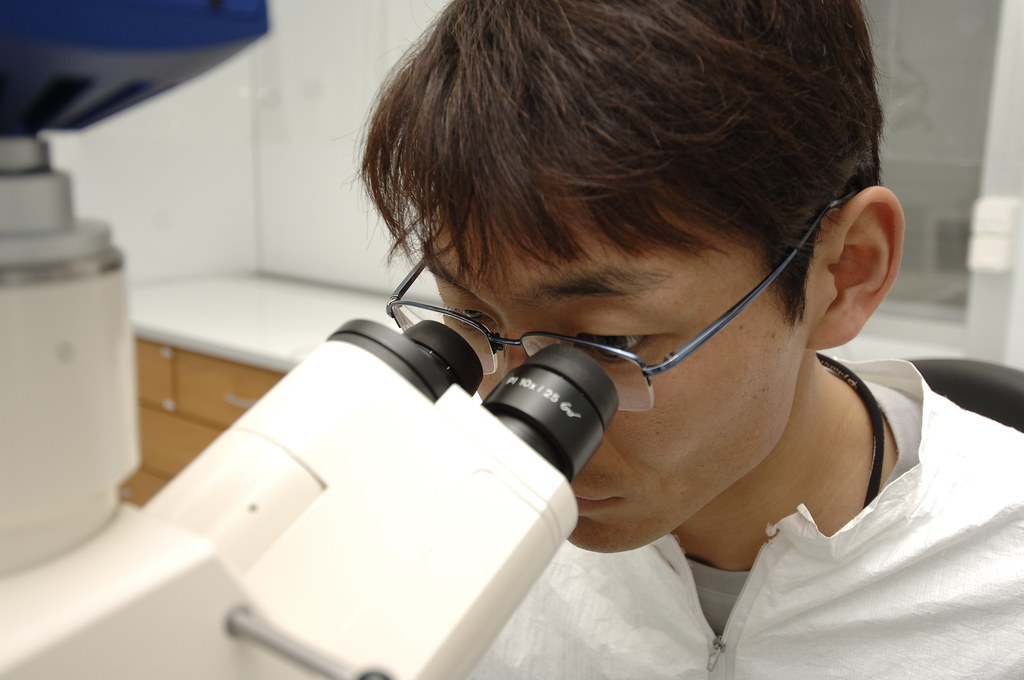> 健康・美容チェック > 糖尿病 > 血糖値 > 人工甘味料で糖尿病リスク増!?|人工甘味料は腸内細菌のバランスを崩して、血糖値が下がりにくい状態にする作用がある!?
■人工甘味料で糖尿病リスク増!?|人工甘味料は腸内細菌のバランスを崩して、血糖値が下がりにくい状態にする作用がある!?
by Steve Snodgrass(画像:Creative Commons)
(2014/9/18、神戸新聞NEXT)
菓子や清涼飲料に広く使われているサッカリンなどの人工甘味料には、代謝に関わる腸内細菌のバランスを崩して血糖値が下がりにくい状態にする作用があるとする研究結果を、イスラエルの研究チームが英科学誌ネイチャー電子版に17日発表した。
イスラエルの研究チームによれば、サッカリンやスクラロース、アスパルテームなどの人工甘味料は腸内細菌のバランスを崩して、血糖値が下がりにくい状態にする作用があるという研究結果が発表されました。
ダイエット清涼飲料の飲みすぎの人は、胴囲の増加が飲まない人の6倍にで紹介した記事によれば、今回の記事とは考え方が違うものの、アステルパームという人工甘味料が健康に対して何らかの影響を与えていると考えられていました。
- 糖尿病の初期段階に起こりやすい膵臓(すいぞう)内の損傷に少なからず影響を与えている
- 人工甘味料は食欲を促進させ、満足感を感知する脳の細胞に損傷を与える。
砂糖のような自然の糖分の不足により、さらに甘いものへの欲求が増す。
両方の記事に共通するのは、人工甘味料には、糖尿病へのリスクを高める要因があると考えられるというものであり、今回の記事は、人工甘味料が腸内細菌のバランスを崩すことによって、代謝異常を引き起こす可能性があるということですね。
肥満やメタボの第3の要因に腸内細菌叢が関係している?和食を食べて予防しよう!という記事によれば、肥満やメタボリックシンドロームを引き起こす第三の要因として腸内細菌叢が関係しているのではないかと考えられているそうです。
やせない原因は腸にあった!?やせ型腸内細菌と肥満型腸内細菌|腸サビ|世界一受けたい授業 10月29日によれば、腸内細菌の中に肥満型腸内細菌とやせ型腸内細菌がいることが分かってきたそうです。
肥満型腸内細菌とヤセ型腸内細菌は両方とも誰もが持っており、同じものを食べていても、肥満型腸内細菌が多い場合は、栄養の吸収をどんどん促進させて肥満になってしまうのだそうです。
ヤセ型腸内細菌を多く持っている人は太りにくい体質ということになります。
米ワシントン大学の研究によると、肥満型腸内細菌を与えたマウスとやせ型腸内細菌を与えたマウスを同じエサで育てた実験で、肥満型腸内細菌を与えたマウスは体脂肪が47%も増えたのに対し、やせ型腸内細菌を与えたマウスは27%しか増えなかったという結果になったそうです。
アメリカ人には肥満型腸内細菌を持つ人が多いと言われており、日本人にはヤセ型腸内細菌を持つ人が多いと言われています。
それは和食や食物繊維の多い野菜をよく食べているため、肥満型腸内細菌が抑制されているのではないかと考えられるそうです。
→ 糖尿病の症状・初期症状 について詳しくはこちら
→ 糖尿病危険度チェック について詳しくはこちら
【関連記事】
続きを読む 人工甘味料で糖尿病リスク増!?|人工甘味料は腸内細菌のバランスを崩して、血糖値が下がりにくい状態にする作用がある!?