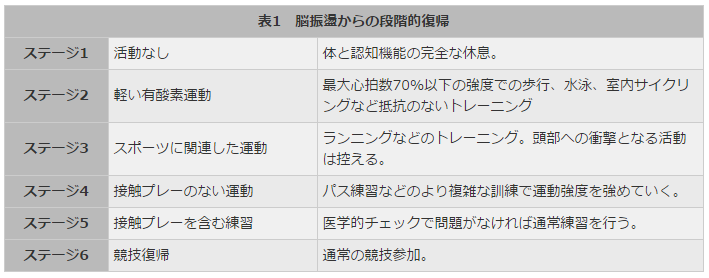> 健康・美容チェック > 冷え性 > “冷え”はストレス過多のサイン!?自律神経の乱れから男性でも冷え症で悩む人が増えている!
■“冷え”はストレス過多のサイン!?自律神経の乱れから男性でも冷え症で悩む人が増えている!

by Jon Nicholls(画像:Creative Commons)
増える“無自覚冷え症男子” 簡単「冷え症対策」
(2009/1/26、東京ウォーカー)
現代人がもっとも感じている冬の悩み、それは「冷え症」。
最近は男性でも「冷え症」で悩む人が増えているのだとか。
冷え性と言えば、女性の悩みと考える人も多いと思いますが、最近では、男性でも冷え症で悩む人が増えてきています。
その男性の冷え性の原因の多くはストレスのようなのです。
「冷え症の原因の多くは“ストレス”なんです。
本来、私たちの体は日中は“緊張モード”になり夜は“リラックスモード”になる自律神経が働いています。
残業続きだったり、リラックスできない状況が続くと、自律神経がバランスを崩し、血管が収縮、血流が悪くなってしまうんです。
“冷え”は、ストレス過多のサインでもあるんですよ」
(大阪大学大学院医学系研究科・石蔵先生)
大阪大学大学院医学系研究科・石蔵先生によれば、冷え性の原因の一つがストレスにあるようです。
冷えを感じている人は、ストレスがたまっているかもしれません。
自分に合ったストレス解消方法を見つけ、体を温める食事を食べたり、サプリメントなどで栄養を整えるなどして、冷え症を解消しましょう。
■冷え性解消方法
 冷たい食べ物や甘い食べ物をあまり食べないようにする
冷たい食べ物や甘い食べ物をあまり食べないようにする
糖分には体を冷やす作用があり、冷え性の原因となるので、できるだけ食べないようにする。
温かい飲み物を飲んで冷え性改善!
 旬の野菜や果物を摂取して冷え性改善!
旬の野菜や果物を摂取して冷え性改善!
 食べない系ダイエットは避ける
食べない系ダイエットは避ける
食事をすると、体内に吸収・分解される際に、熱が発生します。食事誘発性熱産生といいます。
 たんぱく質は熱に変わりやすいので、たんぱく質の摂取を忘れない
たんぱく質は熱に変わりやすいので、たんぱく質の摂取を忘れない
基礎代謝をアップして痩せやすい身体を作る4つの方法によれば、筋肉をつけるためには、運動することだけではなく、筋肉を作る材料となるたんぱく質を摂取することが大事です。
冷え性の人が増えている理由の一つには、デスクワークが増えたり、運動する機会が減るなどして、筋肉量が減少していることが挙げられます。
たんぱく質を摂取し、運動する機会を増やして、熱のもととなる筋肉を付けたいですね。
 ココア
ココア
ココアには体の冷え対策に有用な「体温保持効果」があることがわかったそうです。
ココアに含まれる『ポリフェノール』や『テオブロミン』は血管拡張作用があることが報告されており、特に手足の先の血液循環を改善することで、ゆっくりと長く冷えを抑制できると考えられます。
【参考記事】
・ココアには体の冷え対策に有用な「体温保持効果」がある!?
乾燥しょうがは、ジンゲロールとショウガオールの2つの働きによって、全身を温めてくれるそうです。
【参考記事】
・乾燥しょうがで体を温める!
体温を上げる(冷え性を改善する)方法には、食生活の改善以外にもさまざまな方法がありますので、ぜひこちらもご覧ください。
 運動で冷え性改善!
運動で冷え性改善!
運動不足になると、血液を送る筋力が低下し、冷え性の原因となるので、積極的に運動して筋肉を鍛えましょう。
第2の心臓とも呼ばれるふくらはぎが動き、そのポンプ作用で血流が良くなります。
また筋肉を使うことで体温が上がります。
冷え性でない人は運動(ウォーキング・ラジオ体操・筋力アップ)で冷え性対策をしているによれば、長年冷え性の人は、厚着をしたり、電気毛布や湯たんぽ、暖房器具を利用する人が多いのに対して、冷え症でない人は、からだを動かすことを大事にしているようです。
- ウォーキングやラジオ体操など体を動かすことを意識している
- 筋力を上げてから冷えが気にならなくなった
- 体を温める食べ物を多くとるように心がけている
また、運動することで交感神経の働きが上手になってくるそうです。
冷え性を根本的に対策するには運動する機会を増やすほうがいいかもしれませんね。
ウォーキングやスクワット・スロトレなどがオススメ。
 お風呂にゆっくり浸かる
お風呂にゆっくり浸かる
お湯に浸かると、身体が温まり、血液の循環がよくなり、疲れもとれ、健康にもダイエットにも効果的。
また、ストレスがかかりやすい現代人の生活の中ではリラックスする方法としてもお風呂の時間を大事にしたいものです。
お風呂にゆっくりつかることで体が温まるだけではなく、リラックスすることで自律神経(交感神経と副交感神経)のバランスが整うことが期待されます。
さらには、冷え性・低体温になると、血流が悪くなり、肌に栄養がいきわたらず、老廃物の代謝が低下してしまうため、肌の不調が出てくるので、美容のためにも、お風呂にゆっくりつかるのはよいのではないでしょうか。
●オススメ入浴法:ストレッチ入浴法
40度~42度のちょっと熱いと感じる程度のお湯を用意し、入浴時間は10分間。
最初の5分は寝るようにして首までしっかり浸かり、残りの5分は起き上がり座った姿勢で胸元を出してリラックス。
※入浴前は足元からかけ湯を行うこと。
1.お湯は40~42℃で2分間首まで浸かる。
2.2分経ったら上半身のストレッチ
両肘を後ろに突っ張り胸をはる
左右の肩甲骨をくっつけるように背筋を伸ばし5つ数える(2回)
(思いっきり力を入れて背筋を伸ばすのがポイント)
3.下半身のストレッチ
入浴から5分後起き上がり胸元まで体を出す
坐禅のように脚を組む
足の指先を手で握り引き寄せるように足指を伸ばす
5つ数えたら手を離し足を伸ばす。(2~3回)
(足を伸ばすことで血液がしっかり流れる)
4.10分たつまでゆっくり浸かる
【参考記事】
●冷え症・ストレッチ入浴法|みんなの家庭の医学 12月7日
 お酒の飲みすぎに気をつける
お酒の飲みすぎに気をつける
 タバコを控える
タバコを控える
タバコは急激に血管を収縮させてしまい、血液の流れが悪くするともに基礎代謝も低下させてしまうためです。
 寒さにあたる
寒さにあたる
寒さにあたることで、交感神経の活動が高まり、血管収縮のトレーニングになる。
・足の冷え解消のツボ:築賓(ちくひん)
・足の冷えと腰痛解消のツボ:胞肓(ほうこう)
・下腹の冷え解消・更年期障害・月経不順のツボ:三陰交(さんいんこう)
・足の冷え改善のツボ:八風(はちふう)
・下半身の血流改善のツボ:臀中(でんちゅう)
 マッサージ
マッサージ
冷えと肌荒れに共通するのが、血行不良。
冷えは血行不良が原因の一つであり、血行が悪いと新陳代謝が落ちるため、肌荒れが起きやすくなるそうです。
また、ユースキン製薬が男女約800人に調査したところ、かかと荒れがある人のうち約8割が「冷えの自覚がある」と答えています。
冷えと肌荒れ防止のために、マッサージクリームを使ってマッサージをすると、冷え対策・肌荒れ対策になり一石二鳥ですよね。
特に、ふくらはぎのマッサージを入念にやるとよいそうです。
ふくらはぎは血液を送るポンプの役割を果たしていて、ふくらはぎをマッサージをするとその機能を補うことが出来ます。
【参考記事】
 ヘスペリジン
ヘスペリジン
グリコ健康科学研究所によれば、冷えを感じる女性が「ヘスペリジン」に糖を結合させた「糖転移ヘスペリジン」を摂取すると冷水で冷やした手の皮膚表面温度の回復を早めることが分かったそうです。
また、あらかじめ糖転移ヘスペリジンを摂取しておくと、冷房が効き過ぎていても、手足の冷えが抑えられるそうです。
【関連記事】
 酒粕
酒粕
月桂冠株式会社は、冷え性の症状がある男女8名に、アルコールを除いた酒粕の粉末を10g食べて、40分後に手を冷却することによって負荷をかける実験を行ったところ、酒粕を食べた人は手の表面温度に上昇傾向がみられたそうです。
【関連記事】
【ストレス 関連記事】
続きを読む “冷え”はストレス過多のサイン!?自律神経の乱れから男性でも冷え症で悩む人が増えている! →