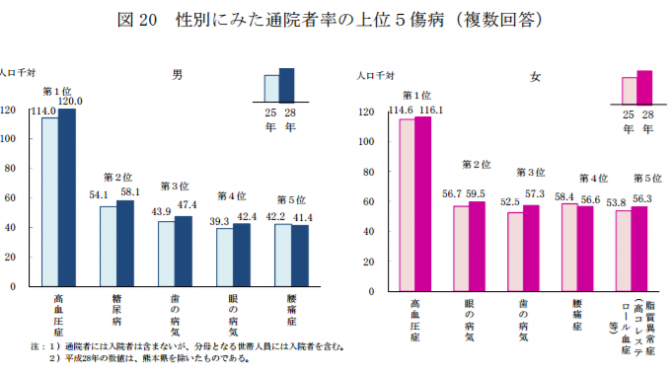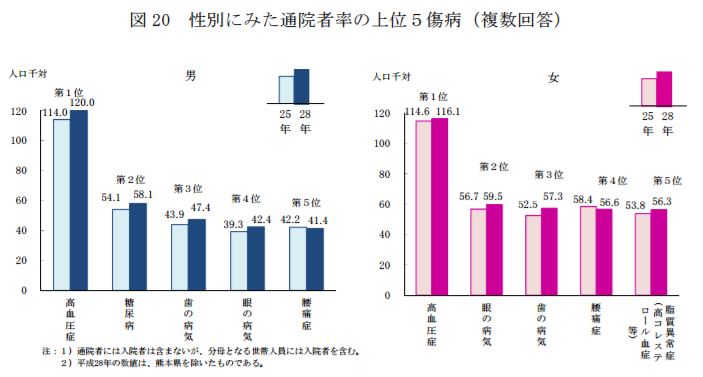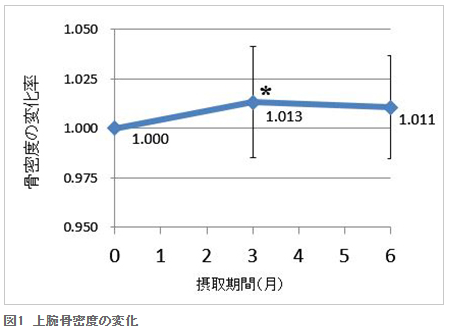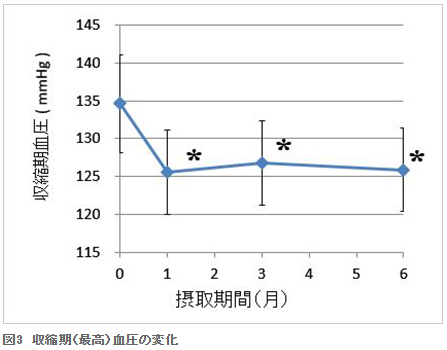> 健康・美容チェック > 中性脂肪 > 【ゲンキの時間】サバに含まれるオメガ3(DHA・EPA)が中性脂肪を下げる|サバダイエットで中性脂肪値・コレステロール値改善
【目次】
■サバダイエットで中性脂肪値・コレステロール値改善
2018年4月15日放送の「ゲンキの時間」では、サバにはオメガ3を含む不飽和脂肪酸(EPA・DHA)が多く含まれており、中性脂肪を下げる効果が期待できるため、中性脂肪を下げたいという方にサバをオススメしていました。
(2016/3/15、大阪日日新聞)
サバダイエットには右田社長と社員5人が参加。実施期間は2月5日から3月5日までの1カ月間。ルールは、期間中に摂取する動物性タンパク質はサバのみ▽原則として1日2食はサバ料理を食べる―の二つ。ダイエットの天敵ともいえる炭水化物やアルコールについては特に制限しなかった。
<中略>
サバダイエット終了後に右田社長が血液検査した結果、中性脂肪90(実施前101)▽善玉コレステロール57(同56)▽悪玉コレステロール113(同117)―といずれも改善し、体重も1・3キロ減。ほかの社員の数値も軒並み良くなり、体重が5・4キロ減ったという社員もいた。
サバにはDHAやEPAが多く含まれており、DHA・EPAは中性脂肪を下げる効果や血管を柔らかくする効果があることから、動脈硬化や心筋梗塞を予防する働きがあるといわれています。
→ DHA・EPAを含む食品 について詳しくはこちら
→ 動脈硬化とは|動脈硬化の症状・原因・改善方法 について詳しくはこちら
少人数による実験なのではっきりとはわかりませんが、サバ料理を食べたことによって、体重が減少し、中性脂肪・善玉コレステロール・悪玉コレステロールの数値が改善したという結果が出たそうです。
消費者庁の食品の機能性評価モデル事業」の結果報告(平成24年4月)によれば、EPA/DHAの「心血管疾患リスク低減」「血中中性脂肪低下作用」に関してはいずれの機能も総合評価はAとなっています。
→ 悪玉コレステロールを減らす方法|LDLコレステロールを下げる食品・食事 について詳しくはこちら
■EPAなどオメガ3を含む食品と健康効果の関係
また、魚うどん(EPA)で血管若返り|たけしのみんなの家庭の医学によれば、体重が97キロで、血糖値、LDLコレステロール(悪玉コレステロール)、中性脂肪値が基準値を超えていた人が、魚うどん(青魚のトビウオを原料にした魚のすり身で作られたうどん)を食べたことで、体重が-14キロになり、すべての数値が症状に戻ったそうです。
ニッチェ近藤さん、小さじスプーン1杯のオメガ3(えごま油)の摂取でダイエット・中性脂肪低下効果|オメガ3で中性脂肪値が下がるメカニズム|美と若さの新常識(#NHK)によれば、『美と若さの新常識~カラダのヒミツ~ 「スプーン1杯の魔法 食べるアブラの極意」』(NHK BSプレミアム)では、お笑いコンビ・ニッチェの近藤くみこさんが1ヵ月間毎日小さじスプーン1杯の オメガ3(エゴマ油)を摂取する実験を行なったところ、中性脂肪 189mg/dl → 165mg/dlという結果が出ています。
やせるホルモンGLP-1を増やす方法(食物繊維・EPA)|たけしのみんなの家庭の医学やEPAの摂取によって、褐色脂肪細胞を増産させ、ヤセやすくなる!?によれば、やせるホルモンGLP-1を増やすには食物繊維とEPAを含む食品をとることがよいそうです。
サバなどの青魚を食べるようにしたいですね。
サバ缶を使うのもおすすめです!
→ 中性脂肪値を下げるためにEPA・DHAを含む食品(青魚など)やサプリメントを摂取しよう! について詳しくはこちら
→ オメガ3脂肪酸とは|オメガ3の効果・効能・ダイエット|オメガ3の多い食べ物・食品 について詳しくはこちら
→ 中性脂肪を下げる食事・運動・サプリメント について詳しくはこちら
続きを読む 【ゲンキの時間】サバに含まれるオメガ3(DHA・EPA)が中性脂肪を下げる|サバダイエットで中性脂肪値・コレステロール値改善