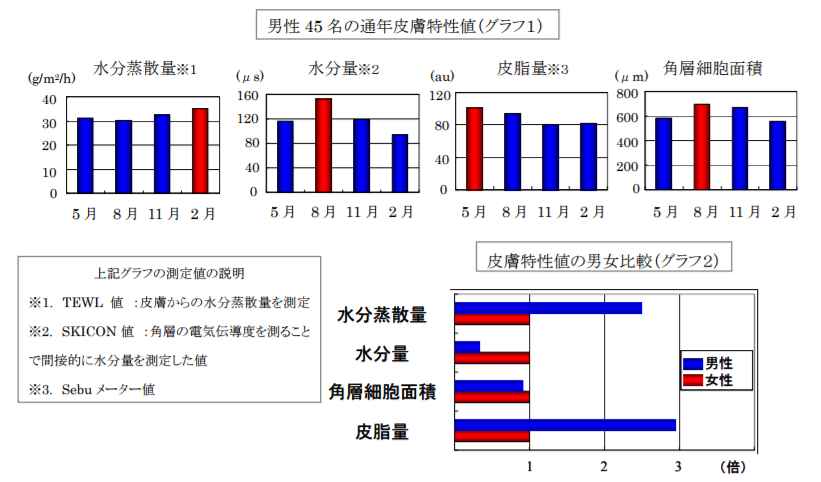> 健康・美容チェック > 骨粗しょう症 > 女性の股関節骨折は死亡リスクを高める|50歳以上の女性の約半数が骨粗しょう症による骨折を経験|米研究
■女性の股関節骨折は死亡リスクを高める|米研究

by Sascha Kohlmann(画像:Creative Commons)
女性の股関節骨折は死亡リスクを高める、米研究
(2011/9/28、AFPBB)
65~69歳の女性が股関節を骨折した場合、1年以内に死亡するリスクは健康な同世代の女性に比べて5倍高くなるとする論文が26日、米国医師会(American Medical Association)の内科専門誌「アーカイブス・オブ・インターナル・メディシン(Archives of Internal Medicine)」に発表された。
同様のリスクは、70~79歳の女性では2倍、80歳以上の女性では3倍だった。
65歳から79歳の女性および80歳以上の女性が股関節を骨折した場合、死亡リスクが高まるという論文結果が発表されました。
考えられる仮説としては3つ。(※仮説はこのブログによるもので、研究内容とは異なります。)
1.高齢の女性が股関節を骨折すると、リハビリが大変で、散歩するなど運動する機会が減ってしまうために、健康を悪化させてしまうから
2.骨折のそもそもの原因が低栄養にあるから
お年寄りは低栄養に注意|低栄養になると、免疫の低下、筋肉の減少、骨が弱くなることで、感染症や骨折の恐れが高くなるによれば、低栄養になると、免疫が低下したり、筋肉が減少したり、骨が弱くなったりすることで、感染症に掛かりやすくなったり、骨折するおそれが高くなるようです。
【関連記事】
3.オステオネットワークの破たん
オステオカルシン(骨ホルモン)を増やして血糖値を下げる!|オステオカインが全身の臓器を制御している|#ガッテンによれば、近年の研究によって、骨は単なる運動器の一部ではなく、外界の環境変動やストレスを感受し、骨が分泌する生理活性物質「オステオカイン」と骨免疫の作用により、全身臓器を能動的に制御していることが示唆されています。
この骨による全身の制御メカニズムを「オステオネットワーク」といいます。
骨と免疫力に関係があると仮定すれば、股関節の骨折により、骨への刺激がなくなることで免疫力が弱まるということは考えられないでしょうか?
■50歳以上の女性の約半数が骨粗しょう症による骨折を経験
米国の骨粗しょう症財団によると、50歳以上の女性の約半数が骨粗しょう症による骨折を経験している。
国際骨粗しょう症財団(International Osteoporosis Foundation)は、股関節の骨折は世界で年間160万例にのぼっていると発表している。
米国の骨粗しょう症財団によると、50歳以上の女性の約半数が骨粗しょう症による骨折を経験しているそうです。
ただ、骨粗しょう症は若いうちは関係ないと思い込んでいる人もいると思いますが、骨粗しょう症のリスクは若い人にも十分あります。
それはカロリーを気にするあまり冒頭のような食事の摂り方をして、栄養不足を招いていることが原因だ。
特に調査によると肥満度の判定方法の一つにBMI値が低い人ほど3食きちんと食べなかったりするため、骨粗しょう症になりやすいという。
血中のカルシウム濃度は一定で、不足し始めると骨のカルシウムから補填をするようになる。
すると、血中のカルシウムが不足すればするほど骨のカルシウムも減っていき、骨がもろくなり、骨粗しょう症につながっていくのだ。
【関連記事】
大江医師によると、ロコモの要因となる病気は3種類。
骨の強度が低下する骨粗鬆(こつそしょう)症
▽関節の軟骨がすり減り、痛みが出たりする変形性関節症
▽神経の通り道である脊柱管(せきちゅうかん)が狭くなり、神経の通りが悪くなる脊柱管狭窄(きょうさく)症
-で、この3つの病気などが複合して起きたり、積み重なって運動器の機能が低下し、移動能力が落ちてしまうという。
ロコモティブシンドロームの要因となる病気は、骨粗鬆症・変形性関節症・脊柱管狭窄症の3つの病気。
こうした病気になることで、運動器の障害が生まれ、要介護状態になる危険性が高くなります。
記事には、ロコモティブシンドロームかどうかを点検する「ロコチェック」が紹介されていました。
点検項目は、
(1)片脚立ちで靴下がはけない
(2)家の中でつまずいたり、滑ったりする
(3)階段を上るのに手すりが必要
(4)横断歩道を青信号の間に渡りきれない
(5)15分くらい続けて歩けない
-の5種類。
上記の5種類のうち1つでも当てはまれば、「ロコモ」の可能性があるそうです。
また、ロコモにならないための運動「ロコトレ」も紹介されています。
骨の強度が弱まることを防ぐとともに、バランス能力を鍛えて転倒しにくくする開眼片脚立ちと、お尻や太ももの筋肉の訓練であるスクワットの2種類だ。
方法が詳しく紹介されていました。
開眼片足立ちの方法
1日3回、左右1分間ずつ、床につかない程度に片足を上げる。
スクワットの方法
1日に3度(1度に5・6回ずつ)椅子に腰をかけるようにお尻をゆっくり下ろす。
骨粗鬆症の予防にはどのようなことをすればよいのでしょうか。
加齢による骨量の低下は避けられないが、カルシウムやビタミンDを多く含む食品の摂取、毎日の適度な運動で予防を心がけることが大切だ。
森部長は「閉経後の女性に限らず、骨粗鬆症が原因で骨折した家族がいる人や、喫煙・飲酒の習慣がある人はリスクが高い。50歳を過ぎたら早めに検査を受けてほしい」と呼びかける。
骨粗鬆症の予防には、
- カルシウムやビタミンDを多く含む食品の摂取
- 毎日の適度な運動
- 早期発見のため、検査を受ける
骨粗鬆症を病気だと認識している人も少ないでしょうし、また、骨粗鬆症の検査が行われていること自体知らないという方も多いと思います。
骨粗鬆症を予防するためにも、カルシウムやビタミンDを多く含む食品の摂取、毎日の適度な運動を行い、早期発見のため、検査を受けるようにしてくださいね。
【骨粗鬆症とは】
骨粗鬆症は、骨量が減少して若年成人(20~44歳)の平均値の7割未満に落ち込んだ状態。骨がスカスカになり、骨折しやすくなる病気だ。
骨量は男女とも20~30代をピークに加齢とともに減少する。
特に閉経後の女性の場合、女性ホルモンの分泌が低下して骨量が急激に減るため、発症率は60代で3人に1人、70代では2人に1人といわれている。
■まとめ
65歳から79歳の女性および80歳以上の女性が股関節を骨折した場合、死亡リスクが高まるという論文から3つの仮説を考えました。
1.高齢の女性が股関節を骨折すると、リハビリが大変で、散歩するなど運動する機会が減ってしまうために、健康を悪化させてしまうから
2.骨折のそもそもの原因が低栄養にあるから
3.オステオネットワークの破たん
これらの3つの仮説を正しいと考えるとすれば、予防するのに欠かせないのは、日ごろから運動をして骨・筋肉に刺激を与えること、低栄養や骨粗しょう症を予防する食事に切り替えていく(中高年(メタボ対策)から高齢者(フレイル対応)への食習慣の移行ができていないために低栄養になってしまっていると考えられるため)ことです。
【参考リンク】
続きを読む 女性の股関節骨折は死亡リスクを高める|50歳以上の女性の約半数が骨粗しょう症による骨折を経験|米研究 →