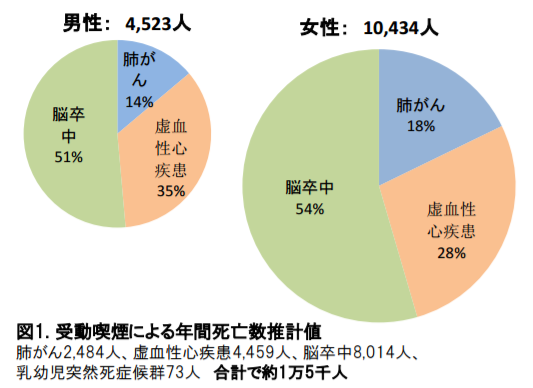by Mislav Marohnić(画像:Creative Commons)
> 健康・美容チェック > 脳卒中 > 脳梗塞 > なぜ脳梗塞は月曜日に起こりやすいのか?
(2015/4/20、medley)
国立病院機構南京都病院などから集まった研究班は、1999年から2009年までに脳卒中を発症し、京都脳卒中登録(KSR)に登録された13,788人の情報を統計分析し、曜日によって脳卒中の発症率が違うかどうかを調べました。
その結果、脳卒中の発症が最も少ないのは日曜日で、最も多いのは月曜日だとわかりました。
脳卒中を更に詳しく分けて脳梗塞、脳出血、くも膜下出血に区別して調べると、脳梗塞の発症が月曜日に多く、日曜日に比べてオッズ比1.189倍にのぼることがわかりました。
京都府の研究班の調査によれば、脳梗塞は月曜日に起こりやすいということがわかったそうです。
→ 脳梗塞の症状・原因・予防 について詳しくはこちら
曜日と健康についてどのような関係があるのでしょうか?
以前Twitterのツイート数についての記事を紹介しましたが、時間帯によってつぶやかれている内容は異なっています。
「#疲れた」のピークは午後5時!?|つぶやきからわかる本当に疲れる時間帯とは??によれば、「疲れた」とつぶきたくなっているのは、17時台であり、学校終わり、仕事終わりで、疲れがたまっている時間であることが予想されます。
時間帯別総ツイート数ランキングからわかる感情の推移とは?でも紹介しましたが、17時台には、「疲れた」だけでなく、「頭痛い」「足痛い」という言葉がつぶやかれていて、歩きまわったり、頭を使ったりして、疲れている印象を受けます。
時間帯と同様に曜日によっても何らかの傾向があるのではないでしょうか。
「疲れた」3秒に1回つぶやかれている!水曜日に「疲れた」つぶやきが増加によれば、水曜日に「疲れた」ツイートが増えているそうで、週の真ん中で疲れを感じている人が多いと思われます。
月曜日に脳梗塞を発症することも何らかの要因が関係していると思われます。
10年以上健康に関するアクセスをアクセスデータを見ていますが、人は、楽しい時(遊びに出かける週末)は健康について考えないものです。
【関連記事】
日曜日には健康についての検索数が減り、月曜日になると健康に関する検索が増えているということからも、体に関する何らかの不調が出てきたり、休みの翌日に健康を意識していると考えられます。
日本では通称サザエさん症候群(世界的にはブルーマンデーといわれるそうです)と呼ばれる月曜日の学校や勤務へと行きたくない気持ちを表現する言葉があります。
サザエさん症候群|Wikipediaより
サザエさん症候群(サザエさんしょうこうぐん)とは、日曜日の夕方から深夜、特に18:30から19:00にかけてフジテレビ系列で放送される『サザエさん』を見た後、「翌日からまた通学・仕事をしなければならない」という現実に直面して憂鬱になり、体調不良や倦怠感を訴える症状の俗称である。
もしかすると、ここに今回の問いを解決するヒントがあるのではないでしょうか?
【関連記事】