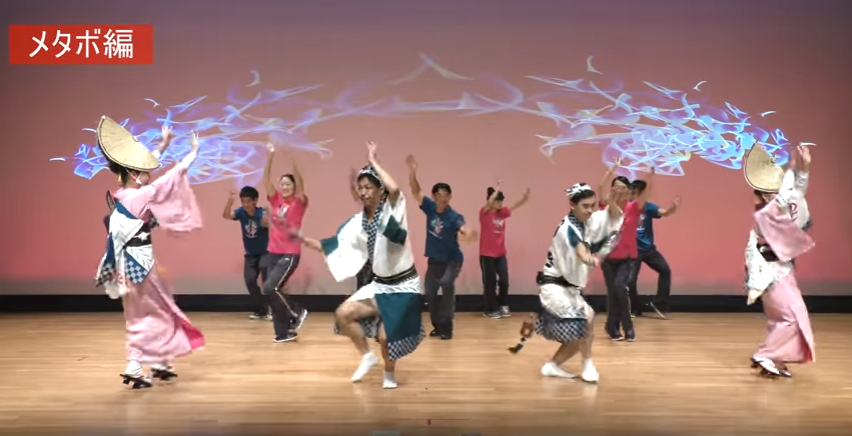アメリカの「リーダーズ・ダイジェスト・マガジン」が世界中から集めた失敗しない8つのダイエットのポイントを発表したそうです。
by Mike Mozart(画像:Creative Commons)
アメリカが世界中から集めた8つのダイエット方法
(2009/10/24、アメーバニュース)
1. 満腹になる前に食事をやめる。
2. オリーブオイルなど良質の油を使った料理を食べる。
3. 食事中にテレビを見たり、仕事をするなど他のことをしない。(知らず知らずのうちに食べ過ぎてしまう)
4. 体を動かす。
5. 3食きちんと食べる。
6. 一人で食事をしない。(周りに人がいると、暴食することがなくなり、ゆっくり食べることで少ない量で満腹感を得ることができる)
7. 空腹時以外食事をしない。(現代人にはストレスにより間食してしまう人が多い。)
8. 食事にグラス一杯のワインを付ける。(ポリフェノールが体内の悪玉コレステロールを酸化してくれる)
一つ一つを見ていきます。
1. 満腹になる前に食事をやめる。
腹八分目になるような食事の仕方をする必要があります。
よく噛んでゆっくり咀嚼(そしゃく)することで、脳にある満腹中枢を刺激し、食べ過ぎを防ぎ、肥満を防いでくれます。
※糖尿病の方や糖尿病予備軍にすすめている糖尿病の食事療法でも、そのように指導されているようです。
【関連記事】
- 噛む(咀嚼)ことによる3つの健康効果(唾液を多く出す・食べ過ぎを防ぐ・脳への刺激を増やす)
- ヒスチジンを含む食品をよく噛んで脳内ヒスタミンを増やし食欲を抑える|ためしてガッテン(NHK)
- よく噛んでゆっくり食べることがダイエットの秘訣
2. オリーブオイルなど良質の油を使った料理を食べる。
良質な油を摂取することはこのブログでも何度も紹介しています。
おすすめはオメガ3脂肪酸の油です。
【関連記事】
3. 食事中にテレビを見たり、仕事をするなど他のことをしない。
だらだら食べてしまうと食べ過ぎてしまうようです。
4. 体を動かす。
ダイエットには運動は欠かせません。
【おすすめの運動・エクササイズ】
- サーキットスロートレーニング(サーキットスロトレ)
- サーキットトレーニングのやり方
- スローステップ運動・スロージョギングの疑問|ためしてガッテン(NHK)
- スロージョギングの効果・やり方とは|ためしてガッテン(NHK)
- スロトレ(スロートレーニング)|生活ほっとモーニング(NHK)
- モナリザ症候群―交感神経の働きが低下することで、代謝が起こりにくく、痩せにくいカラダになってしまう
5. 3食きちんと食べる。
食事誘発性熱産生による消費カロリーが意外と多いんです。
【関連記事】
6. 一人で食事をしない。
周りに人がいると、暴食することがなくなり、ゆっくり食べることで少ない量で満腹感を得ることができるそうですが、ただし、周りの家族・友人が食べ過ぎる傾向にあると、それに応じて食べる恐れがあるため、注意が必要ですね。
【関連記事】
7. 空腹時以外食事をしない。(現代人にはストレスにより間食してしまう人が多い。)
本当は食べたいと思っていないのに、ストレスのために食べてしまうことがあります。
食べる以外でストレスを解消する方法を身につけたいですね。
8. 食事にグラス一杯のワインを付ける。
ワインのポリフェノールに限らず、抗酸化作用のある食品を摂ることが重要だということでしょう。
ダイエットの情報はこちら
↓ ↓ ↓ ↓ ↓