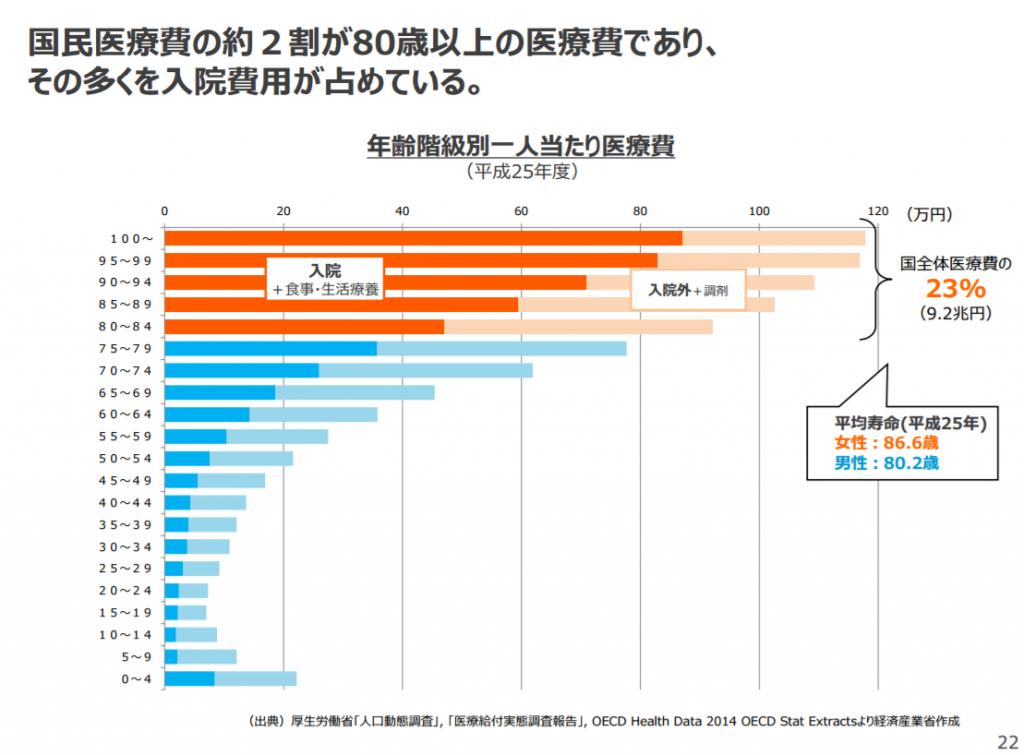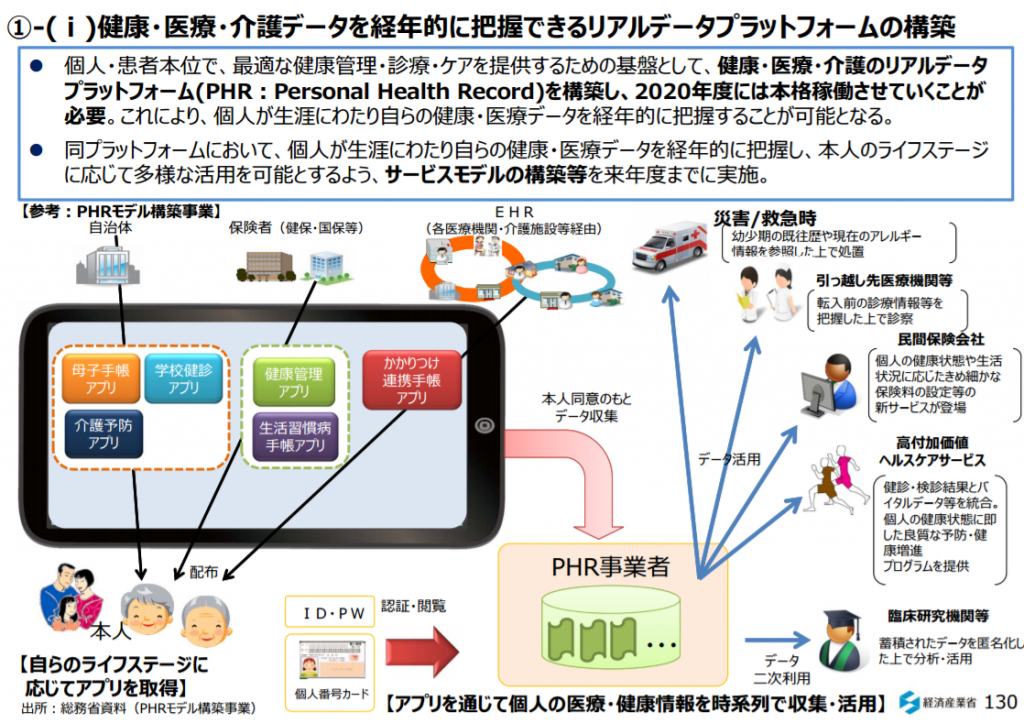■キム・カーダシアン(Kim Kardashian)の効果的なダイエット方法(食事・運動)とは?
by Kalumba2009(画像:Creative Commons)
(2012/9/28、OK!JAPAN)
今回の記事では、キム・カーダシアン(Kim Kardashian)本人のコメントとセレブリティー・トレーナーのガーナー・ピーターソン(Gunnar Peterson)によるパーソナル・プログラムの解説が紹介されています。
参考になるポイントをまとめてみたいと思います。
■食事
塩分や脂肪分が大量に含まれているファースト・フードを口にせず
今までは忙しさにかまけてファースト・フードで簡単に食事を済ませる事が多かったけれど、でもメニューの選択次第では全てのファースト・フードが必ずしも不健康と言う訳ではないと思うし、それは言い訳にならないと言う事に気が付いたの。そして、出来るだけグルテンや糖分が含まれていない健康的な食事を摂取するように心掛けたと言う訳。それに卵の白味で作ったオムレツのようなシンプルなメニューが好きだと言う事もダイエットのプラスになったようだわ。
でも極度なダイエットは、精神的にも良くないし、全ては“中庸”の精神が必要だと思うの。だから私も時々大好物のアイスクリームを食べたりして、バランスの取れた食生活を保つようにしているの。
食事の考え方も大変参考になりますよね。
ストイックになりすぎるとどうしても続かなくなりがちです。
キム・カーダシアンさんの考え方は「中庸」の精神。
たまには息抜きにアイスクリームを食べてもいいというように考えて、次の日に調節するというように考えれば、長続きできるのではないでしょうか。
あと、もう一点気になったのは、「グルテンや糖分が含まれていない食事」を心がけているという点です。
グルテンが含まれていない食事といえば、グルテンフリーダイエットです。
グルテンフリーダイエットとは、小麦などグルテンを含むものを一切食べない方法で、グウィネス・パルトローやミランダ・カー、マイリー・サイラスといった有名セレブが取り入れているそうです。
【グルテンフリー 関連記事】
- マイリー・サイラスのダイエットの3つのルールとは?
- ミランダ・カーの美の秘訣
- ディーン・フジオカさんはグルテンアレルギーのため、フォーなどのグルテンフリーの食事を食べている
- <柿の種>グルテンフリー(GLUTEN FREE)で健康志向のアメリカの消費者から人気に
また、糖分が含まれていない食事を心がけているということですので、糖化について気にしているのかもしれません。
【糖化 関連記事】
■運動
スクワット・ランジ・ウェイトを組み合わせたトレーニングを毎日定期的に実行しているわ。
例えば、スクワット、ジャンプ、ランジス、ラテラル・ワーク、ラテラル・ジュンプなど、身体を大きく動かす多様な運動をミックスして、キムの体型に合った特別なトレーニング・プログラムを組み入れているんだ。
スクワット、ランジ、ウエイトを組み合わせたトレーニングを毎日定期的にしているそうです。
【関連記事】
ランジとは、下半身を強化する運動で、真っ直ぐに立った姿勢から片足を前に一歩踏み出し、腰を沈めて前に出した足の太腿が、床と水平になるくらいまでしゃがみ込む、そして元の姿勢に戻ります。
この運動を交互に行うのがフォワードランジです。
このフォワードランジで鍛えられる筋肉はハムストリングス(太腿の裏側の筋肉)、大臀筋(おしり)、腸腰筋(足を持ち上げる筋肉、腰骨と足の付け根、背骨と足の付け根をつなぐ重要な筋肉、外から見えないのでインナーマッスルと言われます)、大腿四頭筋(太腿の筋肉)です。
足を前に踏み出すから太腿メインの運動と思われがちですが、後ろ側になった足に体重をかけることで、腸腰筋を鍛えることができます。
—抵抗運動を繰り返す事が減量の早道と言うのは本当でしょうか?
それは運動の組み合わせ次第! 例えば抵抗運動(レジスタンス・トレーニング)をする事によって、効果的にカロリーを燃焼する働きをする筋肉を強化する事がワークアウトの重要な要素! それから、血流を良くする“カーディオ”は、心臓の働きを強化すると言う効果も有り、抵抗運動とカーディオの組み合わせを上手に組み合わせるのが一番良い方法だと思うよ。
無酸素運動と有酸素運動を上手に組み合わせることが一番良い方法のようです。
【関連記事】
有酸素運動 : 糖や脂肪をエネルギーとして消費
レジスタンス運動(無酸素運動) : 筋肉量を増やし、基礎代謝の増加
■考え方
ガーナーの指導と自分自身の努力のおかげで役15ポンド(約7キロ)の減量に成功した事を本当に誇りに思っているわ。
キムは、ただ単に減量するだけではなく、女性らしいラインを維持したダイエットを目指している
体重が減らすことが大事なのではなく、女性らしいラインを維持したダイエットが大事ということなのではないでしょうか。