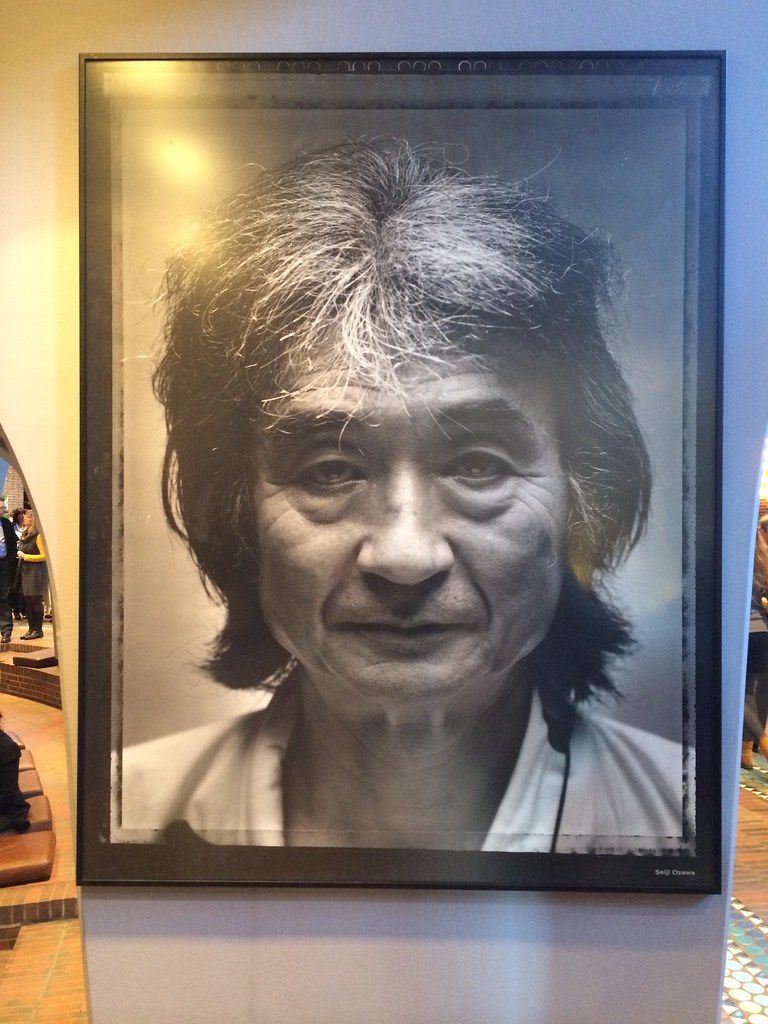by Trang Angels(画像:Creative Commons)
米加州議員が「痩せすぎモデル」規制法案、摂食障害のまん延懸念
(2016/2/23、ロイター)
マーク・レビン議員は今月19日、同州で働くことを希望するモデルに対して、健康な体重であり、摂食障害を患っていないことを証明する医師の診断書提出を義務付ける法案を提出した。
アメリカ・カリフォルニア州のマーク・レビン議員は、ファッションモデルの摂食障害を減らす取り組みとして、健康的な体重を保証する医師の診断書の提出を義務付ける法案を提出したそうです。
以前「痩せ過ぎ」モデルに健康的な体重を保証する医師の証明書の提出を義務付け|仏(2015/12/21)というニュースをお伝えしましたが、この動きは米カリフォルニア州にも広がっています。
【関連記事】
- 拒食症対策のため「痩せ過ぎモデル」に罰則を与える新規制―仏議会(2015/4/4)
- 【クローズアップ現代】女性のやせすぎ問題|痩せ過ぎと低体重児・モデルのヤセ過ぎ問題|10月5日
- 広告基準協議会、やせすぎモデルは「不健康」なためファッション誌広告NG-英
- VOGUE、モデルのやせすぎ問題に対策を発表
- ラルフ・ローレンのモデルの写真修正が話題に、やせすぎへの警鐘も
- 20代女性の5人に一人が「やせ」|摂取カロリーは終戦直後よりも少なくなっている!?
レビン議員は、ファッションモデルの40%が拒食症や過食症などの摂食障害に苦しんでいることを示すデータがある、と指摘している。
20代女性の5人に一人が「やせ」|摂取カロリーは終戦直後よりも少なくなっている!?によれば、20代女性の5人に一人が「やせ(BMI18.5未満)」という状態であるそうです。
また、2013年の20代女性の平均エネルギー摂取量は、終戦直後よりも少ないそうです。
【関連記事】
■まとめ
女性の摂食障害は大きな社会問題となっていますので、世界的にこの動きは広がっていくかもしれません。
【関連記事】
【2010年】
- ラルフ・ローレンのモデルの写真修正が話題に、やせすぎへの警鐘も(2010/1/7)
- 美の基準は一つではなく、健康の上にしか成り立たない。(2010/3/11)
【2012年】
- お尻が大きすぎて解雇されたモデルが訴訟に勝利(2012/3/12)
- 若い女性のやせ、「国民健康の脅威」|健康への影響や低体重児の増加の懸念(2012/4/16)
- VOGUE、モデルのやせすぎ問題に対策を発表(2012/5/7)
- ケイト・アプトンは朝にウェイトトレーニング、午後に有酸素運動を行なっている|Kate Uptonの登場により、カーヴィー・健康的なボディの時代がくる?(2012/8/2)
【2013年】
- H&M 水着PRにプラスサイズモデル起用(2013/5/24)
- 大御所モデルが「ケイト・アプトンは太っている」と批判(2013/12/17)
【2014年】
【2015年】
- 拒食症対策のため「痩せ過ぎモデル」に罰則を与える新規制―仏議会(2015/4/4)
- LANE BRYANT、「痩せすぎモデル」ではない女性たちによる「I’M NO ANGEL」キャンペーン(2015/4/9)
- 広告基準協議会、やせすぎモデルは「不健康」なためファッション誌広告NG-英(2015/6/5)
- 【クローズアップ現代】女性のやせすぎ問題|痩せ過ぎと低体重児・モデルのヤセ過ぎ問題|10月5日(2015/10/5)
- ぽっちゃりモデル(プラスサイズモデル)がランニング雑誌のカバーモデルを務めた!?(2015/7/21)
- 女性スターが「写真加工によって、美についての非現実的な理想を作り上げる」と批判(2015/11/7)
- 「痩せ過ぎ」モデルに健康的な体重を保証する医師の証明書の提出を義務付け|仏(2015/12/21)
【2016年】
- 「美しい」と「きれい」の言葉の違いとは?|ジェニファー・ローレンス、ハリウッドのルックス重視に苦言より(2016/1/5)
- 問題に対してユーモアで解決しよう!|アカデミー賞授賞式の司会クリス・ロック(Chris Rock)から学んだこと #Oscars(2016/2/29)
- 米加州議員が「痩せすぎモデル」規制法案、モデルの摂食障害を減らす取り組み(2016/2/24)
- 「aerie(エアリー)」はモデルの写真修正(デジタル加工)をやめたことで売り上げがアップしている!(2016/5/25)
- アリシア・キーズが始めた「#nomakeup」ムーブメントの意味とは!?(2016/6/6)
- 米国の10代ミスコン、水着審査を廃止|「きれい」から「美しい」へ女性に求める価値観が変わってきているために起きている(2016/6/30)
- #nike (#ナイキ)の #Instagram で大きめの体型をした #モデル を起用し称賛される!(2016/7/27)
- 「J.クルー × ニューバランス」アクティブウエア、ビジュアルにプロのモデルではなくリアルな女
性を起用(2016/10/7)