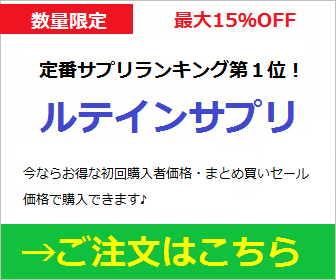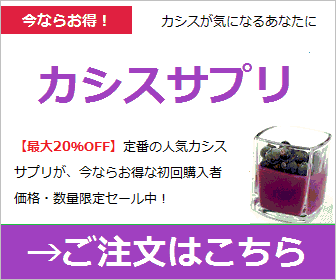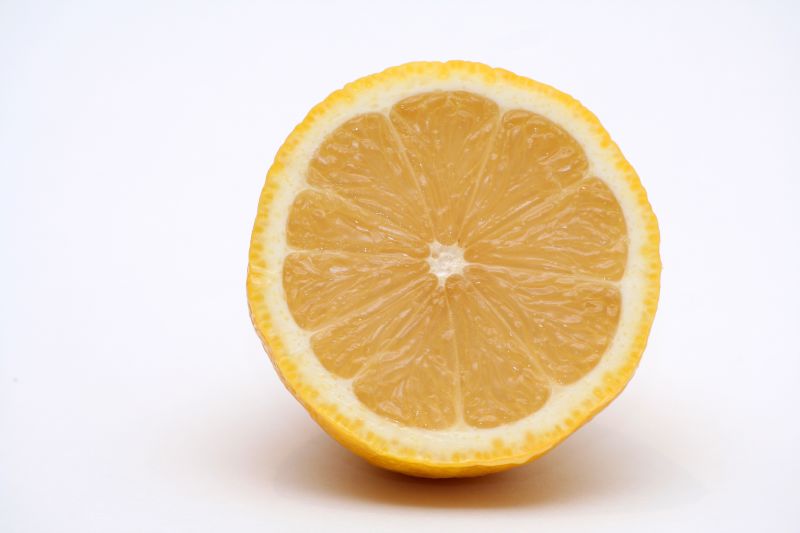> 健康・美容チェック > 目の病気 > 緑内障 > 【名医のTHE太鼓判】小倉優子さんに緑内障(視野が欠ける)の疑い「気づかなければ失明もあり得た」
【目次】
■【名医のTHE太鼓判】小倉優子さんに緑内障(視野が欠ける)の疑い「気づかなければ失明もあり得た」
by PACAF(画像:Creative Commons)
#小倉優子 さんは #名医のTHE太鼓判 で受けた“アイドック”で失明の危険性もある重大な疾患が見つかった。
✅目の角膜に無数の傷(コンタクトをとるとさすような痛み)
✅視野が欠けているhttps://t.co/qR2J97BLmT
— 4050health (@4050health) December 9, 2019
#小倉優子 さんは #名医のthe太鼓判 で受けた眼底検査の結果、「視神経が弱くなって視野が欠けている(視野の右下が見えていない)」という異常が発覚し「緑内障の疑い」と診断されました。#緑内障 とはhttps://t.co/CdT63YNuu7
— 4050health (@4050health) December 9, 2019
2019年12月9日放送の「名医のthe太鼓判」でアイドックを受けた小倉優子さんは「視神経が弱くなって視野が欠けている(視野の右下が見えていない)」という異常が発覚し「緑内障の疑い」と診断されました。
緑内障と診断された時、すでに66%の人は視野が欠けていたで紹介した緑内障フレンド・ネットワークの調査によれば、緑内障と診断された時、既に3人に2人は視野が欠けていたことがわかったそうです。
フィリングイン機能(視野を補う)により、緑内障になっても気づきづらい|みんなの家庭の医学によれば、人間は、片方の目に見えない所があっても、もう片方の目で補っており、両目でも視野が欠けているところがある場合、周りの風景から情報を作り出し、あたかも見えているように補正する機能(フィリングイン)を持っています。
緑内障は、このフィリングイン機能があることにより、視野を補ってしまうため、失明寸前まで視野の欠損に気づきづらいのです。
小倉優子さんにとっても、緑内障が見つかったのはショックなことだと思いますが、番組でアイドックを行なっていなければ、緑内障の性質上発見が見つからなかった可能性があり、早期治療ができていなかった可能性が高いです。
私たちも、緑内障を早期発見するために、定期的に眼科で検査を受けたり、また家庭の中でも、片目ずつで見て同じように見えるかどうかをチェックしてみましょう!
→ 緑内障チェック・見え方テスト について詳しくはこちら
→ 緑内障とは|緑内障の症状・原因・予防・チェック について詳しくはこちら
■緑内障の予防・検査
緑内障は、早期発見が大事ですので、眼科での定期的な検査(緑内障ドック)が一番の予防法といえます。
緑内障は、眼圧測定だけではわからないため、眼底検査、視野検査などが必要です。
また、緑内障は、ぶつかって眼圧が上昇する場合や生まれつき(隅角が未発達)でない場合には、生活習慣(糖分の摂りすぎ、血液がドロドロ、眼精疲労、ストレス、運動不足など)と何らかの関係があるのではないかと考えられています。
緑内障の治療・予防には、栄養補助食品(ルテイン・カシス等)や生活習慣の見直しなどによる日頃からのケアが重要です。
→ 緑内障の予防(食事・サプリメント) についてさらに詳しくはこちら
→ ルテインの健康効果 について詳しくはこちら
カシス・ルテイン・ブルーベリーサプリが、今なら最大20%引きの初回購入者価格・スーパーセール中!
→ カシスの健康効果 について詳しくはこちら
今なら最大20%引きのお得な初回購入者価格・まとめ買いセール特価で購入できます!