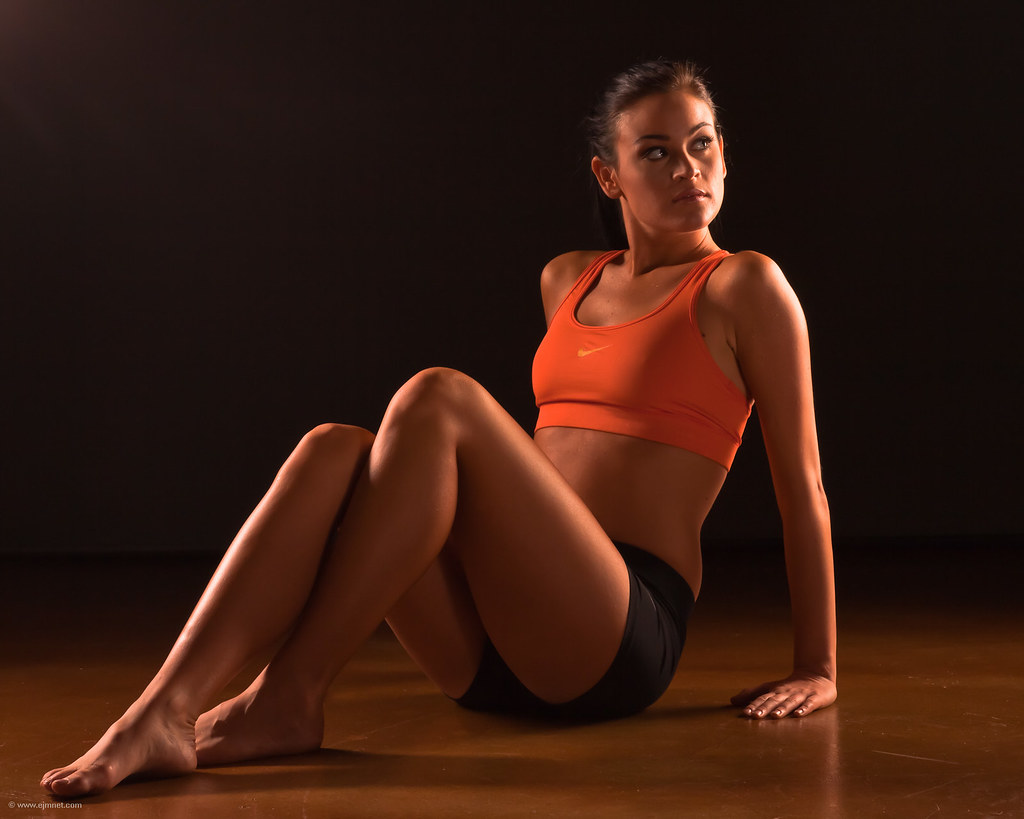タイラーニックス|unsplash
【藤井サチ】12kgストレス太り経験も…おうち時間で簡単に始められるサチ流のボディづくりとは(2021/3/15、ViVi)で紹介されているViViモデルの藤井サチさんのインタビューから学べることは5つ。
1.体のコンプレックス
2.女性のやせ問題・モデルのやせ問題
3.海外モデルがトレーニングを始めて意識が変化してきたこと
4.トレーニングによって自信がつくこと
5.ありのままの自分を受け入れること
1.体のコンプレックス
”もともとボリュームのある腰とお尻がコンプレックスだったの。「やせなきゃ」ってばかり思っていて。“やせている=キレイ”の概念がいつの間にかできてた。”
【藤井サチ】12kgストレス太り経験も…おうち時間で簡単に始められるサチ流のボディづくりとはhttps://t.co/OZn7pKPRUc
— 健康美容ブログ「HAKUR」|女性の知りたいがココにある! (@4050health) March 16, 2021
女性の9割は「体型」に自信がない(スタイルに不満がある)によれば、女性の約9割が自分の体型に自信がないそうです。
【関連記事】
- 「自分の体型に満足」な女性は0%、下半身に悩み
- 女性の8割が「色気に自信がない」
- 日本人女性の7割は自分の脚にコンプレックスを抱えている!?|下半身を引き締めるためのエクササイズの継続は難しい!
- 東京の女性はボディの肌に自信がない? 世界4都市で異なるボディケア意識
- 日本人女性がやせる理由は「優越感や日本人男性が好むから」?
- 女性は自身の顔を過小評価している!?
Dove Real Beauty Sketches | You’re more beautiful than you think (3mins)
女性は自身の顔を過小評価している!?|ダブ(DOVE)による美意識に関する実験で紹介した女性の顔を見ずに被験者本人とその女性を良く知る知人から髪の長さや顔の作り、特徴を聞き出し、その情報を元に2枚の似顔絵を描く実験によれば、知人の情報を元に描いた似顔絵の方が格段に美しいという結果が出たそうです。
今回の実験によれば、女性は自身の顔を過小評価しているということがわかったそうです。
つまり、いかに自分に自信を持ち、自分自身を適正に評価することが重要ではないかと考えられます。
2.女性のやせ問題・モデルのやせ問題
モデル≒痩せているというイメージがあって、ボリュームのある腰やお尻がコンプレックスになっていたのでしょうが、この数年で「女性の痩せすぎ問題」「モデルのヤセ過ぎ問題」が取り上げられて、世界の意識が変わってきたのを感じます。https://t.co/ImgjPx3VxO
— 健康美容ブログ「HAKUR」|女性の知りたいがココにある! (@4050health) March 16, 2021
”モデル業界はやせている人が多くて、私も中高生の頃はやせてなきゃいけないと思ってた。”https://t.co/OZn7pKPRUc
痩せることに対するプレッシャーは若い女性ほど感じているでしょうね。
若い女性のやせ、「国民健康の脅威」|健康への影響や低体重児の増加の懸念https://t.co/Ckn0q5n2tj
— 健康美容ブログ「HAKUR」|女性の知りたいがココにある! (@4050health) March 16, 2021
【クローズアップ現代(NHK)】女性の痩せすぎ問題|痩せ過ぎと低体重児・モデルのヤセ過ぎ問題でも取り上げていますが、この10年でやせ問題が取り上げられるようになりました。
3.海外モデルがトレーニングを始めて意識が変化してきたこと
”海外のモデルさんがすごく鍛えてかっこ良くて、トレーニングが仕事の一つになっているのを見て、私も、そうなりたいって思ったの。”https://t.co/OZn7pKPRUc
海外モデルが鍛えているのをみて意識が変わったんですね。#インスタ で海外モデルが鍛えた腹筋を見せる理由https://t.co/yds79YKFkX
— 健康美容ブログ「HAKUR」|女性の知りたいがココにある! (@4050health) March 16, 2021
痩せることに対するプレッシャーを若い女性ほど感じていたのですが、近年では海外モデルが美しい体のためにトレーニングで鍛えている姿がインスタなどで紹介されるようになり、意識が変わってきています。
4.トレーニングによって自信がつくこと
”トレーニングを始めたら、楽しくて達成感も生まれて自信になって。自分のために運動するようになったのね。コンプレックスのお尻に筋肉をつけて持ち上げて丸みを作れば、カーヴィーなカラダになれるんじゃないかって。”https://t.co/OZn7pKPRUchttps://t.co/jhT9e3RQ6i
— 健康美容ブログ「HAKUR」|女性の知りたいがココにある! (@4050health) March 16, 2021
74%の人がダイエットへの成功で自信が持てるようになった!で紹介した1年半以上ダイエットを続けて6キロ以上減量した成人2547人を対象に行なったアンケート調査によれば、良い影響があったと答えたのは92%いたそうです。
また、「自分に自信が持てるようになった」(74%)、「社交的になった」(69%)、「活発になった」(63%)という結果が出ています。
見た目に対しての評価(自己評価・他者評価)も上がっているでしょうし、目標を達成したことによる自信も出てきているのだと思います。
5.ありのままの自分を受け入れること
”まず、ありのままの自分を受け入れて好きになる。そのうえで、気になるところをカバーする。”https://t.co/OZn7pKPRUc
ありのままの自分を受け入れること、その上でなりたい自分になるを可能にすることが大事なんですよね。https://t.co/9TdMtVrpL4
— 健康美容ブログ「HAKUR」|女性の知りたいがココにある! (@4050health) March 16, 2021
藤井サチさんは、もともとボリュームのある腰とお尻がコンプレックスだったそうですが、藤井さん自身、女性らしさと強さを持つメリハリのあるカラダが好きで、トレーニングを始めたら、達成感も生まれて自信になり、また、コンプレックスを感じていたお尻に筋肉をつけて持ち上げて丸みを作れば、カーヴィーなカラダになれるんじゃないかと思うようになったそうです。
つまり、ありのままの自分を否定するのではなく、受け入れて、どううまくカバーしていくかが大事になってきています。
柏木由紀さんのようにすっぴんを見せて目の下のクマ、ニキビ跡、毛穴、シミといった肌の悩みを公開するのは難しいこと。ありのままのリアルを伝えることが共感を呼び、応援する人が増えていく。これができるかどうかが今一番大事なこと。https://t.co/MMiafJiP2H https://t.co/Xbp3D6iVao
— 健康美容ブログ「HAKUR」|女性の知りたいがココにある! (@4050health) January 10, 2021
さっしーってすごいですよね。人脈を使えばテレビのようなチャンネルにできるけど、それを自分で編集してますし、視聴者が何を観たいか、ありのままをどこまでさらけだせるかという今のトレンドを抑えてますし。さっしーは演者としてもプロデューサーとしてもすごい。https://t.co/XbJ3xqnA5m
— 健康美容ブログ「HAKUR」|女性の知りたいがココにある! (@4050health) March 4, 2021
柏木由紀さんのようにすっぴんを見せて目の下のクマ、ニキビ跡、毛穴、シミを公開するのは難しいことだけど、ありのままのリアルを伝えることが共感を呼び、応援する人が増えていくで紹介しましたが、柏木由紀さんや指原莉乃さんのようにすっぴんを見せて、どううまくメイクでカバーするかという動画が人気です。
これからはますますこの考え方が大事になってくるのではないでしょうか?