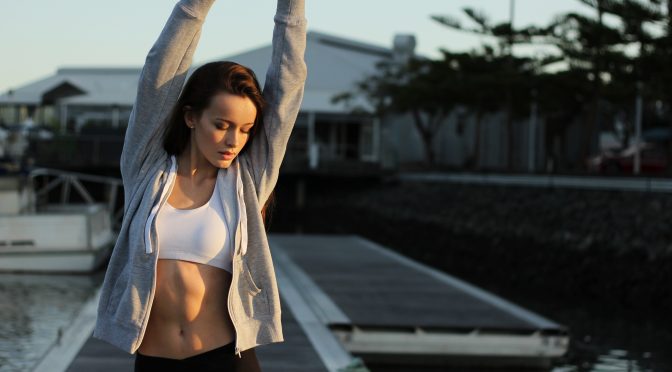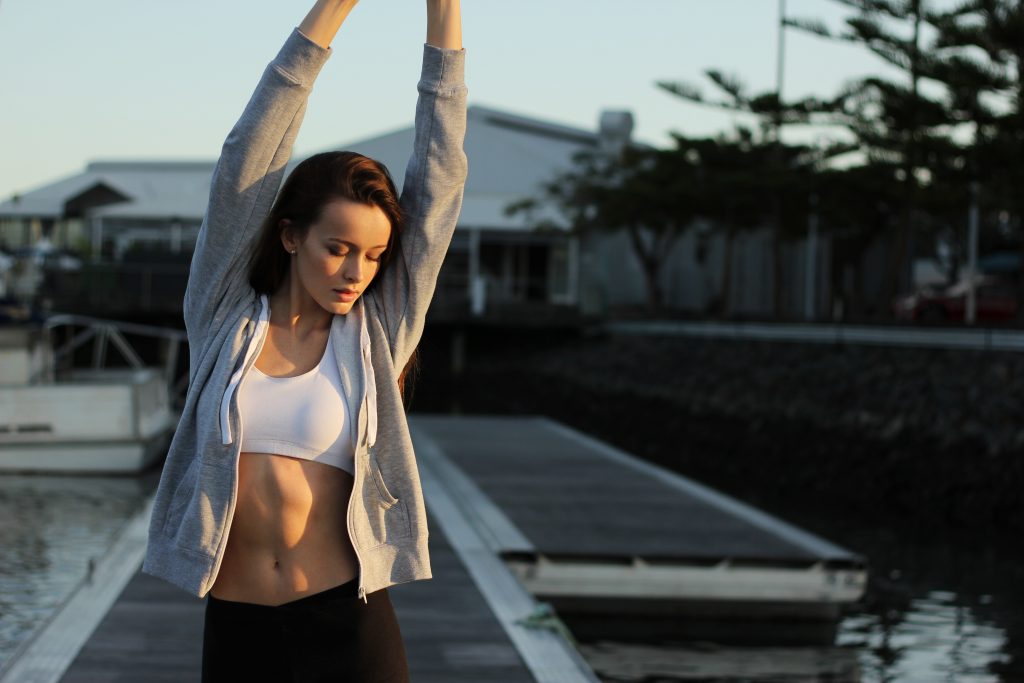2016年2月8日放送のバイキングのテーマは「健康の新常識」です。
【目次】
- 運動前にストレッチするとケガをしやすくなる!?
- 青魚を食べると寝付きが良くなる!?
- 食事によるコレステロール制限は意味がない?
- 紅茶を多くのむと骨折のリスクが低下する!?
- 食物繊維を摂り過ぎると便秘がひどくなる!?
1.運動前にストレッチするとケガをしやすくなる
by teammarche(画像:Creative Commons)
ジャンプ、スプリント、スクワット、ウエイトリフティング前のストレッチはパフォーマンスを低下させる!?によれば、運動前にストレッチをすると、パフォーマンス能力が低下するそうです。
なお、ストレッチによる怪我の頻度に違いは見られなかったそうです。
研究者の見解によれば、ストレッチは確かに筋肉や腱をほぐしてくれるが、それはもしかしたらのびのびになってしまった“古着のゴム”のように、筋肉の伸縮率を低下させてしまうのではないかと考えられるそうです。
筋トレ前のストレッチは逆効果?によれば、ヨガのように一つ一つの筋肉をじっくり伸ばして静止する静的ストレッチの場合、副交感神経を優位にすることで筋肉が弛緩してしまい、筋肉のパフォーマンスが落ちてしまうため、筋トレには逆効果なのだそうです。
なお、静的ストレッチは筋トレに後に行うと、筋肉が弛緩して血行が促進され、疲労回復につながり、筋トレに効果的みたいです。
2.青魚を食べると寝付きが良くなる!?
by Toshihiro Gamo(画像:Creative Commons)
DHAを補給した学齢期の児童は睡眠持続が向上する!? – オックスフォード大
(2014/3/12、マイナビニュース)
英国オックスフォード大学の研究チームによる研究の結果、長鎖オメガ3、特にDHA(ドコサヘキサエン酸)を補給した児童群は、連続的な睡眠を中断する短い時間帯でる「覚醒エピソード」が7回減少し、睡眠持続時間も一晩で58分延長される結果を得たこと、ならびに親による評価をもとに、良好な睡眠が取れているとされる児童ほど血中DHA濃度が高い可能性があることが示唆されたと発表した。
青魚に含まれるDHAには、中性脂肪を下げる効果や認知症予防が期待されていますが、1日600mgのDHAを16週間補給した子どものグループは、摂取しない人に比べて睡眠時間が1時間増え、睡眠が改善されるという結果が出たそうです。
DHAの1日摂取量600mg(例:マイワシの刺身3切れ分)
→ DHA・EPAの効果・効能・食品・摂取量 について詳しくはこちら
3.食事によるコレステロール制限は意味がない?
今回番組で取り上げた内容は、食事でコレステロール値は変わらない|日本動脈硬化学会が声明がもととなっています。
コレステロールは、食事で作られるのは10-20%、肝臓で作られるのは80-90%であるので、食事を制限しても意味がないと考えられるというものでした。
コレステロールにはHDLコレステロール(善玉コレステロール)とLDLコレステロール(悪玉コレステロール)があり、善玉が多く、悪玉が少ない方が血管の病気を起こしにくいと考えられています。
コレステロールは油から作られており、オリーブオイル、オメガ3(アマニ油、エゴマ油など)、DHA・EPAなどいい油を摂ることで血管の病気のリスクを下げることができると考えられるそうです。
→ コレステロールの比率のLH比(LDLとHDLの比率)とは について詳しくはこちら
4.紅茶を多くのむと骨折のリスクが低下する!?
by Nikki L.(画像:Creative Commons)
●紅茶の健康効果
- インフルエンザ予防
- 口臭予防
最近の研究によれば、紅茶を1日3杯以上飲んでいる人の骨折のリスクがほとんど飲まない人に比べて低いことがわかったっそうです。
<骨粗しょう症>紅茶のポリフェノール「テアフラビン」に予防効果で紹介した大阪大学の研究によれば、紅茶の苦み成分であり、抗酸化物質であるポリフェノール「テアフラビン」に骨の破壊を抑える効果があり、骨粗しょう症を予防する可能性があるそうです。
→ 骨粗しょう症の症状・原因・予防・食事 についてはこちら
5.食物繊維を摂り過ぎると便秘がひどくなる!?
最近では、ダイエット(特に食べない系のダイエット)や少食により、食事(特に便のもととなる食物繊維)そのものの量が減っているため、いい便が作られないことがあります。
現代人の生活は食物繊維が不足しているので、食物繊維は摂ってほしいのですが、人によっては、食物繊維の摂りすぎで、かえって便秘になることがあるそうです。
食物繊維といっても、食物繊維には不溶性食物繊維と水溶性食物繊維の2種類があり、不溶性食物繊維だけを摂りすぎると、便秘になりやすくなるケースがあります。
不溶性食物繊維には、便のカサを増して、腸の蠕動(ぜんどう)運動を促す働きがあるのですが、腸の機能が衰えている人がとりすぎると、腸が動かない(ぜんどう運動が起きない)ため、水分が腸に吸収されて便が固くなって、便秘になってしまうことがあるようです。
水溶性食物繊維には便をやわらかく、かつ滑りもよくする働きがあるので、水溶性・不溶性の食物繊維をバランスよく摂取するようにしましょう。
→ 便秘解消方法 について詳しくはこちら
→ 食物繊維の多い食品について詳しくこちら
【コレステロール関連記事】
続きを読む 【#バイキング】健康の新常識(ストレッチ・青魚・コレステロール・紅茶・食物繊維)