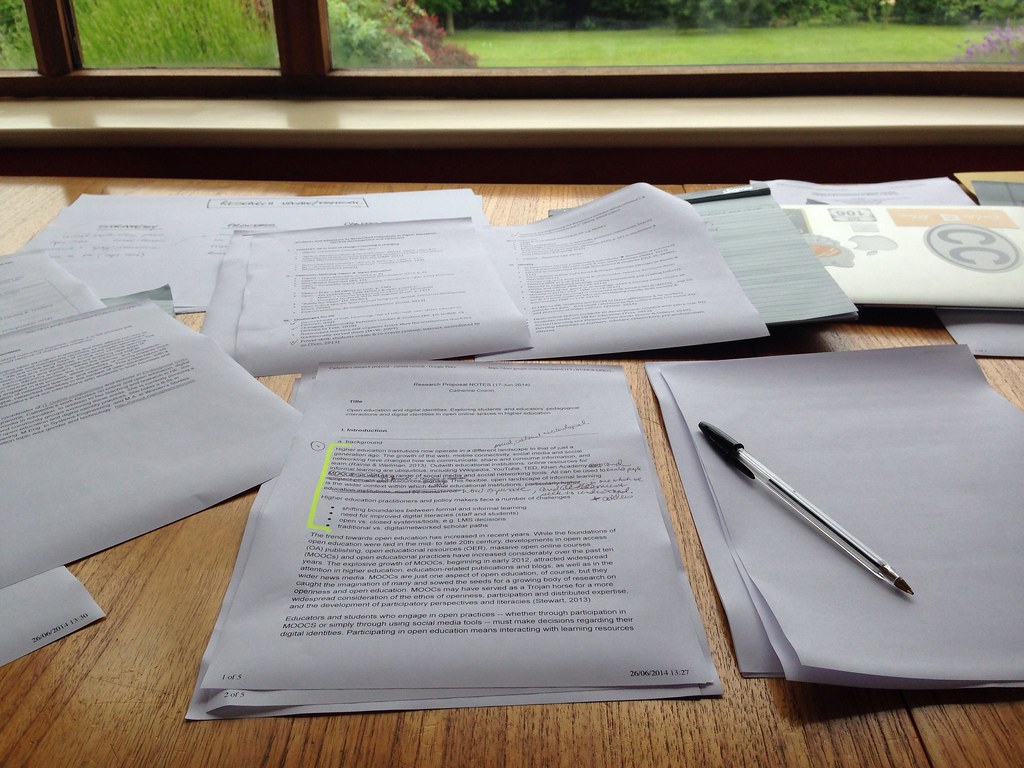2024年7月4日放送の黒柳徹子さんが司会の「徹子の部屋」に出演した高田純次(77)さんは、2022年に人間ドックで20個以上の大腸ポリープが見つかり、3度に及ぶ摘出手術を行なっていたことを告白しました。
→ 大腸ポリープの手術内容・大腸ポリープ切除後の食事の注意点|大腸ポリープ手術を受けた患者さんにインタビュー について詳しくはこちら
■有名人と大腸ポリープ
- ドランクドラゴン塚地さんにガン化の可能性の高い直径8MMの大腸ポリープが見つかる|ポリープの大きさが大きいほど大腸がんになるリスクが高くなり、ポリープの出来やすい人は大腸がんになるリスクが高い!
- #高橋ジョージ さんは、大腸がんの疑いがあり、大腸内視鏡検査を受けたところ、2MM程度の大腸ポリープが見つかる
- 【名医のTHE太鼓判】クロちゃん、人間ドックで大腸ポリープが判明!
- 梅沢富美男さん、大腸検診で「ポリープ」発見 今井雅之さんのアドバイスで
■大腸ポリープは大腸がんのリスクを高めるリスク要因
大腸ポリープは大腸がんのリスクを高めるリスク要因であると考えられています。
大腸がんのリスクファクター|国立がん研究センター
大腸がんの大部分は腺腫性ポリープから発生するが,一方,ほとんどの腺腫性ポリープは良性であり,がん化するのは一部である.ポリープの大きさが大きければ大きいほど大腸がんになるリスクが高くなる.また,ポリープのできやすい人は,大腸がんになるリスクが高い.
ポリープの大きさが大きいほど大腸がんになるリスクが高くなり、また、ポリープの出来やすい人は大腸がんになるリスクが高いことから、大腸ポリープをいかに小さく、またできにくくするかは大腸がん予防の一つのアプローチといえます。
■大腸ポリープを予防する方法
大腸がんになりにくい体質にするための方法|#ガッテン(#NHK)
大腸がんでは、直系の親族に大腸がんの人がいることは、大腸がんのリスク要因とされていますが、生活習慣を改善することによって大腸がんになりにくい体質にすることも可能なのだそうです。
●禁煙
●アルコールを控える
肥満や飲酒なども大腸がんリスクとされています。
大腸がん予防方法・大腸がんの危険度チェックによれば、最もリスクが高いのは飲酒。
飲酒による大腸がんのリスクは一日に日本酒を1合⇒1.4倍、2合⇒2.0倍、3合⇒2.2倍、4合⇒約3倍となっているそうです。
●運動
運動は、大腸がん予防に非常に効果が高いことがわかっているそうです。
全身運動(水泳・ジョギング・ダンスなど)がおすすめなのだそうです。
※大腸がん危険度チェックによれば、毎日合計60分歩く程度の運動をしていない方が運動不足に該当します。
●葉酸
【みんなの家庭の医学】大腸がん予防に葉酸の多い海苔|10月20日によれば、大腸がんのリスクを高める大腸ポリープのできやすさと葉酸の濃度には関係があるといわれ、血液中の葉酸濃度の値が8ng/ml(ナノグラム)以上あれば、女性なら大腸ポリープの頻度が約2割減、男性なら約5割減するそうです。
→ 葉酸の多い食品 について詳しくはこちら
●ラクトフェリン
ラクトフェリンに大腸ポリープの成長を抑える作用|国立がんセンターと森永乳業で紹介した国立がんセンターと森永乳業の研究によれば、ラクトフェリンに大腸ポリープの成長を抑える作用があることがわかったそうです。
どのような仕組みでポリープが縮小しているかはこの研究ではわかっていないものの、ラクトフェリンを毎日3グラム摂取することにより、血中のラクトフェリン濃度が上昇し、免疫が増強していることを示すNK細胞の活性が上がっていたことから、ラクトフェリンとNK細胞の活性化に何らかの関連性があるのではないかという仮説が立てられます。
●メトホルミン
大腸がん予防に期待 糖尿病薬メトホルミンに大腸ポリープの再発を防ぐ効果|横浜市立大
横浜市立大の中島淳教授によれば、糖尿病薬として使われているメトホルミンに大腸がんの恐れのあるポリープの再発を抑制する効果があることがわかったそうです。
糖尿病治療薬「メトホルミン」にがん細胞を破壊するキラーT細胞を活性化する作用があることが判明‐岡山大研究グループによれば、糖尿病治療薬「メトホルミン」にがん細胞を破壊するキラーT細胞を活性化させる作用があることがわかったそうです。
→ 大腸がんの症状・初期症状・原因 について詳しくはこちら
■葉酸と大腸がんについて
■葉酸代謝が大腸がんの発がんの初期段階で重要な働きを示している
葉酸代謝と大腸腺腫との関連|多目的コホート研究|国立がん研究センター
大腸発がんには、DNAのメチル化が関わっていると考えられています。適切なDNAメチル化の維持には、葉酸が重要な役割を果たしていることが知ら れています。葉酸は、メチレンテトラヒドロ葉酸還元酵素(MTHFR)、メチオニン合成酵素(MTR)、メチオニン合成酵素還元酵素(MTRR)などの酵素群とビタミンB2、B6、B12などの補酵素群の働きにより代謝され、DNAのメチル化に必要なメチル基を供給しています(図1)。
葉酸、ビタミンB2、B6、B12摂取については、大腸腺腫との間に統計学的有意な関連は見られませんでした。
大腸がんの発がんにはDNAのメチル化がかかわっていると考えられており、葉酸が重要な働きを果たしていると考えられますが、葉酸、ビタミンB2、B6、B12摂取と大腸線種との間に統計学的な関連は見られなかったようです。
メチオニン合成酵素 の遺伝子多型とアルコール摂取および葉酸摂取との間に交互作用を認めたことは、「葉酸代謝が大腸発がんの初期段階において重要な役割を果たしている」とするこれまでの研究結果を支持するものであると考えられます。
ただ、葉酸代謝が大腸がんの発がんの初期段階で重要な働きを示していることは間違いないようです。
■葉酸濃度が高くても大腸がんリスクが下がるという関連は見られない
血中の葉酸と大腸がん罹患との関係について|多目的コホート研究|国立がん研究センター
これまでの研究では、葉酸が不足している場合に、わずかに大腸がんリスクが高くなることが示されていますが、日本人の多くでは必要な量が摂取されているため、その中での差が見られなかったという可能性があります。また、葉酸は、大腸がんの多段階発がんの初期の段階では予防的に働くにも関わらず、進行した段階ではかえって促進するという可能性を示す研究結果もあります。また、ある特定の遺伝子多型のタイプの人やアルコールを多量に飲む人で、葉酸不足によって大腸がんリスクが高くなるという研究結果もあります。
葉酸と大腸がんの関係については様々な研究が行なわれています。
- 葉酸が不足している場合に、わずかに大腸がんリスクが高くなる
しかし、日本人の多くでは必要な量が摂取されているため、その中での差が見られなかったという可能性 - 葉酸は、大腸がんの多段階発がんの初期の段階では予防的に働くにも関わらず、進行した段階ではかえって促進するという可能性
- ある特定の遺伝子多型のタイプの人やアルコールを多量に飲む人で、葉酸不足によって大腸がんリスクが高くなる
多目的コホート研究では、男女とも、葉酸濃度が高くなっても、大腸がんリスクが下がるという関連はみられませんでした(図1)。また、飲酒量でグループ分けしても、結腸がんと直腸がんに分けて調べても、どのグループでも男女とも関連は見られませんでした。
国立がん研究センターが発表している多目的コホート研究によれば、葉酸濃度が高くても大腸がんリスクが下がるという関連は見られなかったそうです。
葉酸、ビタミンB6、ビタミンB12、メチオニン摂取と大腸がん罹患との関連について|多目的コホート研究|国立がん研究センター
葉酸、ビタミンB6、ビタミンB12、メチオニンは、生体内でのメチル代謝において、それぞれ異なる役割を担っています。アルコールやアセトアルデヒドはそれらの代謝経路を阻害したり、栄養素を破壊したりすることによって、大腸がん発がんの初期段階である遺伝子の低メチル化を引き起こすと考えられます。
今回、特にビタミンB6と大腸がんの関連が強かった理由として、日本人の一般的な食事からは葉酸やビタミンB12は十分取れるのに対し、ビタミンB6摂取量は不足していることが挙げられます。その最大の摂取源は白米ですが、茶碗1杯(約150g)に約0.03mgのビタミンB6しか含まれていません。ビタミンB6を多く含む食品(魚・ナッツ・穀類等)を積極的に摂取することが、大腸がんの予防につながる可能性があります。
日本人の一般的な食事からは葉酸は十分に摂取できるため、差が見られなかった可能性が考えられます。
【関連記事】
続きを読む 高田純次さん、人間ドックで20個以上の大腸ポリープが見つかり、3度に及ぶ摘出手術を行なっていた!【徹子の部屋】