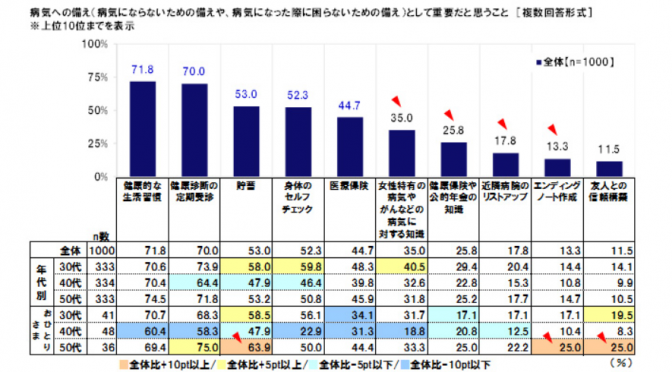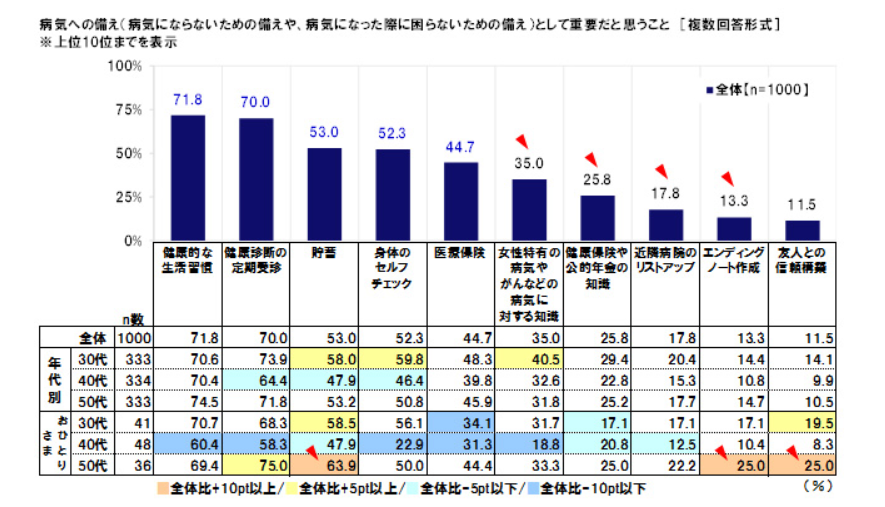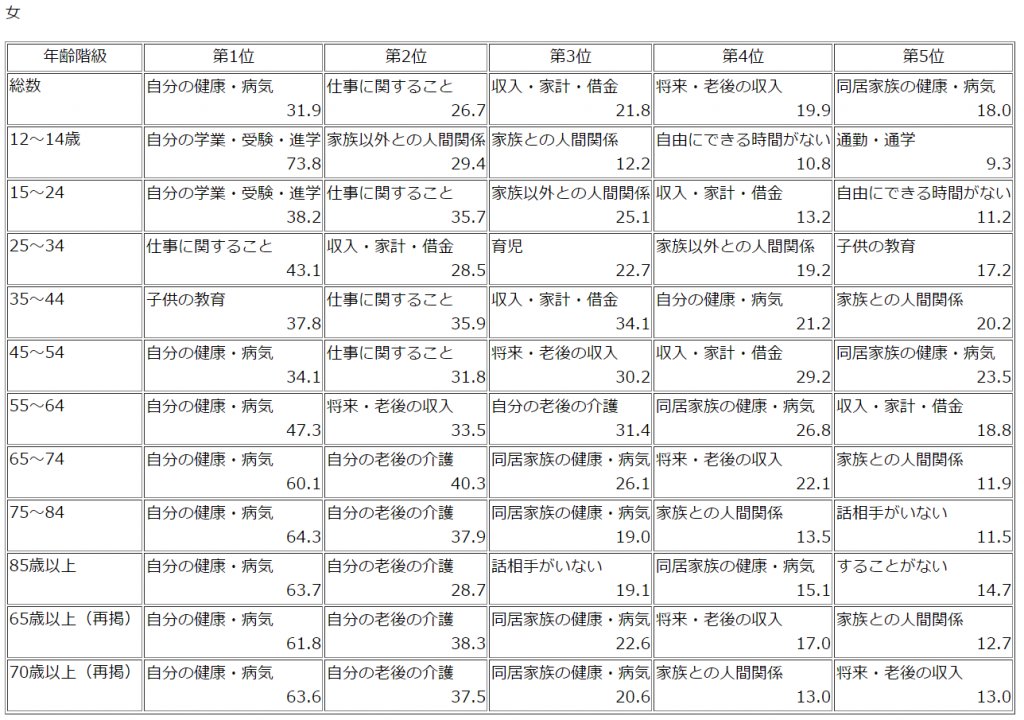> 健康情報 > 健康・美容チェック > 肝臓 > 肝臓の病気 > 肝機能の低下がわかるチェックリストと肝臓病の初期症状のサイン > 手のひらが赤くなる|なぜ肝臓が悪くなると掌が赤くなるのか|肝臓の病気の症状
肝硬変|肝炎情報センターでは、肝硬変の症状の一つとして、「手掌紅班」が挙げられています。
肝臓の病気の初期症状として「手のひらが赤くなる(手掌紅斑)」がありますが、なぜ「手のひらが赤くなる」という症状が起こるのでしょうか。
【目次】
■手のひらが赤くなる(手掌紅斑)症状

isco|unsplash
手のひらの母指球(親指の付け根の膨らみ)や子指球(小指の付け根の膨らみ)などが、斑状に赤紫になった状態。
肝臓病の初期症状として、親指と小指の付け根の膨らんだところが>斑状に赤くなる(赤紫色になる)脂肪肝より少し進んでいる場合があり、肝硬変や慢性肝炎の恐れがあるので、血液検査を受けたほうが良いそうです。
→ 肝炎とは|肝炎(B型・C型・アルコール性)の症状・原因・チェック について詳しくはこちら
→ 肝硬変とは|肝硬変の症状・原因・食事 について詳しくはこちら
■手のひらが赤くなる(手掌紅斑)原因|なぜ肝臓が悪くなると手のひらが赤くなるのか
手掌紅斑の原因は、肝機能障害によって肝臓でエストロゲンの処理ができなくなり、血液中のエストロゲンが上昇するためと考えられている。
肝臓では血管拡張作用があるエストロゲンの処理を行なっています。
肝機能低下によって肝臓でエストロゲンの処理ができなくなると、血液中のエストロゲンが上昇することにより、掌が斑状に赤くなると考えられます。
また、手掌紅斑はクモ状血管拡張(胸の上部や首、上腕などにクモの巣状の毛細血管が浮き出て、赤い斑点ができる)という症状が一緒に起こることが多いです。
→ 肝機能障害の症状・原因・食事・肝機能の数値 について詳しくはこちら
■まとめ
肝臓の病気になり、肝機能が低下すると、手のひらが赤くなるという症状が起こることがあります。
特徴としては、手の平全体が赤くなるのではなく、真ん中は白いままで、親指の付け根と小指の付け根の膨らんだところが赤くなります。
手掌紅斑が現れている場合には、脂肪肝より少し進んでいる場合があり、肝硬変や慢性肝炎の恐れがあるので、血液検査を受けることをおすすめします。
→ 肝臓の病気|肝臓病の初期症状・種類・原因 について詳しくはこちら
→ 肝臓の数値|γ-GTP・GOT(AST)・GPT(ALT)|肝臓の検査 について詳しくはこちら
→ 肝機能の低下がわかるチェックリストと肝臓病の初期症状のサイン について詳しくはこちら
■肝臓を助ける栄養・食事