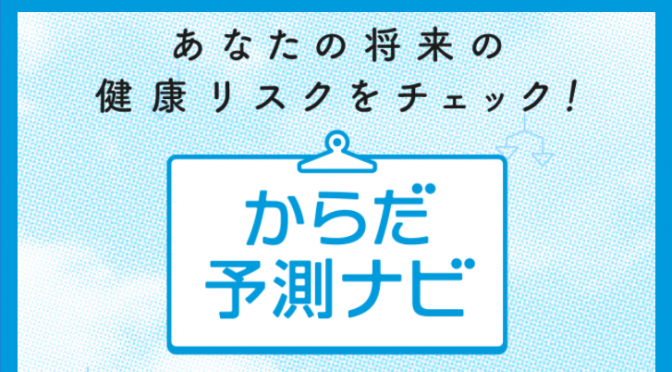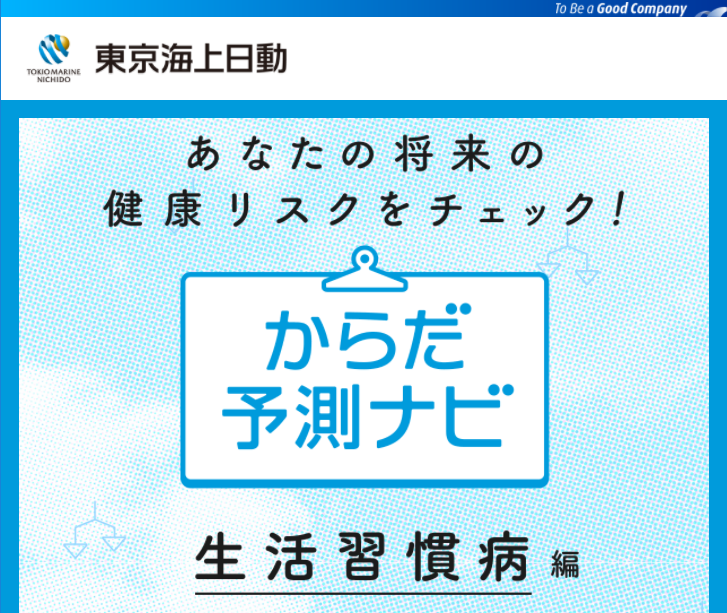> 健康・美容チェック > 脳卒中 > 人工甘味料入りのダイエット飲料を飲む人は脳卒中・認知症の発症リスクが約3倍高い!?|ボストン大学医学校
■人工甘味料入りのダイエット飲料を飲む人は脳卒中・認知症の発症リスクが約3倍高い!?
by frankieleon(画像:Creative Commons)
(2017/4/21、CNN)
調査はボストン大学医学校の研究チームが米マサチューセッツ州フレミンガムに住む45歳以上の2888人と、60歳以上の1484人を対象に実施し、1991~2001年にかけて糖分の多い飲料水と人工甘味料入りの飲料水を摂取した量を調査。このデータと比較して、45歳以上のグループでは以後10年間の脳卒中の発症率を調べ、60歳以上のグループでは認知症の発症率を調べた。
その結果、人口甘味料入りの清涼飲料水を1日1回の頻度で飲んでいた人は、そうでない人に比べて、虚血性脳梗塞(こうそく)を発症する確率がほぼ3倍に上ることが分かった。
同様に、認知症と診断される確率もほぼ3倍に上っていた。
ボストン大学医学校の研究チームの調査結果によれば、人工甘味料を使った清涼飲料水を飲んでいた人は、脳卒中や認知症を発症するリスクが約3倍高いということがわかったそうです。
今回の調査結果を分解して考えてみたいと思います。
■脳卒中と糖尿病の関係
●なぜHbA1cの値が高いと心筋梗塞や脳卒中のリスクが高まるのか?|国立がん研究センターと東京女子医大などで紹介した国立がん研究センターと東京女子医大などのチームによれば、HbA1cの値が高いと、心筋梗塞や脳卒中のリスクが高まるそうです。
●低血糖でも脳梗塞リスクがある?|ヘモグロビンA1cが低くても脳梗塞や心筋梗塞のリスクが上がる|国立がん研究センターによれば、HbA1cが6・5%以上の人は、5・0~5・4%の人に比べ、心血管疾患になるリスクが1・8倍だったそうです。
また、この調査結果によれば、ヘモグロビンA1c(HbA1c)が高い場合だけでなく低くても脳梗塞や心筋梗塞のリスクが上がるそうです。
●2型糖尿病で動脈硬化が進行した患者は低血糖でも高い脳卒中・心筋梗塞の危険性が高まる|神戸の医師らが調査によれば、2型糖尿病で動脈硬化が進行した患者の場合は、血糖値が高すぎるだけでなく、低すぎても脳卒中や心筋梗塞の危険性が高まるそうです。
→ 脳卒中 について詳しくはこちら
■認知症と糖尿病の関係
●認知症の発症リスクが高いのは、脳卒中の経験がある人、糖尿病や心臓病の持病がある人、握力が弱い人、うつ傾向がある人で紹介した国立長寿医療研究センターなどのチームによれば、脳卒中の経験がある人、糖尿病の人は、認知症を発症するリスクが高いそうです。
●糖尿病になると、認知症の発症リスクが2倍高くなる!?で紹介した東京大の植木浩二郎特任教授によれば、糖尿病になると認知症の発症リスクが2倍高くなるそうです。
●認知症チェック・認知症予防にアマニ油・デジタル認知症|駆け込みドクターによれば、糖尿病・高血圧・脂質異常症などの生活習慣病のリスクの高さと認知症(アルツハイマー病)には関係があり、アルツハイマー病の発症リスクは、糖尿病だと2倍、高血圧だと2倍、脂質異常症だと3倍になるそうです。
●アルツハイマー病の「脳糖尿病仮説」の実証|「メマンチン」が脳インスリンシグナルを改善|東北大で紹介した東北大学大学院薬学研究科の森口茂樹講師、福永浩司教授らの研究グループはアルツハイマー病治療薬である「メマンチン」が脳インスリンシグナルを改善することを発見しました。
今回の研究は、アルツハイマー病の「脳糖尿病仮説(アルツハイマー病は脳で起こる糖尿病なのではないか)」とする仮説を実証した初めての成果であるというのがポイントです。
●糖尿病患者の半数でアルツハイマーの初期症状を確認で紹介した加古川市内の病院に勤務する医師らの臨床研究によれば、糖尿病の通院患者の半数以上に、「海馬傍回(かいばぼうかい)」と呼ばれる脳の部位が萎縮(いしゅく)するアルツハイマー病の初期症状がみられることがわかったそうです。
インスリンには記憶、学習機能を高める作用もあり、糖尿病でインスリン反応性が低下することが、アルツハイマー病発症につながっている可能性があるようです。
→ 認知症対策|認知症に良い食べ物・栄養 について詳しくはこちら
●インスリン抵抗性を伴った2 型糖尿病にアルツハイマーのリスク|九大研究によれば、インスリン抵抗性を伴った2型糖尿病の場合、アルツハイマーの発症に関係があるとされるプラークが形成されるリスクが高くなるという研究結果が発表されたそうです。
九州大学の研究によれば、血糖値の異常が認められた患者にはプラークが形成されるリスクが高いという結果がでたそうです。
こうした研究をまとめると、糖尿病になるとアルツハイマー型認知症になるリスクが高くなるのではないかという仮説が立てられます。
しかし、今回の調査結果を考えると、違った視点が見えてきます。
糖分の多い飲料でも、人工甘味料を使わない清涼飲料水やフルーツジュースなどでは、脳卒中や認知症のリスクが増大する傾向はみられなかった。
今回の調査結果によれば、血糖値の高さではなく、人工甘味料だけに脳卒中や認知症のリスクを高くする要素があるのではないかという仮説が立てられることになります。
→ 糖尿病の症状・初期症状 について詳しくはこちら
→ 糖尿病危険度チェック について詳しくはこちら
■人工甘味料と健康の関係
by Steve Snodgrass(画像:Creative Commons)
人工甘味料で糖尿病リスク増!?|人工甘味料は腸内細菌のバランスを崩して、血糖値が下がりにくい状態にする作用がある!?で紹介したイスラエルの研究チームによれば、サッカリンやスクラロース、アスパルテームなどの人工甘味料は腸内細菌のバランスを崩して、血糖値が下がりにくい状態にする作用があるという研究結果が発表されました。
ダイエット清涼飲料の飲みすぎの人は、胴囲の増加が飲まない人の6倍にで紹介した記事によれば、今回の記事とは考え方が違うものの、アステルパームという人工甘味料が健康に対して何らかの影響を与えていると考えられていました。
- 糖尿病の初期段階に起こりやすい膵臓(すいぞう)内の損傷に少なからず影響を与えている
- 人工甘味料は食欲を促進させ、満足感を感知する脳の細胞に損傷を与える。
砂糖のような自然の糖分の不足により、さらに甘いものへの欲求が増す。
両方の記事に共通するのは、人工甘味料には、糖尿病へのリスクを高める要因があると考えられるというものであり、人工甘味料が腸内細菌のバランスを崩すことによって、代謝異常を引き起こす可能性があるということです。
肥満やメタボの第3の要因に腸内細菌叢が関係している?和食を食べて予防しよう!によれば、肥満やメタボリックシンドロームを引き起こす第三の要因として腸内細菌叢が関係しているのではないかと考えられているそうです。
■まとめ
(2017/4/22、朝日新聞)
人工甘味料の摂取が発症リスクを高めるのか、発症しやすい体質や生活習慣の人がダイエット飲料を好んで飲んでいるのかは現時点でわからないという。
これまでは、糖尿病と認知症の関係について多く研究されていましたが、今回の研究では人工甘味料の摂取が認知症や脳卒中のリスクを増大させる可能性があるということですので、ぜひ人工甘味料と糖尿病、認知症、脳卒中の関係について解明してほしいですね。