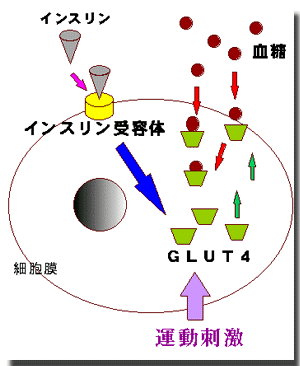> 健康・美容チェック > 糖尿病 > 12.08%の妊婦に妊娠糖尿病がある!若いころから血糖値について学ぼう!
 12.08%の妊婦に妊娠糖尿病がある!若いころから血糖値について学ぼう!
12.08%の妊婦に妊娠糖尿病がある!若いころから血糖値について学ぼう!
JuanEncalada|unsplash
元SDN48・奈津子 妊娠糖尿病を振り返る「妊娠糖尿病になる人が結構多いんだ!」という驚きも(2022/5/3、たまひよ)によれば、妊娠糖尿病と診断された奈津子さんは産院からの指導で、起床時と朝・昼・晩の食後2時間後に、毎回血糖値を計測してノートに記録することからどんな食事をどのくらいの量をとることで身体にどのような影響を与えるのか、低糖質系のレシピ本を読んで栄養の勉強を行ない、運動(散歩)を行なったそうです。
■妊娠糖尿病とは?
妊娠糖尿病とは、妊娠をきっかけにインスリンの働きが落ち、インスリン分泌量が十分に増えずに血糖値が高くなる状態。
妊娠糖尿病になると、胎児が大きくなりすぎたり、早産や妊娠高血圧症候群を起こす恐れがあります。
●妊娠糖尿病の女性が2型糖尿病を発症するリスクは高い!で紹介したロンドンにある病院のグループの研究によれば、妊娠糖尿病の女性が2型糖尿病を発症するリスクは、正常血糖の妊婦に比べ7.43倍に上るそうです。
2型糖尿病になる女性を少なくするためにも、妊娠糖尿病にならないように、検査などでの早期発見や食生活の改善・指導を行うようにしていく必要がありそうです。
●20歳の時に痩せている女性が妊娠すると、妊娠糖尿病になる危険性が高まる?で紹介した筑波大水戸地域医療教育センターの谷内洋子博士研究員の分析によれば、女性の20歳時の体重を聞き、BMIが18未満の「痩せている」に該当している女性は、BMIが18以上で肥満でない女性と比べ、妊娠糖尿病を発症する可能性が約5倍高かったそうです。
なぜ20歳のときに痩せている女性が妊娠すると、妊娠糖尿病になる危険性が高まるのでしょうか?
それは痩せている女性は、青年期に必要な栄養の不足や筋肉量が少ないことが血糖値を高めている可能性があるそうです。
●<妊娠糖尿病>発症防ぐ仕組み解明 インスリンの機能低下改善 順天堂大などによれば、妊娠中に、すい臓のインスリン分泌細胞内で「セロトニン」が大量に作られていることが発見され、このセロトニンによって、インスリン分泌細胞が増殖しているようです。
つまり、妊娠糖尿病の場合は、セロトニンの量が少ないため、インスリンの分泌細胞が増えず、機能低下を補うことができないために起きているようです。
■まとめ
今回の記事では、病院で担当した女性の医師や食生活の指導を病院専属の栄養士も妊娠糖尿病だったそうで、また、日本内分泌学会と日本糖尿病・妊娠学会によれば、12.08%の妊婦に妊娠糖尿病があるということで、妊娠糖尿病は決して珍しいものではないようです。
【参考リンク】
- 妊娠糖尿病|日本内分泌学会
近年のわが国における糖尿病患者数の増加と共に、晩婚化・晩産化に伴い、増加傾向にあります。全妊婦に糖負荷試験をしたとすると、12.08%の妊婦に妊娠糖尿病があることがいわれており、これに既存の糖尿病と糖尿病合併妊娠を加えると約15%の妊婦が耐糖能異常と診断されます。
- 1. 妊娠糖尿病はどれくらいの頻度であるのですか?|日本糖尿病・妊娠学会
これまでの診断基準では、わが国の妊娠糖尿病の頻度は2.92%でしたが、2010年7月に大規模な診断基準の変更があったため、妊娠糖尿病の頻度は12.08%と4.1倍に増えることがわかりました。
これまでの記事で、若く痩せている女性が妊娠すると妊娠糖尿病になるリスクが高く、また妊娠糖尿病の女性が2型糖尿病を発症するリスクは高いことから、若いころから栄養について、血糖値コントロールについて学んでいきたいですね。
→ 血糖値(正常値・食後血糖値・空腹時血糖値)・血糖値を下げる食品

菊いも茶(3g×10パック)【長崎県産有機菊芋使用】【機能性表示食品(血糖値の上昇を抑える)】【送料無料】【産直便】 2,435円(税込)
 糖尿病関連ワード
糖尿病関連ワード
■糖尿病の症状・初期症状|糖尿病とは
■糖尿病の診断基準(血糖値・HbA1c)
■糖尿病改善・予防する方法(食べ物・運動)
■糖尿病危険度チェック
■糖尿病の原因(生活習慣)|女性・男性
■薬局でもできる糖尿病の検査|検尿(尿糖検査)と採血による血糖検査
■糖尿病の合併症|網膜症・腎症・神経障害
■糖尿病の食事(食事療法)|血糖値を抑える食べ方
■糖尿病の運動(運動療法)|筋トレ・有酸素運動
■インスリン(インシュリン)とは|血糖を下げる働きがあるホルモン
■血糖値(正常値・食後血糖値・空腹時血糖値)・血糖値を下げる食品
「本記事は医療行為の代替ではなく、テレビ・論文・公的資料を一般の生活者向けに噛み砕いたものです」
この街を初めて訪れた方へ
この記事は、例えるなら「ばあちゃんの料理教室(ハクライドウ)」という街の中の「ひとつの家」です。
この街には、生活・料理・健康についての記事が、
同じ考え方のもとで並んでいます。
ここまで書いてきた内容は、
単発の健康情報やレシピの話ではありません。
この街では、
「何を食べるか」よりも
「どうやって暮らしの中で調整してきたか」を大切にしています。
もし、
なぜこういう考え方になるのか
他の記事はどんな視点で書かれているのか
この話が、全体の中でどこに位置づくのか
が少しでも気になったら、
この街の歩き方をまとめたページがあります。
▶ はじめての方は
👉 この街の歩き方ガイドから全体を見渡すのがおすすめです。
▶ この街の地図を見る(全体像を把握したい方へ)
※ 無理に読まなくて大丈夫です。
気になったときに、いつでも戻ってきてください。
この考え方の全体像(意味のハブ)
この記事で触れた内容は、以下の概念記事の一部として位置づけられています。
▶ 料理から見る健康
この街の考え方について
この記事は、
「人の生活を、断定せず、文脈ごと残す」
という この街の憲法 に基づいて書かれています。
▶ この街の憲法を読む


-e1534902412651-672x372.jpg)
-e1534902412651-768x1024.jpg)