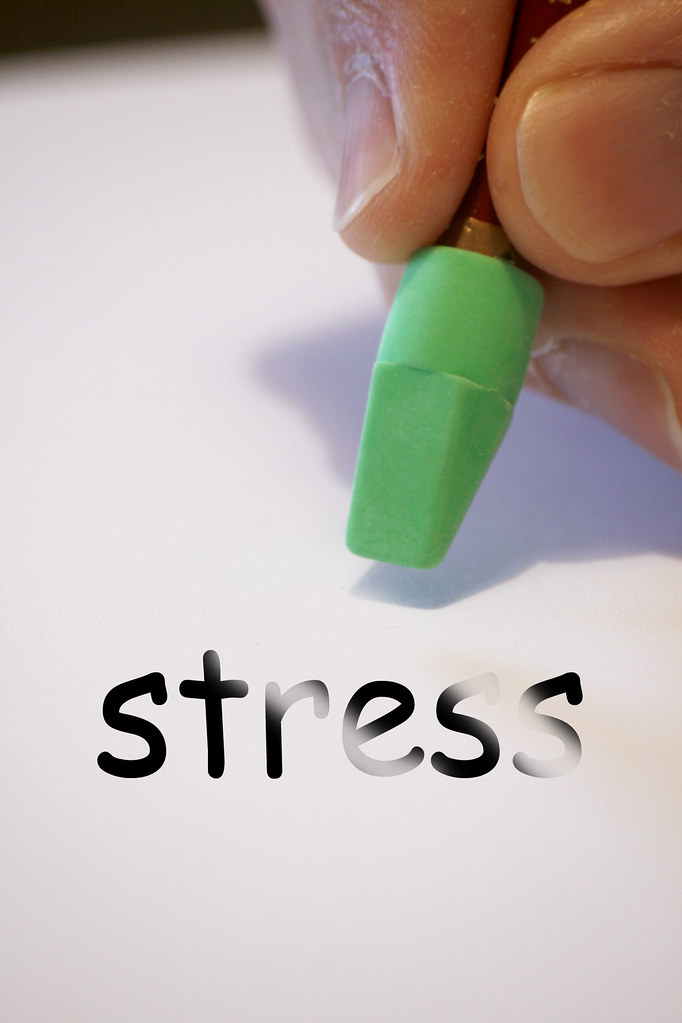by Ritesh Man Tamrakar(画像:Creative Commons)
> 健康・美容チェック > 不妊 > 男性不妊 > 男性不妊治療に期待 「ゲノムの守護神」発見|京大グループ
「ゲノムの守護神」発見 京大グループ 男性不妊治療に期待
(2009/12/15、京都新聞)
雄の生殖細胞で「ゲノムの守護神」として働いているタンパク質を、京都大の中辻憲夫・物質―細胞統合システム拠点教授と中馬新一郎・再生医科学研究所助教らが発見した。
男性不妊症の診断や治療への応用が期待できるという。
米科学誌「デベロップメンタルセル」に15日発表する。
京都大の中辻憲夫・物質―細胞統合システム拠点教授と中馬新一郎・再生医科学研究所助教らの研究によれば、男性不妊症の診断や治療への応用につながる発見があったそうです。
Tdrd9には、レトロトランスポゾンのRNAを選択的に細かく切断する機能があった。
レトロトランスポゾンのRNAを切断して飛び回れなくするとともに、切断されたRNAがレトロトランスポソン本体に作用し、発現が抑えられていることが分かった。
Tdrd9の機能異常が無精子症の原因の一つになっている可能性があり、Tdrd9を標的とした男性不妊症の遺伝子診断や治療が期待できる。
また、レトロトランスポゾンと機能が似ているレトロウイルスが原因の白血病やがんの治療にも応用できる可能性があるという。
Tdrd9(生殖細胞だけで働いている遺伝子が作るタンパク質)を作れない雄のマウスの生殖細胞では、遺伝情報を壊すレトロトランスポゾンが異常に増加し、細胞死を引き起こして、精巣が委縮して、精子が全くできず、無精子症による不妊となるそうです。
つまり、このTdrd9の機能異常が無精子症の原因の一つである可能性があるそうなのです。
【レトロトランスポゾン】
ゲノムを飛び回る遺伝子「トランスポゾン」の一つ。
本体のDNAからいったんRNAにコピーされて増幅し、再びDNAの中に組み込まれる。
動物の進化にかかわるとされるが、無秩序な増幅は遺伝情報を壊し、生殖にも影響する。
【参考リンク】
- 生殖細胞のゲノムを利己的遺伝子から守る新たな蛋白質を発見(2009/12/15、京都大学)
【関連記事】