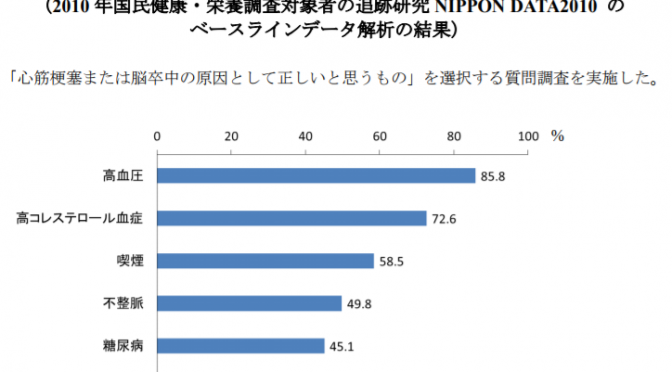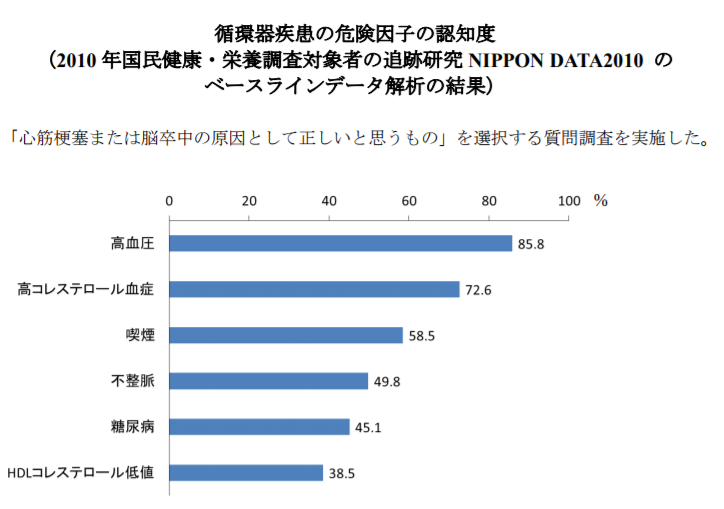【目次】
■眼底検査で糖尿病や高血圧、緑内障、加齢黄斑変性などの病気の予測ができる
by Defence Images(画像:Creative Commons)
眼底検査で糖尿病や脳卒中を予測
(2010/9/21、産経新聞)
瞳の奥にある網膜などの状態を見る「眼底検査」。
目の疾患だけでなく、高血圧や糖尿病など全身疾患を発見するきっかけにもなることから、企業の健康診断などに取り入れられている。
最近では、眼底検査が将来の病気の発症予測につながることを示唆する研究も出てきた。
専門医は眼底検査の重要性を訴えている。
眼底検査が、目の病気だけでなく、高血圧や糖尿病などの病気を発見するきっかけになっているそうです。
また、眼底検査が病気の予測につながるのではないかとする研究も行われているそうです。
■眼底検査とは
眼底検査は、目に光を当ててレンズを使って眼科医が直接のぞきこむ方法と、専用の眼底カメラで撮影して結果を分析する方法の2種類ある。
いずれの場合でも瞳の奥にある網膜や血管、網膜の外側の脈絡膜などの様子をチェックする。
■なぜ眼底検査によって病気がわかるの?
検査によって、緑内障や糖尿病網膜症、網膜色素変性症や黄斑(おうはん)変性症といった視力障害の原因となる疾患が見つかる。
眼底検査によって、緑内障や糖尿病網膜症、加齢黄斑変性などの目の病気がわかりますが、眼底検査は目の病気以外の病気の発見にもつながるのだそうです。
だが、「眼底検査は一義的には目の病気を発見し、治すためのもの。でも実は、その情報は眼科だけにとどまりません」と山形大学医学部の山下英俊教授は話す。
「内臓の血管を生きた状態で見ることができるのは網膜だけ。だから、眼底検査は内臓の血管をつぶさに見ていることと同じなのです」。
そのため、網膜の血管の変化から、高血圧や糖尿病などを早期に発見することにつながり、健康診断などに取り入れられている。
眼底検査は、内臓の血管を生きた状態で見ることができる唯一の検査であり、これによって、血管の変化から、高血圧や糖尿病などの病気の早期発見につながるのだそうです。
■眼底検査で病気の発症を予測
最近では、眼底検査によって全身疾患の発症を予測する可能性を示唆するような研究も報告されている。
山形大学医学部が山形県舟形町の住民を対象に行った研究では、血圧が正常であっても眼底検査の結果、「網膜細動脈」と呼ばれる、血管のサイズが細い人の方が太い人に比べて、5年後に高血圧を発症するリスクが高いことが明らかになった。
また、眼底検査によって発見される目の病気の一つで、視野の中心部で物がゆがんだり小さく見えてしまう「加齢黄斑変性症」も、その重症度と、脳卒中や心疾患、認知症の発症率との間に関連があることが分かってきた。
このうち脳卒中の場合では、より重症の新生血管を伴う加齢黄斑変性症は発症リスクが約2倍高いことなども判明。
少しずつだが、眼底をめぐる他疾患との関係性が解明されてきている。
ポイントをまとめます。
- 血圧が正常であっても眼底検査の結果、「網膜細動脈」と呼ばれる、血管のサイズが細い人の方が太い人に比べて、5年後に高血圧を発症するリスクが高い。
- 「加齢黄斑変性症」も、その重症度と、脳卒中や心疾患、認知症の発症率との間に関連がある
- 脳卒中の場合では、より重症の新生血管を伴う加齢黄斑変性症は発症リスクが約2倍高い
眼底検査が様々な病気の発症リスクの判断基準の一つになるようになりそうですね。
40歳を過ぎたら、ぜひ眼の検査(眼底検査)を受けましょう。