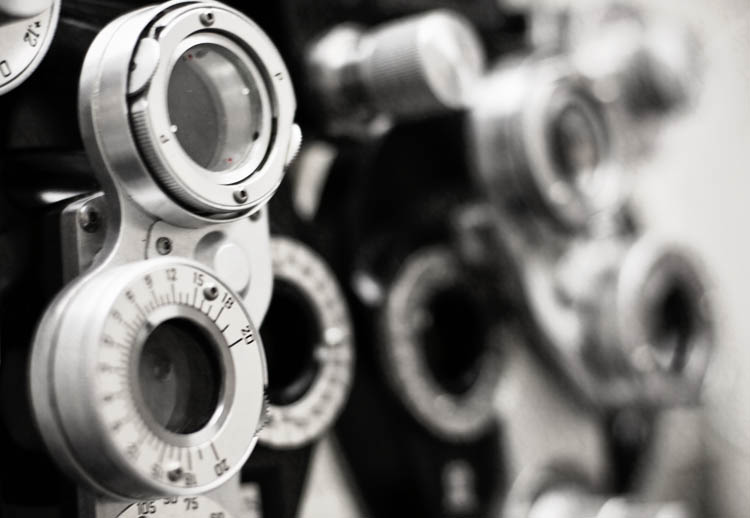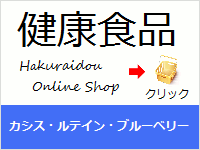> 病気・症状 > オメガ3 > 関節リウマチ患者に良い食べ物のポイントは、食事の量を適切に、痛みや炎症を抑えるオメガ3脂肪酸を摂取!
■関節リウマチ患者の食事のポイント
by Gareth Williams(画像:Creative Commons)
リウマチ患者が知っておきたい食事のポイント|あなたの健康百科
関節リウマチの患者では、関節が炎症で腫れて痛むため運動不足になったり、ステロイド薬を服用したりするので、肥満や糖尿病、脂質異常症といった合併症が起こりやすくなる。
関節リウマチ患者が知っておきたい食事のポイントについて、神戸大学大学管理栄養部の赤毛弘子管理栄養士によるアドバイスがされています。
ポイントを簡単にまとめると、次の通りです。
●肥満は関節への負担がかかり、また合併症(糖尿病・脂質異常症)になるリスクが高まるため、体重や食事の量・内容をしっかりとコントロールする
●リウマチの痛みや炎症を抑えることが期待されるオメガ3脂肪酸を摂取する
飽和脂肪酸は肉などに含まれていて、痛みや炎症を強める恐れがあるといわれています。中性脂肪やコレステロールを増やすので、あまり取り過ぎないようにしたいところです。一方、不飽和脂肪酸の多価脂肪酸にn-3系脂肪酸というものがあります。これは青魚に多く含まれていて、炎症を抑えたり動脈硬化などを防いだりしてくれるといわれています
サッカー選手はオメガ3を摂ってケガしにくい体質を作ろうによれば、オメガ3には炎症を抑える効果があり、ケガを予防するためにも、オメガ3を摂って、それ以外の油を摂らないことが望ましいそうです。
消費者庁の食品の機能性評価モデル事業」の結果報告(平成24年4月)によれば、EPA/DHAの「関節リウマチ症状緩和」の機能に関して総合評価はAとなっています。
オメガ3脂肪酸には、青魚などに多く含まれるEPAやDHA、エゴマ油などに含まれるαリノレン酸が含まれています。
【関連記事】
ただその際に気を付けたいのは、油の摂取量。
今までの油とオメガ3脂肪酸の油を置き換えるようにしたほうが良いようです。
オメガ3脂肪酸はえごま油、シソ油、亜麻仁油(アマニ油)、くるみ、青魚、緑黄色野菜、豆類などの食品に含まれています。
→ オメガ3脂肪酸|オメガ3の効能・効果・食べ物・オメガ3ダイエット について詳しくはこちら
→ DHA・EPA について詳しくはこちら
→ えごま油 について詳しくはこちら
■まとめ
オメガ3系脂肪酸|「統合医療」情報発信サイト 厚生労働省
2012年のシステマティック・レビューでは、海産物や魚油に含まれる種類のオメガ3は関節リウマチの症状軽減にやや有用であると結論づけられています。 このレビューの対象試験では、多数の参加者が魚油を摂取している期間に「朝のこわばり」の短縮、関節の腫れや痛みの軽減、症状管理を目的とした抗炎症薬の使用減少を報告しました。
関節リウマチの症状を緩和するためにも、食事を見直すことが重要なので、ぜひやってみてください。

【新物】島根県産えごま油(50g)|低温圧搾生搾り|オメガ3(αリノレン酸)を摂ろう! 1,944円(税込)
【参考リンク(論文・エビデンス)】
続きを読む 関節リウマチ患者に良い食べ物のポイントは、食事の量を適切に、痛みや炎症を抑えるオメガ3脂肪酸を摂取!