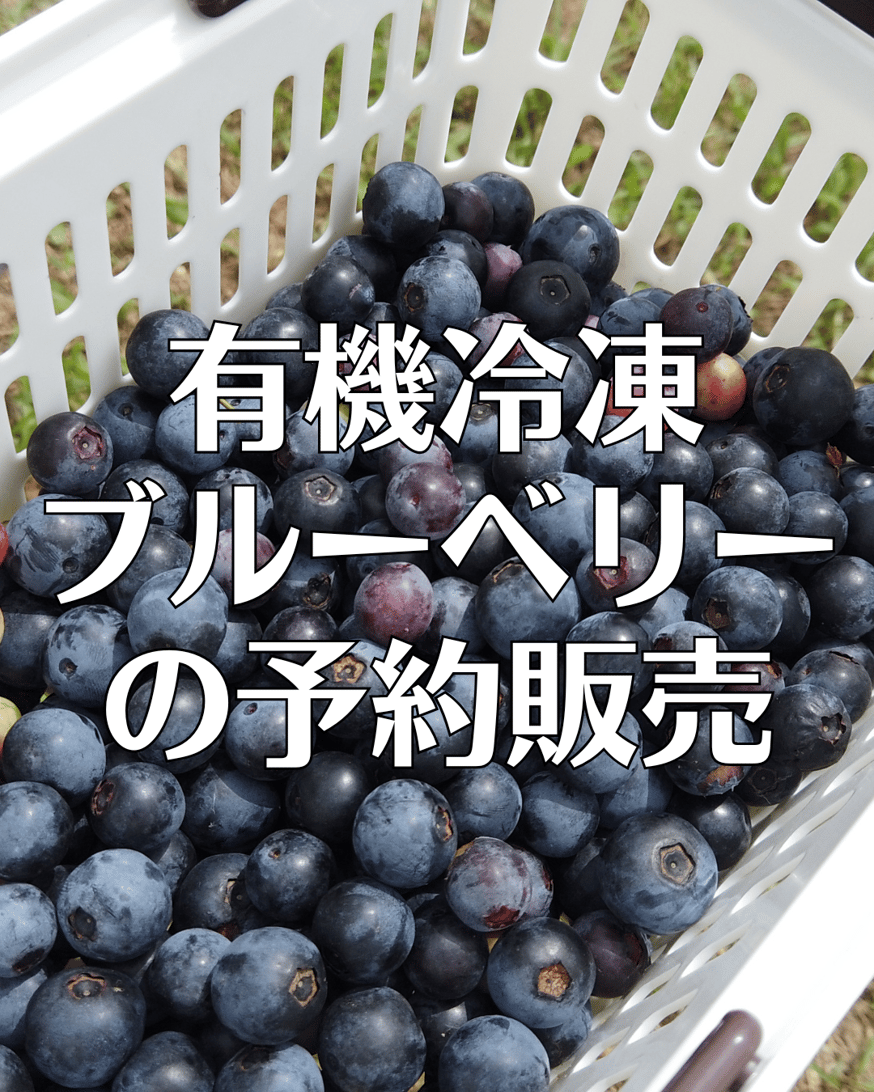Berries keep your brain sharp(2012年4月26日、ハーバード大学)で紹介されているブリガム・アンド・ウィメンズ病院(BWH)のハーバード大学研究者による新たな研究によれば、イチゴやブルーベリーといったフラボノイドを豊富に含むベリー類を長期にわたって摂取すると、高齢女性の記憶力低下を2年半遅らせることができることがわかったそうです。
→ ブルーベリーの健康効果 について詳しくはこちら
【参考リンク】
- Devore EE, Kang JH, Breteler MM, Grodstein F. Dietary intakes of berries and flavonoids in relation to cognitive decline. Ann Neurol. 2012 Jul;72(1):135-43. doi: 10.1002/ana.23594. Epub 2012 Apr 26. PMID: 22535616; PMCID: PMC3582325.
■概要
ハーバード大学の研究チームが、ブルーベリーやイチゴに含まれるフラボノイド(特にアントシアニン)が、高齢女性の記憶力低下を遅らせる効果を調査しました。
長期間(約20年)のデータから、週に2回以上ベリーを食べた女性は、記憶力の低下が最大2.5年遅れることがわかりました。
■どんな研究をしたの?
1976年から始まった「看護師健康調査」に参加した女性看護師12万1,700人の中から、1995~2001年に70歳以上だった1万6,010人(平均年齢74歳、平均BMI26)のデータを分析し、1980年から4年ごとに、参加者がどんな食べ物をどのくらい食べているかをアンケートで調査(特にブルーベリーとイチゴの摂取量に注目)を行い、認知機能テストを実施しました。
■結果
●記憶力低下の遅延
ブルーベリーやイチゴを週に2回以上食べた女性は、ほとんど食べない女性に比べて、記憶力の低下が最大2.5年遅れた。
特に、ブルーベリーを週1回以上、イチゴを週2回以上食べたグループで、認知機能の低下が顕著に抑えられた。
●フラボノイドの効果
ベリーに含まれるアントシアニン(青や赤の色素)と総フラボノイドの摂取量が多いほど、記憶力低下が少ないことがわかった。
フラボノイドは、脳の神経細胞を保護し、炎症や酸化ストレスを抑える働きがあると考えられる。
■なぜベリーが脳に良いの?
ブルーベリーやイチゴの効果は、**フラボノイド(特にアントシアニン)**によるものです。
抗酸化作用: フラボノイドは活性酸素(細胞を傷つける物質)を減らし、脳の神経細胞を老化やダメージから守る。
抗炎症作用: 脳の炎症を抑え、認知症やアルツハイマー病のリスクを下げる。
血流改善: ベリーは脳への血流を良くし、酸素や栄養の供給を増やす。これが記憶力や思考力をサポート。
神経保護: アントシアニンは脳の海馬(記憶に関わる部位)で働き、神経のつながりを強化する。
■まとめ
ハーバード大学の研究では、ブルーベリーやイチゴを週に2回以上食べる高齢女性は、記憶力の低下が最大2.5年遅れることがわかりました。
フラボノイド(特にアントシアニン)が脳の酸化ストレスや炎症抑をえ、神経を保護することでこの効果を発揮します。
他の研究でもブルーベリーやイチゴなどのベリー類に含まれるフラボノイドが健康に役立つといわれています。
【関連記事】
- ベリー類、お茶、ダークチョコレート、リンゴなど多様なフラボノイドを含む食品を摂ると病気のリスクが下がり、寿命を延ばす可能性がある!
- ブルーベリーやイチゴを食べると心臓発作を起こすリスクが1/3になる!?
毎日の食事にブルーベリーやイチゴなどのベリー類を取り入れたいですね。
→ 認知症の症状|認知症予防に良い食べ物・栄養 について詳しくはこちら
→ 【予約販売】有機JAS 冷凍ブルーベリー 500g(長崎県産)【大粒】【産直便】 3,780円(税込) の予約注文はこちら
【関連記事】
- ブルーベリーを週2-3回食べている人は糖尿病にかかる割合が低くなる!【あさイチ】
- ブルーベリーを食べると、体重や血糖値の管理(糖尿病予防)に役立つだけでなく、腸内環境を整えることで健康をサポートすることが判明!
- ブルーベリーのサプリメントによって高脂肪食ラットの腸内細菌叢のバランスの改善、全身の炎症が減り、インスリン抵抗性が改善
- ブルーベリーで認知症予防!ブルーベリーを毎日食べると記憶力やタスク切り替え能力といった認知能力を向上させる!
- ブルーベリーの摂取がメタボの人の高血圧や酸化ストレスの改善に役立つ!
- ブルーベリーのアントシアニンが糖尿病網膜症の原因となる高血糖が引き起こす網膜細胞のダメージを防ぐ!