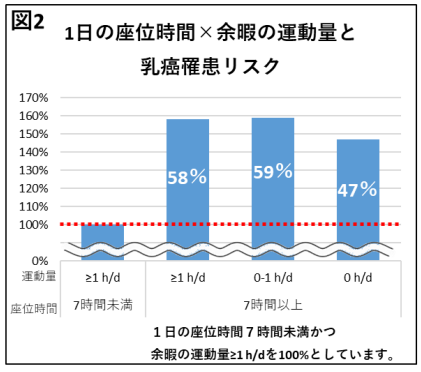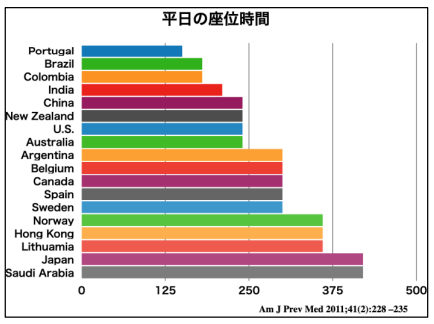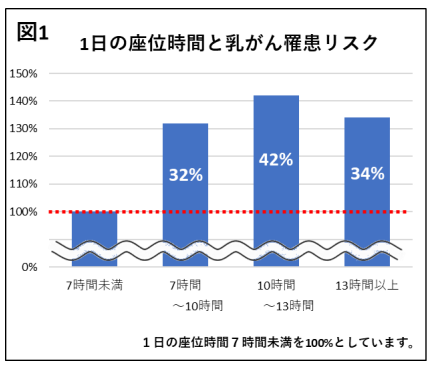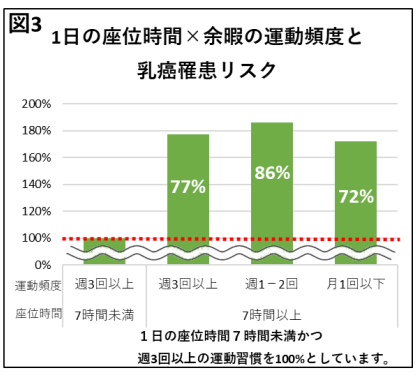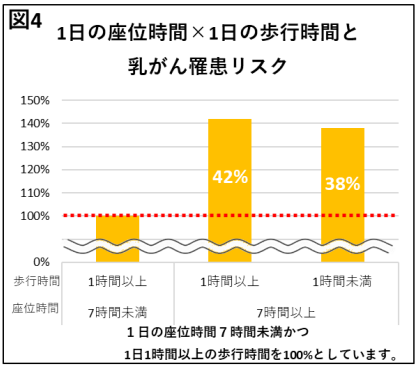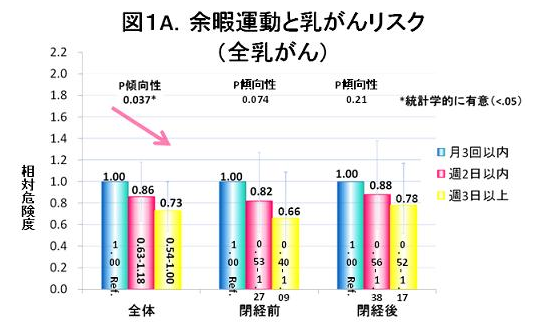トラジャ川島如恵留 体調不良で活動一時休止「お休みをとって心身の健康を取り戻したい」当面は6人で活動(2024年12月2日、スポニチアネックス)によれば、「Travis Japan」の川島如恵留(のえる、30)さんが体調不良により一定期間活動を休止すると発表しました。
コロナ禍以降、体調不良であっても無理をせずに一定期間休みをとりやすくなった気がします。
40~50代の頑張りすぎる女性は更年期症状などの体調不良の自覚率が高い!自分でできるケアのやり方!(2017年)によれば、がむしゃらだと言われた経験がある女性の方がそうでない女性に比べて、体調不良の自覚率が高いという結果が出たそうです。
仕事に熱心に取り組む女性は体調不良の自覚がありながらも頑張ってしまう方が多かったのでしょうが、体調がよくない時はいったん休むという考え方にシフトしているのではないでしょうか?
野村彩也子アナ復帰 「体調不良は業務過多によるもの」/企業でストレスの見える化するツールの活用が増える!?でも紹介しましたが、体調不良で休養していた野村彩也子アナの体調不良の原因は業務過多であり、その兆候を早期に察知できなかったことが理由として挙げられています。
健康と生産性の関係|出勤していても体調不良を感じている社員は労働生産性が下がっているで紹介した「アブセンティーイズム(疾病により欠勤している状態)」と「プレゼンティーイズム(出社こそしているものの、何らかの疾病で業務遂行に障害が起き、労働生産性が下がっている状態)」を参考に考えると、出勤していても体調不良を感じている社員は労働生産性が下がっており、それが企業の生産性損失コストの多くを占めているようです。
体調不良を押してまで頑張ってもパフォーマンスが落ちてしまっているという結果が出ています。
そのため、良いパフォーマンスを発揮するためには、日ごろからの体調に気を付けること、そして体調を崩したらしっかり休むことが大事なんですね。
【追記(2025年5月17日)】
川島如恵留(Travis Japan)に関するお知らせによれば、5月17日より活動を再開するそうです。
■まとめ
今後はストレス度をチェックしながら、仕事の大変さ・量をコントロールして、体調不良になるのを未然に防ぐことが企業にとってかかせないものになるのではないでしょうか?
大事な考え方は「未病」です。
未病とは、発病には至っていないものの健康な状態から離れつつある状態を指します。
自覚症状がない場合でも検査で異常がみられる場合や、自覚症状があっても検査では異常がない場合など、その状態は様々です。
今回のケースも本人はいろんなところでサインを出していたかもしれませんし、それを回りが察知できなかったことも考えられます。
そのサインを察知する責任を負うというのは難しいものです。
だからこそいろんなツールを活用していくのは大事だと思います。
これから未病対策のような予防医療・予防医学に取り組んでいくことは医療費の削減するためにも今後重要になっていくと考えられますし、世界的にも予防医学・予防医療の方向に進んでいるのを感じます。
ザッカーバーグ夫妻、人類の病気を予防・治療するプロジェクトで30億ドルを投資で紹介したザッカーバーグさんはこのようにコメントしています。
ザッカーバーグは「アメリカでは病気にかかった人々を治療するための支出に比べて、そもそも人々が病気にならないように研究するための支出はわずか50分の1しかない」と述べた。
ザッカーバーグさんのコメントは、病気を発症してからではなく、病気予防に重点を置くという考え方は、東洋医学の「未病」という考え方に近いと思います。
また、QOL(生活の質)の向上といった間接的なコスト削減も期待できると考えられます。
社会的インパクト投資(ソーシャルインパクトボンド)とヘルスケア分野(認知症・がん)の可能性|サキドリ↑(NHK)によれば、福岡県大川市の高齢者施設では、学習教材を使っての認知症予防への取り組みに社会的インパクト投資が使えるのかの実証実験として、高齢者100人が参加して、5か月間実験したところ、実験に参加した多くの高齢者の要介護度が下がり、公的介護費用が削減するという結果になったそうです。
※「社会的インパクト投資(ソーシャルインパクトボンド、SIB)」とは、障がい者支援や低所得者(貧困)支援、難民、失業、引きこもりの人の就労支援などの社会問題の解決と収益の両立を目指す社会貢献型の投資のこと。
また、積極的に計画・実行する人はがん・脳卒中・心筋梗塞の死亡リスクが低い|国立がん研究センターで紹介した国立がん研究センターによれば、日常的な出来事に対して、積極的に解決するための計画を立て、実行する「対処型」の行動をとる人は、そうでない人に比べて、がんで死亡するリスクが15%低く、また、脳卒中リスクが15%低く、脳卒中や心筋梗塞などで死亡するリスクが26%低いという結果が出たそうです。
その理由としては、日常的な出来事に対して、積極的に解決するための計画を立て、実行する「対処型」の人は、がん検診や健康診断を受診するため、病気の早期発見につながり、病気による死亡リスクが低下して可能性があるようです。
つまり、予防医学・予防医療を導入するということは、病気による死亡リスクが減少し、医療費の削減にもつながるということです。
今後ますます未病対策のような予防医学・予防医療に関心が高まるのではないでしょうか。