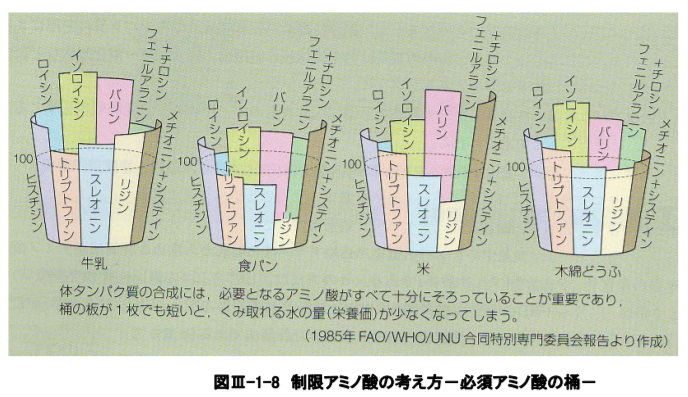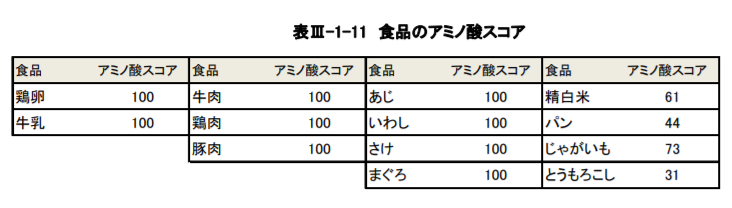運動苦手なやつ、産まれとか遺伝じゃなくて大体肉の量が足りてねえんだよな
鶏胸肉を毎日250~300g食うようになるだけで圧倒的にパフォーマンス変わってくるんで、まず食う必要がある。食わずに運動するのは虐待であってトレーニングじゃない
— 砂鉄 (@satetu4401) November 11, 2023
このツイートで気になったのは、運動が苦手な人は「生まれ」や「遺伝」ではなく、食事で摂るたんぱく質量が低いから、良いパフォーマンスができないという仮説です。
■運動と筋肉量の関係
(2021/6/11、名古屋大学)
・児童の中高強度の「身体活動」と「四肢骨格筋量」に関連が認められた。
・中高強度の「身体活動」を1日あたり1時間以上、週5日以上実施していない児童は、「四肢骨格筋量」が減少しやすい。
・世界保健機構が推奨する「身体活動」を満たしていない児童は、「四肢骨格筋量」が減少するリスクは、満たしている児童の2.34倍になる。
名古屋大学によれば、「身体活動」と「四肢骨格筋量」に関連があり、運動をしていないと「四肢骨格筋量」が減少することがわかりました。
■運動神経とは
子供の運動能力を伸ばすトレーニング|10歳頃までに素早い身のこなしや反射神経という能力は完成してしまう!?によれば、運動神経とは、目や耳など感覚器から入ってきた情報を脳が上手に処理して、からだの各部に的確な指令をだす神経回路のことです。
運動能力を運動神経で捉えた場合には、食事や筋肉量とは関係がなく、脳が体の各部に的確な指令を出し、その指令通りに体を動かすことになります。
【関連記事】
■食事と筋肉と身長の関係
●身長が伸びるメカニズム
筋トレ(筋肉を鍛える)をすると背が伸びなくなるのか?|子供の身長を伸ばすために必要な要素とは?によれば、身長が伸びるメカニズムは女性ホルモンの働きがかかわっており、女性ホルモンが分泌されると、成長ホルモンの分泌を介して身長が伸びるように働くのですが、その一方でその分泌量が多くなると、今度は骨に働きかけて身長の伸びを停止させてしまうそうです。
つまり、身長が伸びるメカニズムは筋肉の量との関係というよりも、ホルモンの分泌量との関係が深いというわけですね。
身長は遺伝が大きな要因を占めていますが、食事(たんぱく質や亜鉛をしっかりと摂る)・運動・睡眠といった環境要因も影響を与えています。
●体重が増えないと身長も伸びない
国立成育医療研究センター堀川玲子医師によれば、急激に身長が伸びる“成長スパート期”の山がいかに高いか、山の時期がどのくらいか、期間がどのくらいかというのが、将来の身長を左右するそうです。
一番伸びる時期は、女の子11歳頃、男の子13歳頃。https://t.co/Y2L5FePKVZ— ハクライドウ@40代・50代向け健康美容ブログ (@hakuraidou) 2019年1月2日
国立成育医療研究センターの堀川玲子医師によれば、子どもの身長が急激に伸びるタイミングは2度あり、1度目は、生まれた直後、そして2度目は女の子では11歳頃、男の子では13歳頃なのだそうで、“成長スパート期”の山がいかに高いか、山の時期がどのくらいか、期間がどのくらいかというのが、将来の身長を左右するそうです。
また、体重からでも成長スパートはわかる|順天堂大学によれば、体重が増えないと身長も伸びないそうです。
身長が急激に伸びる時期に体重も同じように増えることから、体重計で体重を計ることでも「成長スパート」のタイミングを知ることができるそうです。
つまり、運動能力を身体能力(体の出来具合)としてとらえると、適切なタイミングで適切な量・バランスの食事を摂る、全身運動をする、しっかりと睡眠をとることが運動能力をアップすることにつながると考えられます。
■たんぱく質摂取と筋トレによる筋力増強効果
たんぱく質摂取と筋力トレーニングによる筋力 (筋肉が発揮する力)増強効果を、メタアナリシスを用いた詳細な用量反応解析で解明
(2022/11/24、早稲田大学)
①たんぱく質の摂取による筋力増強の大きさは、総たんぱく質摂取量が約1.5 g/kg体重/日に達するまで、1日当たり0.1 g/kg体重(体重60 kgの人ではたんぱく質6 g)多くなるごとに、0.72%ずつ高まることが分かりました。高齢者の加齢による筋力低下と比較すると、約半年分の筋力低下の軽減に相当します。
②年齢や性別に関わらず、たんぱく質摂取量の増加は筋力トレーニングによる筋力増強効果を増幅させることを確認しました。
③たんぱく質摂取量の増加による筋力増強効果は、筋力トレーニング併用時にのみ発揮されることが明らかとなりました。
この研究によれば、筋トレをする際にたんぱく質を摂取することで筋力増強効果が大きくなることが期待されます。
■まとめ
以上をまとめます。
1)食事をすることで運動神経をアップすることは直接は関係しない
2)運動することで筋肉量を維持
3)適切なタイミングで適切な量・バランスの食事を摂る、全身運動をする、しっかりと睡眠をとることが運動能力をアップすることにつながる
4)運動する際にたんぱく質摂取量を増やすことで筋力増強効果が得られる