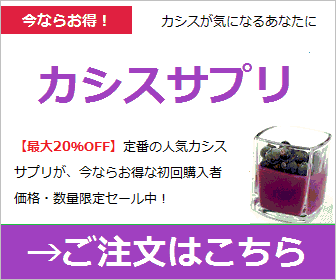> 健康・美容チェック > 低血圧 > 本態性低血圧・起立性低血圧の症状・原因・改善(運動)とは?
「私、低血圧なんです」と普段からさらっと言ってしまう人もいると思います。
しかし、低血圧の症状がひどくなると、めまい、立ちくらみ、吐き気、倦怠感、頭痛、肩こり、不眠、食欲不振など、さまざまな不快な症状に悩まされる方もいるのです。
ぜひ低血圧について一度考えてみましょう。
【目次】
■低血圧とは
by Basheer Tome(画像:Creative Commons)
疲れやすい、めまい、頭痛、ウツウツ…その原因は貧血、低血圧かも
(2014/12/25、日経Gooday)
貧血が、血液自体に問題があるのに対し、低血圧は血液を巡らす“ポンプ作用”に問題がある。心臓から血液を送り出す力や、手足の末梢から心臓に血液を送り返す力が低下し、全身の血液循環が悪くなる状態だ。
低血圧は、血液を循環させるためのポンプ作用に問題があると考えられます。
心臓から血液を送り出す力や、手足などの末梢から心臓に血液を送り返す力が低下することで、血液循環が悪くなっています。
■低血圧が病気である条件
健康常識のウソ・ホント:見過ごされがちな「低血圧」。低すぎるのは問題!
(2008/11/20、毎日新聞)
「一般に、上の血圧(収縮期血圧)が100mmHg未満を低血圧といいますが、数値が低いだけでは病気とはいえません。
低血圧が原因で毎日のようにめまいや吐き気などがあって、社会生活を送るうえで不自由さを感じるときに病気と見なされます。
つまり、低血圧は症状で困っていることが病気の条件なのです」
つまり、低血圧が病気である条件とは、2つの条件がそろったものをいうようです。
- 上の血圧(収縮期血圧)が100mmHg未満
- めまいや吐き気などの症状に悩まされ、社会生活を送るのに不自由さを感じる
ただ、低血圧の症状は、自律神経失調症、軽いうつ病などの病気にも当てはまるものがあるため、誤った診断を受け、低血圧が見落とされるケースもあるそうです。
■本態性低血圧
疲れやすい、めまい、頭痛、ウツウツ…その原因は貧血、低血圧かも
(2014/12/25、日経Gooday)
低血圧の定義は基礎血圧(朝、起きてすぐに測定した数値)の最大値が100mmHg未満とされている。まれに甲状腺の病気などが隠れていることもあるが、一般的に低血圧といえば、体質が原因の「本態性低血圧」だ。
自覚症状を伴う場合を「本態性低血圧症」という。
本態性低血圧ははっきりとした原因はわかっておらず、体質が原因と考えられます。
女性は、女性ホルモンの影響で血管が拡張しやすく、血液を押し出したり、押し返すポンプ作用が弱い。
ただ、低血圧の症状を訴える女性が多いことから、女性ホルモンの影響でポンプ作用が弱いことが原因の一つとして考えられます。
■本態性低血圧の症状
疲れやすい、めまい、頭痛、ウツウツ…その原因は貧血、低血圧かも
(2014/12/25、日経Gooday)
典型的な症状は、朝なかなか起きられないこと。そして、疲れやすく、無理がきかない。そのほかにも、めまい、頭痛、耳鳴り、疲労感、倦怠(けんたい)感、肩こり、動悸、息切れ、胃腸虚弱、不眠などさまざまな症状が表れる。
■典型的な低血圧の女性
疲れやすい、めまい、頭痛、ウツウツ…その原因は貧血、低血圧かも
(2014/12/25、日経Gooday)
頭痛
脳への血流が少ないため
顔色が青白い
血液循環が悪い上に、寝不足、疲労感が重なって顔色が青白いのが特徴
猫背気味
自律神経が乱れると姿勢菌がうまく働かないため猫背気味になる
肩こり
筋肉への血流も滞り、肩が凝る
年齢より若く見える
体内に水分がたまりやすく、肌がみずみずしく見えるため、若見えする
■起立性低血圧
疲れやすい、めまい、頭痛、ウツウツ…その原因は貧血、低血圧かも
(2014/12/25、日経Gooday)
立ったときに、下半身にたまった血液を心臓に押し上げる力が弱く、脳に十分な血液が回らなくなり、立つと血液が下がってしまうことで起きる。血圧を一定に保つ機能をコントロールする自律神経のトラブルが関係している。本態性低血圧症と同様に、朝起きられない、めまい、動悸といった症状も伴う。
低血圧には、急に立ち上がった時に立ちくらみを起こす「起立性低血圧」というものもあります。
その原因は何なのでしょうか。
健康常識のウソ・ホント:見過ごされがちな「低血圧」。低すぎるのは問題!
(2008/11/20、毎日新聞)
原因は、「心臓のポンプの働きが弱いのではなく、血圧を調節している脳の視床下部にある血圧調節中枢の応答が悪いこと」
起立性低血圧は、心臓のポンプの働きが弱いためだと思っていましたが、実は、脳の血圧調節中枢の応答が悪いことが原因だったとは知りませんでした。
また、記事によると、起立性低血圧は、思春期の子供だけの病気ではなく、最近では、高齢者にも多いそうです。
それも特に多いのが、食後だそうです。
食事をすると血液が胃に集まり、脳の血液が不足してクラクラしてしまうのだそうです。
■低血圧の改善には運動
では、低血圧を解消するにはどうしたらよいのでしょうか。
健康常識のウソ・ホント:見過ごされがちな「低血圧」。低すぎるのは問題!
(2008/11/20、毎日新聞)
「低血圧の原因は血圧調節中枢の応答の悪さ。
その状態を改善する薬はありません。
血管収縮薬が使われることもありますが、効き過ぎてしまうのが問題です。
運動は交感神経と副交感神経のチャンネルの切り替えを早くするのに役立つのです」
低血圧の改善には、運動がよいそうで、運動が、交感神経と副交感神経の切り替えを早くするのに効果的なのだそうです。
さらに、記事の中で、低血圧改善のためのおススメの運動も紹介しています。
中野教授が勧めるのは、心拍が少し上がる程度の運動で、ジョギング、自転車こぎ、エアロビクス・エクササイズ、水中ウオーキングなど。
ただし、もともと低血圧の人は血の巡りの調節がうまくいかないので、運動前にはウオーミングアップ、運動後はクールダウンを充分に行うことが大切だと強調します。
低血圧の方は、運動を積極的にとりいれていきたいですね。
今注目のスロートレーニング(スロトレ)などもよいかもしれません。
また、起立性低血圧による立ちくらみの場合は、弾性ストッキングを使うことで、下半身の血液が押し上げられるのを助けてくれます。
医療用弾性ストッキングは、足に適度な圧力を加えて余分な血液がたまることを予防し、足の深部にある静脈への流れを助けてくれます。
【関連記事】
低血圧をよくある症状だと見過ごさず、注意して低血圧を改善していきましょう。
→ 低血圧とは|低血圧の症状・改善・数値・原因・食事 について詳しくはこちら
【低血圧 関連記事】
続きを読む 本態性低血圧・起立性低血圧の症状・原因・改善(運動)とは?