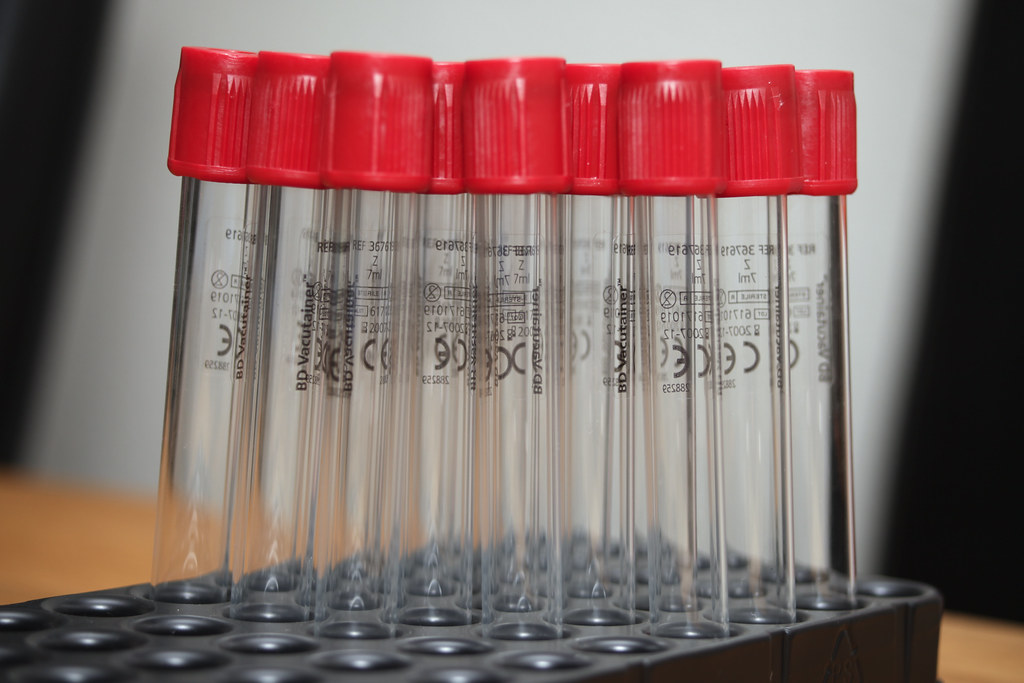by Martin Alvarez Espinar(画像:Creative Commons)
> 健康・美容チェック > メンタルヘルス(うつ・鬱病・不安) > 運動を続けるとストレスに強くなる?その科学的根拠とは?
■運動を続けるとストレスに強くなる?その科学的根拠とは?
運動がストレス耐性アップに効く科学的根拠とは?
(2009/11/27、ライフハッカー)
米紙「ニューヨークタイムズ」では、運動とストレスとの関係を脳の働きから解き明かした研究内容を紹介しています。
米プリンストン大学の研究チームでは、じっと座っているネズミと、活動的に走り回るネズミにおいて、脳の動きを比較。
それぞれのネズミを冷たい水に突っ込んでみたところ、いずれのネズミの脳でも、水につけられたことによるストレス反応が見られたそうですが、活動的なネズミのほうが生化学的にも、分子的にも概して穏やかな反応だったとか。
走ることで生まれる細胞がストレスからの影響を受けづらくする緩衝材になっているからだそうです。
また別の実験によると、ストレス負荷をかけて無力感や不安を与えたネズミは、脳でのセロトニンの活動が活発であった一方、ストレスをかける前に数週間運動させたネズミはセレトニンの活動が少なく、不安感や無力感につながりづらかったとのことです。
これらの実験結果と考察から、運動がストレス耐性に効果的であることが脳の動きからもわかったわけですが、短期間で成果が出るものではないよう。
米コロラド大学の研究によると、3週間運動したネズミには、ストレスに対する脳の働きに特段の変化は見られなかった一方、6週間運動したネズミには変化が認められたそうです。
プリンストン大学が行なったネズミの実験によれば、活動的なネズミのほうがストレスに対して穏やかな反応を示したそうです。
その理由としては、走ることで生まれる細胞がストレスからの影響を受けづらくする緩衝材(衝撃を吸収して中身を守るクッションを思い浮かべるとわかりやすいですね)になっていると考えられるそうです。
運動がストレス耐性に効果的であることが実験によってわかりましたが、その効果は短期間では得られるものではないようです。
米コロラド大学の研究によると、3週間運動したネズミには、ストレスに対する脳の働きに変化は見られなかったようですが、6週間運動したネズミには変化があったそうです。
すべてネズミで行った実験であるため、人間も同様の結果が得られるのかどうかはわかりませんが、一つの参考として、運動を続けることがストレスに強くなる方法と考えられます。
できるビジネスマンが運動を生活習慣の一部に取り入れているのは、体力づくりや健康のためだけでなく、こういうこともあるのかもしれませんね。
「所得と生活習慣等に関する状況」のグラフから見えてくるもの|厚生労働省調査によれば、性別を問わず、運動習慣がある人ほど年収が高い、もしくは、年収が高い人ほど運動習慣を持っているといえます。
起業家の成功の秘訣は「睡眠、食事、運動」によれば、会社を経営している起業家には運動する習慣を持っている人が多いそうです。
それは、運動による健康効果を十分に理解し、感じているからなのかもしれません。
たとえば、「ON、OFFのけじめが、クレージーな発想を生む」/日本マクドナルド・原田社長(2009/11/12、プレジデント)によれば、日本マクドナルド・原田社長(当時)は、毎朝10.5キロのジョギングが日課で、週末は自転車100キロ走るそうです。
家庭でのことや仕事のことでストレスを抱えている人は、運動を続けてみてはいかがでしょうか。
【追記(2016/12/10)】
以前紹介したものはネズミの実験における運動とストレスの関係でしたが、今回紹介する記事では人における運動とストレス・精神的な健康の関係が紹介されています。
「心を強くする」には運動が欠かせないワケ うつ病の治療と予防には定期的な運動が効く|The New York Times
(2016/12/9、東洋経済オンライン)
有酸素運動の仕方によって被験者を3つのグループに分けたところ、運動量が最も少なかった男女のグループは、最も多いグループよりもうつ病を患う確率が約75%も高かった。中間のグループについては、最も運動量の多いグループよりもうつ病になる確率は約25%高かった。
有酸素運動の運動量が多かったグループのほうが、運動量が少なかったグループよりもうつ病になる確率は低かったそうです。
なぜ運動をするとうつ病の発症リスクが下がるのでしょうか?
確立した答えはまだ出ていないようですが、一つの研究がその仮説となると考えられます。
うつ病の人の運動前後の血液サンプルを調査した過去の20の研究を分析したところ、運動によってさまざまな炎症マーカーの値が著しく低下した一方で、脳の健康に寄与すると考えられるさまざまなホルモンや生化学物質のレベルが増加していた。
医学誌「ニューロサイエンス・アンド・バイオビヘイバラル・レビュー」に2月に掲載された研究によれば、運動によって様々な炎症マーカーの値が低下し、また脳の健康に良い影響を与えると考えられるホルモンや生化学物質のレベルが増加していたそうです。
男性更年期障害の対策としても運動がすすめられており、適度な運動をすることによって、男性ホルモン「テストステロン」が分泌され、うつ症状の改善が期待されます。
極端な例になりますが、1か月のハイキング生活で体はどのように変化するか?で紹介した29日間で1日8~10時間のハイキングを行なった男性の場合、ストレスホルモンともいわれるコルチゾールの値は平常が10-23μg/dLのところ、ハイキング前17.8μg/dL→ハイキング後10.8μg/dLと、コルチゾール濃度の正常範囲の最高値に達しました。
また、男性ホルモンのテストステロンは正常範囲が8.7-25.1pg/mLのところ、ハイキング前4.4pg/mL→9.9pg/mLと2倍以上に上昇しています。
先ほどの記事にも書かれている通り、検証した研究の大半は規模が小さく、調査期間も短いため、結論を出すまでには至らないようですが、一つの仮説として、「運動をするとうつ病になりにくい」と考えてよいのではないでしょうか?
【関連記事】
【ストレス 関連記事】