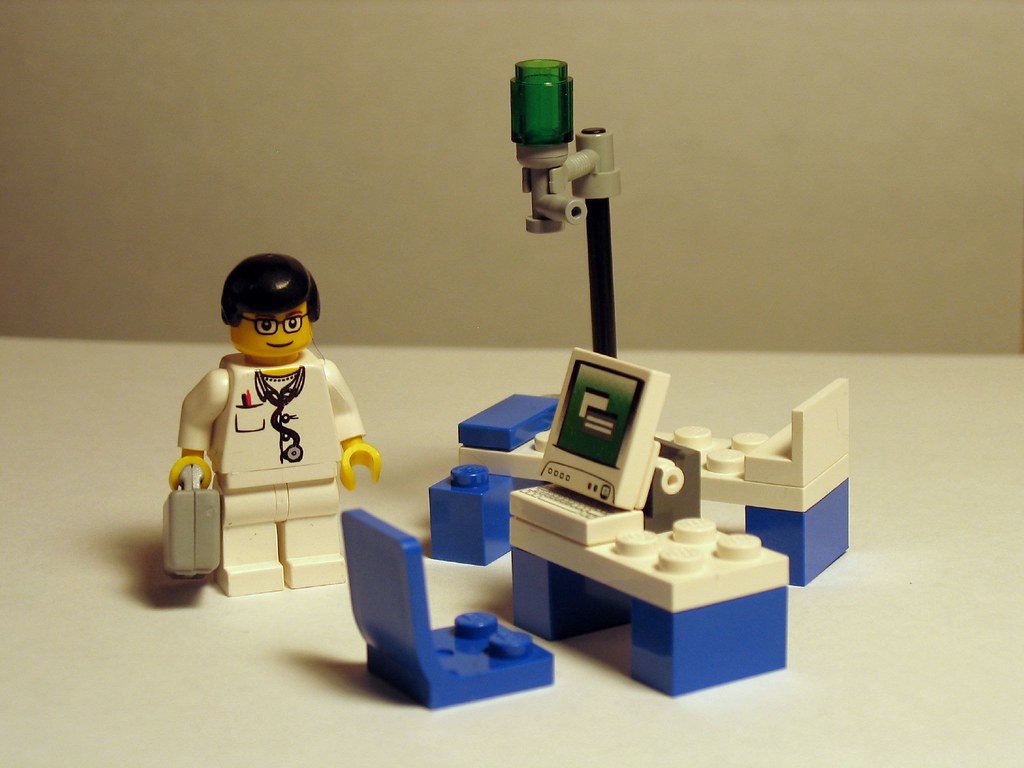■「ゲーム障害」を新たな病気として分類に加える|WHO草案「国際統計分類(ICD)」
by Vision Gaming(画像:Creative Commons)
(2017/12/28、CNN)
WHOの草案では、ゲームに熱中するあまり「個人、家庭、社会、教育、職業あるいは他の重要な機能分野に重大な障害をもたらす」行動パターンの持続あるいは再発を「ゲーム障害」と定義。特徴的な症状として、抑制が効かなくなり、たとえ悪影響が生じてもゲームの優先度が高くなる状態を挙げている。
一般的には、こうした症状が1年以上続くとゲーム障害と診断される。ただ、症状が重く、全条件を満たしている場合は、それより期間が短くても医師がゲーム障害と診断することもある。
世界保健機関(WHO)が改訂を行なっている疾病に関する国際統計分類(ICD)第11版の草案によれば、生活に支障をきたすほどのゲームに過剰に熱中する症状として「ゲーム障害」を加えることを検討しているそうです。
【追記(2018/6/19)】
(2018/6/19、朝日新聞)
ゲーム障害は、依存性のある行動で日常生活に障害をきたす精神疾患の一種とされた。日常生活に支障が出てもゲームを優先する状態が12カ月以上みられる場合で、症状が重い場合はより短期で診断できるとした。
世界保健機関(WHO)はゲームのやり過ぎで日常生活に支障をきたすゲーム依存症を「ゲーム障害」として改訂版国際疾病分類「ICD―11」の最終案に明記し、2019年5月のWHO総会で正式決定するそうです。
長時間のゲームは子供の脳の発達や言語知能に悪影響の可能性がある!?|東北大で紹介した東北大学加齢医学研究所・認知機能発達(公文教育研究会)寄附研究部門の竹内光准教授・川島隆太教授らの研究グループによれば、長時間のビデオゲームが子どもの広汎な脳領域の発達や言語性知能に及ぼす悪影響を発見したそうです。
また、なぜ虫歯は、長時間メディア(特にゲーム)利用、睡眠不足、朝食欠食の子供に多いの?|唾液分泌量が少なくなると虫歯になりやすい!?|富山大学で紹介した富山大学地域連携推進機構地域医療保健支援部門が考える仮説としては、長時間メディア(特にゲーム)利用、睡眠不足、朝食欠食といった生活習慣が自律神経の活動に影響を与え、唾液分泌の量や質に変化が起きていることにより、むし歯になりやすいと考えられるそうです。
■ゲームは悪いばかりじゃない!
今回のポイントは、”生活に支障をきたすほどゲームに熱中している”という点です。
なぜゲームOKの子はゲームNGの子より勉強時の集中力が高いのか?|#EDUCATIONによれば、「朝日小学生新聞」読者(小学1年生〜6年生の男女457人から有効回答)を対象に家庭で遊ぶゲームについてのアンケート調査を行なったところ、ゲームOKの子供はゲームNGの子供より勉強時の集中力が高いそうです。
ゲームOKの子供がゲーム禁止の子供よりも集中力が高い理由としては、「宿題や勉強を済ませてから遊ぶ」「ゲームをしていい時間が決まっている」「夜遅くにゲームをしてはいけない」家庭内のゲームに関するルールが決まっていて、ゲームをするための条件をクリアしないとゲームができないというルールを守れる子供だからこそ勉強時の集中力が高いと考えられます。
大事なことは、ゲームが悪いのではなく、ゲームに熱中し過ぎて生活ができなくなるほどになってはいけないということ。
また、最近ではeSPORTS(イースポーツ)が盛り上がっていますし、ゲーマーがかかわることで新たな発見ができたという研究もあります。
ゲーム愛好者らが酵素の構造を解析、米研究によれば、オンラインゲーマーたちが、科学者が解決できなかったヒト免疫不全ウイルス(HIV)様ウイルスの酵素の構造を解析したそうです。
ゲーマーたちは科学者とは違う発想を持っており、ゲームプレーヤーの創意工夫の能力が適切に指導されれば、幅広い科学的問題の解決に用いることができるそうです。
ゲームだからこそ夢を与えることができたという話やゲームデザイナーの方たちの発想のすばらしさ、ゲームを活用して糖尿病になりにくい生活習慣を学んだり、物理的に人が動くゲームによって街のコミュニティに良い影響を与えるといった話もあります。
#アンビリバボー
目の病気のため眼球摘出手術を受ける少年が『.hack//G.U. 』の続きを遊びたいという電話を受けて、その少年のもとに発売前のゲームを届けるという異例の対応を行なった松山洋さんの話。10年後の少年との再会、そして関係者から知らされた新たな真実とは?https://t.co/WbJmPNEWOJ pic.twitter.com/KfGovbvF0Z— ハクライドウ@Healthtech (@hakuraidou) 2018年3月1日
#ゲームデザイナー #小島秀夫 さんインタビュー|#ゲームセンターCX (2004年)https://t.co/wGMmyxuyUt#メタルギア は制約から始まった#ゲーム とは人間を知る勉強#仮想通貨 や #ブロックチェーン 、#トークンエコノミー など新しい業界を作ろうとしている人にオススメの記事です! pic.twitter.com/QcbG4t3nhb
— ハクライドウ@Healthtech (@hakuraidou) 2018年2月23日
ボストンヘルスケアシステムの研究チームによれば、2型糖尿病患者が糖尿病自己管理教育(DSME)に関するチーム対抗オンラインゲームに参加すると、血糖値(HbA1c)のコントロールが長期にわたって改善できるということがわかったそうです。https://t.co/Exl53bTlwp pic.twitter.com/1xvsXTbLzM
— ハクライドウ@Healthtech (@hakuraidou) 2017年9月7日
#Niantic の #ingress や #PokemonGo のような「物理的に人が動く」ゲームを通じて、人々が外に出て街のコミュニティに参加するようになり、ポジティブな社会的インパクトを起こすようになる!?https://t.co/jYfRuBztzK
よかったら、いいね💕・RT・フォローお願いします! https://t.co/z2hv8sP9Mv
— ハクライドウ@Healthtech (@hakuraidou) 2018年2月21日
大事なのは、ゲームとのかかわり方です。
家族や友達との会話のほうが楽しいという子どもは自然とゲームの時間に制限を設けるでしょう。
しかし、いろんな世界を見せたうえで、ゲームのほうが魅力的だと子ども自身が判断したのであれば、それでいいのではないでしょうか。
それこそ、先ほど紹介したゲーマーのように新たな発見をするような人になるかもしれませんし、eSPORTSの分野でスーパースターになるかもしれません。